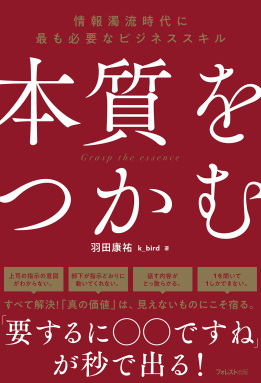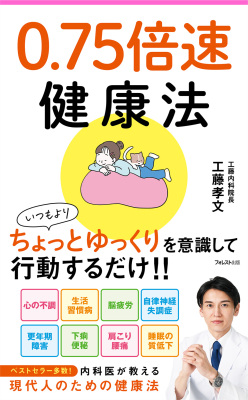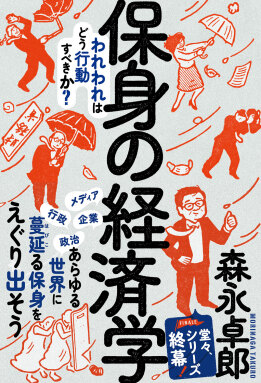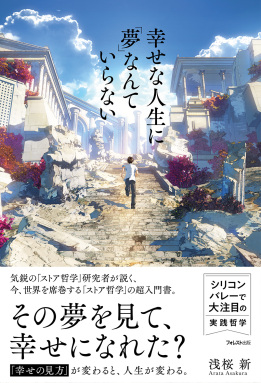今のあなたにフィットした書籍を見つけてください!
今のあなたにフィットした書籍を見つけてください!
-
物事の本質をつかむって難しいよな」「何か方法があるのだろうか?」と漠然と思ったのですが、著者の羽田康祐さんだったら書けるのではないかと無茶振りしたことがきっかけで本書が生まれました。「難しいなあ」とおっしゃりつつ、自身のこれまでの経験や学びを棚卸しし、私が期待した以上に、その方法を体系化してくださいました。抽象度の高い「本質」という言葉をここまで具体的に、そして日々のビジネスに落とし込んだ本は他にないはずです!

POSTED BYかばを
View More本質をつかむ方法が具体的に記された本!
日々の仕事や問題解決において、その本質をつかむことができれば生産性が上がるが、それができないと延々と成果は出ない。
「要するに◯◯ですね!」が秒で出る!
たとえば、次のようなケースのことだ。
◎上司の指示の意図がわからない。
◎部下が指示どおりに動いてくれない
◎何がわからないかわからない。
◎話す内容がとっ散らかる。
◎1を聞いて1しかできない。
これらに共通するのは、物事の表面にとらわれるあまり、本質を見失っていることだ。
逆に本質をつかむ力が身につけば、「要するに◯◯ですね!」と相手の話の要点をすぐにとらえることができるし、そのように理解してもらえる説明や指示ができるようにもなる。
では、どうすれば「本質をつかむ力」を身につけられるのか?
本書では、それを以下の7つの力に分解して、詳細に解説する。
第1 本質的な「意味」を見抜く力
第2 本質的な「原因」を見抜く力
第3 本質的な「目的」を見抜く力
第4 本質的な「特性」を見抜く力
第5 本質的な「価値」を見抜く力
第6 「関係」の本質を見抜く力
第7 「大局」を見抜く力
本書の構成
【第一章 本質を見抜く力とは何か?】
現代社会が「可視化」への依存を強めていく中で「本質を見抜く力」がなぜ重要なのかを掘り下げる。
【第二章 本質を見抜く7つの力】
物事の本質を見抜くうえで必要になる7つの力について解説する。
それぞれの力に対して「なぜ重要なのか?」「どのようなメリットがあるのか?」「どのような思考の手順をたどればいいのか?」について解説する。
第二章を読み進めることで、それぞれの力にはどのようなメリットがあり、どのように思考手順を踏めばいいかを体系的に理解できるはずだ。その結果、物事の本質に迫るための方法論を手に入れることができる。
【第三章 本質を見抜く視点力】
ここまで説明してきた、本質を見抜く7つの力――意味、原因、目的、特性、価値、関係、大局――は、一言で言えば「考える力」だ。しかし何かを「考える」には、その手前に「そもそも、何について考えるべきなのか?」を見極める「視点力」が欠かせない。
よって、第三章では本質を見抜くうえで極めて重要な「視点力」について紐解いていく。第三章をお読みになれば、どのような頭の使い方をすれば、自由自在に視点を切り替えることができるのか?をご理解いただけるはずだ。
【第四章 7つの本質力を身につける1週間トレーニング】
本質を見抜く力は「3日で身につく〇〇」などのビジネスハックとは異なり、日々の習慣によって少しずつ鍛え上げられていく筋トレのようなものだ。
この第四章では、本質を見抜く力を身につけるためのトレーニングガイドを提供する。
こんな人に読んでほしい!
◎丁寧に報告したつもりでも「だから何?」「要はどういうこと?」と問われがちな人。
◎言語化するのが苦手な人。
◎部下にきめ細かく指示を出しているのに、全然成長してくれないと感じているリーダー。
目次
第一章 本質を見抜く力とは何か?
第二章 本質を見抜く7つの力
第三章 本質を見抜く視点力
第四章 7つの本質力を身につける1週間トレーニング -
自他ともに認めるせっかちの私は、動画を2倍速で視聴するのは当たり前。だけどたまにその2倍速の感覚のまま仕事もプライベートも過ごしてしまって、気づいたらくたくたで心身ともにボロボロ。「きっと私は早死にするんだろうな」と思ったのが、この企画を提案したきっかけです。難しいことは何一つありません。工藤孝文先生が提案する「0.75倍健康法」をぜひお試しあれ!

POSTED BY美馬
View More「現代社会では無駄な行為として捉えられていること」を
「やることが多すぎて気持ちを落ち着かせる時間がない」
意識的にじっくり行なうことで、不調知らずの心と身体に。
「いつも何かに追われている気がして、なんだか毎日がしんどい」
などと感じていませんか?
心の不調/生活習慣病/脳疲労/自律神経失調症/更年期障害/下痢・便秘/肩こり・腰痛/睡眠の質低下——
これら不調の原因は、生産性や効率性を追い求め過ぎていること。いつもより“ちょっとゆっくり”を意識して行動するだけで、改善することができます。
ただし、それにはコツが必要です。
キーワードは「0.75倍速」。
一見無駄な行為をじっくりと時間かけて行なうことを、本書では「0.75倍行動」と名づけました。
あえて余計だと思える作業に取り組むことは、人間らしさや健常な心身を維持するために必要な行為であり、無駄を排除し過ぎることはさまざまな不調に繋がってしまいます。
本書を参考にして「現代社会では無駄な行為として捉えられていること」を意識的に、そしてじっくりと行なってみましょう。
本書の目次
はじめに
第1章 「せかせか」はどうして健康に悪いの?
つねに戦闘モードで生活する現代人
自律神経のバランスを崩す倍速行動
そもそも焦らなければイライラもしない
人間はまだタイパを求めてはいけない
戦闘モードが脳疲労の原因に
マルチタスクは脳の天敵
脳疲労から抜け出すための3つの方法
頭を空っぽにするためのToDoリスト
人間が1日にできる決断の数は限られている
行動スピードの変化で得られる気づきv もう悩まない人間関係をつくる秘訣
日常にゆっくり時間を取り入れよう
0.75倍速で生きると見えてくる本来の自分
第2章 自律神経の乱れはあらゆる不調のはじまり
心と身体の調子を整える自律神経
交感神経と副交感神経の働き
心身を休ませるために必要な準備の時間
いろいろな不調を生む神経バランスの乱れ
神経バランスを乱れさせる4つのストレス
男女ともにホルモンバランスの変化には要注意
自律神経の状態を把握しよう
健康の秘訣はニュートラルであり続けること
過剰に働いている神経に気づく方法
「やめること」が不調から抜け出す第一歩
3つのNG習慣─その1「不規則な生活」
健康のためには欠かせない日光浴と朝食
3つのNG習慣─その2「運動不足」
運動不足解消のポイントは背筋と呼吸
3つのNG習慣─その3「身体の冷え」
切っても切り離せない自律神経と腸の関係
積極的に摂取したい高食物繊維の食材
第3章 日常に「0.75倍速」を取り入れる
日本人の過半数が倍速視聴常習者
0.75倍速で動画を視聴する
スローテンポの音楽で散歩する
りんごの皮はちぎれないようにむく
白米を玄米に替える
食事中に箸を置いて食レポする
急行は見送って各駅停車に乗る
ゆっくり動くものを目で追う
書き出すことで邪念を取り払う
コーヒーを淹れるならハンドドリップで
時間の流れに身を任せられる趣味を持つ
日常に森林浴の時間をつくる
美しい所作を心がける
話は最後まで聞いてゆっくり答える
集合時間より早く到着しておく
第4章 心の不調はゆっくり時間で解きほぐす
いつでもどこでもできる呼吸法
安定感を与えてくれるマインドフルネス瞑想
忙しいアピールは自分を失くしている証拠
自分と対話する時間を確保する
「やるべきことリスト」よりも「好きなことリスト」
とにかくあらゆることに感謝する
自分も相手も気分がよくなる「感謝アラーム」
「八正道」でいまの生活を大切に感じよう
苦手なことはどんどん人に頼る
0.75倍速の遠回りが可能性をひらいてくれる
仕事が終わらないときはいさぎよく諦める
「諦める」は本来前向きな意味を持つ言葉
自分を最優先にする時間をつくろう
デジタルデバイスから距離を置く
読書は最強の0.75倍速行動
第5章 ゆっくりストレッチで病気を予防する
肩こり解消で自律神経の不調も改善
首・手首・足首ストレッチで血流促進
お手軽太極拳で気分もスッキリ
ラジオ体操はじつはすごいストレッチ
健やかな暮らしのための「0.75倍速ラジオ体操」
おわりに -
本書は、精神科医のTomy先生からのアドバイスと、それぞれのその内容を収録した漫画で構成されています。心も体も疲れてしまっているとき、「スマホばかりを見てしまって、なかなか本が読めない」なんて人も多いのではないでしょうか。そんな時こそ、本当に必要なのは、こうした本を読むことだと思います。
パラパラとページをめくってみてください。しろちゃんとその仲間達、そして、Tomy先生のアドバイスが、悩みを抱える人に寄り添い、勇気づけられると思います。
POSTED BY時
View More漫画で楽しく学ぶ アナタの心の守り方と癒やし方
「自分を好きになれない」
「人に頼れない」
「相手の理想を演じて本当の自分が出せない」
「返信が遅かったり、相手が不機嫌だと不安になる」
「親が何にでも口出ししてくる」
アナタは、こんな気持ちに身に覚えがありませんか?
これらは、“自分を大事にできていない”ことで抱きがちな
お悩みの例です。
「では、自分を大切にするにはどうしたらいいの?」
そう疑問に思う人もいるでしょう。
近年、「自分を大切にすること」が重要であると、
しばしば耳にしますが、いざ実践するとなると
どうしていいのかわからないでいる人は
少なくないと思います。
精神科医であるTomy氏は、
本書の中で、
「自分を大切にすることは、自分を後回しにしないこと」
だと言います。
「自分を後回しにしない」とは、
一見単純なことのようですが、
生産性や高い成果が求められる、
今の社会生活の中では、
難しいと感じる人は多いはずです。
そしてTomy氏は、本書の中でこのようにも語っています。
―――
私は職業柄、さまざまな理由で
生きづらくなった方のお話しを聞きます。
その生きづらさは、ほとんど全てと言っても良いぐらい、
自分を後回しにして、大切にしていないことから発生しています。
たとえば、次々に職場の人が辞めていき、
自分の仕事量が増え、いっぱいいっぱいになってしまった人。
「自分が抜けるとみんなに迷惑がかかるから、どうにもできない」
とつらそうに語ります。
こんな状態になっても頭の中にあるのは、
職場のこと、上司のこと、同僚のみんなのことなのです。
―――
つまり、自分をつい後回しにしてしまう人は、
他人を思いやる優しい人、
責任感の強い人。
そんな、自分を後回しにしがちなアナタには、
可愛らしいキャラクターがたくさん登場する
本書をオススメします。
本書は、主人公の“しろちゃん”とその仲間たちが
自分を後回しにしてしまう人が抱えがちなお悩みに向き合い、
それを乗り越えるストーリーを漫画で収録しています。
まずは、気になる項目を開いていただければ、
さらっと読み進められるはずです。
“しろちゃん”達と一緒に、
自分を大切にする習慣を実践してみてください。
気になる本書の内容
本書の内容は以下のとおりです。
はじめに 「自分を大切にする」とは?
第1章 自分を大切にするための仕事の習慣
報連相が苦手で話すタイミングもわからない
自己嫌悪の気持ちを引きずってしまう
イライラしている人がいると何も手に付かない
人に頼ることができない
アイデアや提案を他人が自分の手柄にしてしまう
失敗をいつまでも引きずってしまう
自分に何が向いているのかわからない
自分の意見を口に出せずつい飲み込んでしまう
第2章 自分を大切にするための人間関係の習慣
他人を優先してばかりで自分に時間を使えない
何を話して良いかわからず、会話も続かない
どうせ自分は嫌われるのだと思ってさびしくなる
悩みがなさそうと言われるけれど元気で明るいのは人前でだけ
自分が誘ってばかり/誘うことが苦手
他人の言葉や態度を悪いほうに受け取ってしまう
友達の作り方がわからない
相手のために頑張っても怒りを買ったり文句を言われる
つい馬鹿にしたり嫌味を言っていつも後悔してしまう
他人のちょっとした言動にすぐ怒りを覚え爆発しそうになる
第3章 自分を大切にするための自分自身の習慣
どうしたら自分を好きになれるのか
できる人に呆れられている気がしてつらい
自分がどうしたいという気持ちや意見がわからない
いつも焦る気持ちで落ち着かずあまりリラックスできない
自分はダメだと否定する言葉ばかりが出てきてしまう
やりたいことはあるのになかなか取り掛かれない
他人の言葉や行動によって自分の考えもすぐ変わってしまう
予定がない日があると落ち着かず無理にでも予定を入れたくなる
何をするにもハードルが高く感じ自信が持てない
人のために尽くすのは好きだが人に何かをしてもらうのは苦手
好き嫌いが激しくちょっとしたことにも嫌悪感を持ってしまう
ストレスを感じるとスマホを触らずにはいられない
死にたいとは思わないけれど生きたいとも思えない
第4章 自分を大切にするためのパートナーシップの習慣
相手の理想を演じてしまい本当の自分を出せない
相手からの好意を感じると急に気持ち悪く感じてしまう
返信が遅かったり不機嫌だと不安でたまらなくなる
付き合いはじめるとこの人で良いのか不安になる
第5章 自分を大切にするための家族関係の習慣
気持ちを察してあげないと冷たいと言われる
親への憤りや怒りの気持ちを持て余している
大人になっても親が何にでも口出ししてくる
家族だから仲良くしたいが兄妹と折り合いが悪い
親を差し置いて、自分だけ幸せになってはいけないと感じる
親が兄妹や世間の優秀な人と比較してくる
おわりに 人生はモノの見方1つで変わる -
『ザイム真理教』『書いてはいけない』『がん闘病日記』…累計78万部突破の森永卓郎シリーズ、堂々終幕!View More
2025年に入り、2024年中はなんとか小康状態を保っていたがんが、腹部に転移していることが確認された。私は自らに残された時間をはっきりと意識するようになった。
ただ、世の中は遅々として変わらない。むしろ保身の姿勢は、あらゆる分野で拡大している。それが本書を執筆しようと考えた最大の動機だ。
本質を追究するのではなく、目先の問題が発生しないようトラブルの回避に専念する。それこそが〝保身〟だ。読者のまわりにも、自らの処遇や地位を守るために、問題を先送りしようとする人がたくさんいるかもしれない。彼らのそうした行動こそが、私は日本社会を低迷させる大きな原因になっていると考えている。
もくじ
まえがき
放送禁止用語はなぜ生まれたか?
波風を立てない最良の方策
大手メディアで生き残る方法
第1章 教育現場の保身
なぜ、小・中学校教員のなり手が減ったのか
マニュアル化する教育現場
企業が銘柄大学を採用したがるワケ
「大企業」志向の合理性
第2章 職場の保身
中高年社員の〝合理的〟判断
三和総研で目撃した銀行員の異常な世界
クソどうでもいい仕事
三和総研の大改革
偉大な戦略家
第3章〝金融村〟の保身
金融村は「株価が下がる」と言えない
私が株価暴落を予測する、これだけの理由
エヌビディアの繁栄はあと数年の命
バブル崩壊の予兆
第4章 大手メディアの保身
『ザイム真理教』ベストセラー後の意外な〝効果〟
なぜ私は大手メディアから干されたのか?
財務省を擁護した朝日新聞
大手メディアの自殺行為
第5章 ザイム真理教の保身
〝保身メディア〟を見分ける方法
財務官僚はこうして出世する
恨みをため込んでいた日銀と銀行業界
金融引き締めでトクしたのは誰?
第6章 立憲民主党の保身
「年収の壁」引き上げをつぶしたのは誰か?
2人の強烈な増税派
増税派誕生のカラクリ
第7章 官僚の保身
「官僚天国」への歩み
「一銭も払わない」は筋が通らない
「マイルド官僚」の「マイルド天下り」
厚労省は火事場泥棒だった
休まず、遅れず、働かず
月で暮らすという〝妄想〟のために
「異次元の少子化対策」はこうして失敗した
少子化対策でトクする人、損する人
「子ども・子育て支援納付金」は〝ついでに〟徴収
「適齢期」をすぎた男女には…
第8章 若者の保身
「どんなときに一番幸せを感じますか?」
政府が言い続けるウソ
企業の儲けはどこへ行く
高齢者は年金をもらいすぎか
給付は下がり、負担は上がる
少子化を止める3つの秘策
〝さしB〟の導入コストを検証する
世代間格差を一瞬で消すウルトラC
あとがき――われわれはどう行動すべきか
テレビを見ない、新聞を読まない――グレート・リセットのために①
価格弾力性を高める――グレート・リセットのために②
働かない――グレート・リセットのために③
投資をしない――グレート・リセットのために④
「面従腹背」で、選挙で鉄槌――グレート・リセットのために⑤
われわれに残された重要な役割
【発行】三五館シンシャ/【発売】フォレスト出版 -
著者の浅桜さんに初めてお会いしたのは、2024年1月末のこと。現役のアニメプロデューサーでありながら、「ストア哲学」の研究者でもあります。そのときに浅桜さんからお聞きした「ストア哲学」のお話は、私たち現代人が生きやすくなる最高の教科書であることがよくわかりました。そこで、アニメプロデューサーでアニメの脚本も手掛ける浅桜さんの類まれなる才能を最大限に発揮していただき、難解なストア哲学を実践的なエンタメとして現代のストーリーに落とし込んで解説いただいたのが本書です。
夢に向かって頑張っているのに、結果が出ない一人の青年が、ふと立ち寄った「サウナ」で、不思議な男と出会う。「そうか。だから、君は幸せになれないんだな」と挑発的なことを言う男との会話の中で、男の語る「幸せの見方」に魅了されていく――。
そんなストーリーに至るまでにも、テーマ設定や登場人物のキャラクターについてもいろいろ意見を交換させていただき、アニメ制作の一端を垣間見る、貴重な機会にもなりました。カバーイラストには、人気イラストレーターのわいっしゅさん(風景)、ぽちさん(人物)という最強コンビに描いていただけたことも最高の体験でした。
各界のスペシャリストのご尽力のおかげで、ともすると難解で、挫折されがちな「ストア哲学」の重要エッセンスをわかりやすくまとまった1冊に仕上がりました。
POSTED BY森上
View More【シリコンバレーで大注目の実践哲学「ストア哲学」の
「なんで、まわりばっかりうまくいって、僕はうまくいかないんだよ」
重要エッセンスをストーリー形式でわかりやすく解説】
夢に向かって頑張っているのに、結果が出ない一人の青年が、
ふと立ち寄った「サウナ」で、不思議な男と出会う。
「そうか。だから、君は幸せになれないんだな」
挑発的なことを言う男との会話の中で、
男の語る「幸せの見方」に魅了されていく――。
*
今、シリコンバレーをはじめ、
世界中を席巻している実践哲学
「ストア哲学」をご存じでしょうか?
「ストア哲学」は、2000年以上前、
困難な状況でも折れないマインドを養うことを
目的としたギリシャ哲学の一派として知られ、
現代の自己啓発関連書の源流ともいわれています。
そんな「ストア哲学」は、
現実的で、ストイックな哲学というイメージが強いですが、
ひと言で言うと、【幸せの見方】を教えてくれる哲学です。
「ストア哲学」は、
2000年超の時を経て、
今、シリコンバレーをはじめ、
世界中の人々に爆発的に注目されています。
ただ、
原書は読み進めるにはとても難しく、
途中で読むことを挫折する人もいます。
でも、
ストア哲学で語られている内容は、
経済至上主義の中で競争を強いられている
現代社会に生きる私たちにとって、
幸せに生きるためのヒントが詰まった哲学なのです。
内容はとても役立つのに、
読んで理解するのが難解な「ストア哲学」を、
ストーリー仕立てでわかりやすく仕上げたのが本書です。
キーワードは、
幸せな人生には、
「目標」は必要だが、
「夢」はいらない。
夢を持って生きよう。
すると、あなたを幸せな人生に導いてくれる――。
そんな私たちが思っている一般的な常識を
ひっくり返してくれるのが、
「ストア哲学」です。
◎「夢」の正体
◎「今」を使いこなす
◎目標は必要だが、夢はいらない
◎夢なしで目標をつくる方法
◎人生における「危険」の値打ち
◎限られた「時間」の使い方
◎「別れの悲しみ」との向き合い方
などなど、
私たち現代人を幸せな人生に導く
「生きる」ヒントが満載の1冊です。
本書を通じて、
あなたらしい「幸せの見方」を手に入れて、
これからの人生を謳歌してください。
気になる本書の内容
本書の目次は以下のとおりです。
はじめに
第1章 僕たち、まだ本気出していないだけ?
◎この何もない、普通の毎日が、自分が夢見た将来だったのか?
◎「普通の人生」とは、傷つかないで済む魔法の言葉!?
◎何者かになる人生、どうすればなれる?
第2章 「幸せの見方」を知ると、人生は変わる
◎夢と現実のはざまで
◎現実から逃げたい
◎熱気との格闘、湧き出る思い
◎不思議な男との出会い
◎だから幸せになれない!?
◎「そうか。だから、君は幸せになれないんだな」
◎なぜ夢や成功と、幸せになることは別問題なのか?
◎幸せの見方、幸せの検証
◎人生を整えるサウナ、誕生
第3章 「夢」の正体
◎「常識」という滞留物を流し去り、「思考」という血を巡らせる
◎「夢は人生に必要だ」という常識は、本当に正しい?
◎「夢」が危険である、3つの理由
◎【理由①】夢は未来に返済を延期した借金
◎【理由②】夢とは本質的には叶わないもの
◎【理由③】夢を叶えるために今の時間を失うな
◎「夢」の正体――3つの「夢が危険な理由」の共通点
◎「夢」とは現代の宗教!?――夢という詐欺師に騙されるな
◎欲望や誘惑を掻き立てられる時代、幸せのために私たちが求めるべきもの
第4章 「人生の不安」を取り除く方法
◎あの男の名前
◎自分でコントロールできること、できないこと
◎夢の多くは、「自分でコントロールできない」もの
◎夢が商売ネタになる理由
◎時間は、「自分がコントロールできるもの」?
◎「自分でコントロールできるもの」は何か?
◎感情が起きる要因は「期待」
◎期待と現実のギャップが、あらゆる感情を生む
◎「自分の心」をコントロールするコツ
第5章 「今」を使いこなす
◎「人生への期待」を捨てるという違和感
◎自分がコントロールできる、たった2つの力
◎「夢」には2つの顔がある
◎それは、手段としての「成長」か、目的としての「成長」か
第6章 目標は必要、夢はいらない
◎「夢」と「目標」の違い
◎目標にはなく、夢に求められるもの
第7章 「夢」に固執した人の末路
◎友人からの衝撃の報告
◎夢は、時として「妬み」を生む
◎夢が妬みを生み、その妬みがさらに苦しみを生む
◎「コントロールできないものを無視する」トレーニング
第8章 正しい道は、他人が評価する道ではない
◎仕事で発生したモヤモヤ
◎多くの他人の評価とその後の結果に因果関係はあるか?
◎「自分が間違っている」と思うほうが楽?
◎多数の言う正しさに追随して、自分の判断を失っていないか?
◎初デートで映画館を選んだ理由に潜む自分の本心
◎君を評価できるのは誰?
第9章 夢なしで目標をつくる方法
◎目標がないと頑張れない!?
◎「欲望のままに」ではなく、「心のままに」
◎人生の最終目的地はどこ?
◎死を目的地にする3つの効能
◎自分の人生にとって、大切にすべきものが見えてくる
◎不思議なサウナ男の正体
第10章 自分の反応が、その意味を決める
◎幽霊との向き合い方
◎2000年経っても、人の心や悩みは変わらない
◎「科学」は人の欲望を生み、「哲学」を飲み込んだ
◎現代に失われた「人」を知る技術
◎砂時計の秘密
◎あらゆることは、反応して初めて意味を持つ
◎「物事の反応・見方を変える」トレーニング
◎不正を生み出す根本原因
◎賞賛と不正はセット
第11章 人生における危険の値打ち
◎なぜ幸せな人生には危険や失敗があったほうがいいのか?
◎成功以上に失敗を乗り越えたことを喜ぶ
◎「老害」になってしまう人の特徴
第12章 限られた時間の使い方
◎「人生の変化」の兆し
◎時間を大切にしているかどうかがわかる質問
◎人の求めに時間を簡単に使ってしまう2つの原因①
◎人の求めに時間を簡単に使ってしまう2つの原因②
◎「忙しさ」が時間のムダ使いである理由
◎最高の時間の使い方
◎男の過去
第13章 「怒り」は、危険な欲望である
◎男が死にきれない理由
◎怒りが起こる2つの理由
◎相手の行為を正すには?
◎「怒り」が持つ、4つの危険性
◎怒りに対抗する3つの砦
◎怒りで人生を消耗するなんて、もったいない
◎教え子ネロと男の過去
第14章 僕たちは「自由」をすでに手に入れている
◎「砂時計」の意味は、誰が決めた?
◎これまでの男の教え、総ざらい
◎人間とは見たいものしか見ない
◎幸せに至る唯一の道に必要な「心の自由」とは?
◎自分の心も、幸せの見方も、自由に操れる
◎2000年を超えてわかった、男の新たな気づき
第15章 「別れの悲しみ」との向き合い方
◎最終講義のテーマ
◎別れとは、感謝をすべき時間
◎完璧にできなくていい、できなかったら、コレをやればいい
◎最後の教えの実践
◎サウナ店員からの告白
おわりに