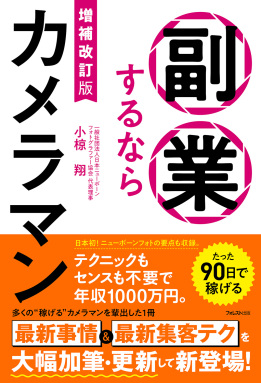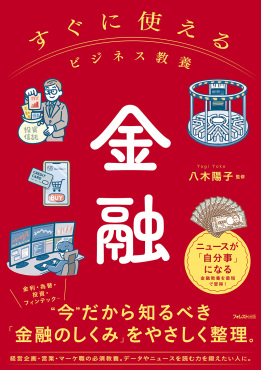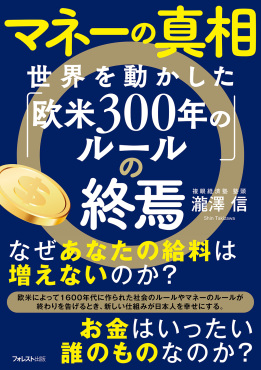著者の関連商品
著者の関連商品
-
副業の1つとしての「カメラマン」という選択肢。2019年に刊行され、多くの“稼げる”カメラマンを輩出した衝撃作が、大幅アップデートして新登場しました。旧版が刊行された2019年当時に比べて、特に「集客」「リピーターづくり」「売上アップ」の手法が変わってきています。いわゆる「稼ぐコツ」がアップデートされているわけです。今回の増補改訂版では、その最新事情&最新集客のノウハウを大幅加筆・更新されています。また、撮影技術についても、さらにブラッシュアップされ、今、カメラ業界で最注目の「ニューボーンフォト」についても1章分で解説してくださいました。もはや、増補改訂版というより、90%以上、新規書き下ろしの1冊となりました。初めてこの本を知った方はもちろん、旧版を読んだ方にもご満足いただける内容に仕上がりました。

POSTED BY森上
View More【多くの“稼げる”カメラマンを輩出した衝撃作が
副業を考えている人、必読!
大幅アップデートして新登場!】
未経験OK、初期費用最少、
ママでも可能、
コスパ最強の副業があります。
1日2時間の仕事で
テクニックもセンスも不要で、
年収1000万円。
副業として最高の選択肢
「稼げる副業カメラマン」になるための
全ノウハウを完全公開した1冊が、
最新事情&最新集客テクを
大幅加筆・修正して新登場です。
「カメラマン」というと、
撮影テクニックやセンスなどが
必要だと思いがちですが、
実はテクニックもセンスも不要です。
なぜなら、
昔に比べて、
カメラの性能が劇的に向上しているからです。
そして、
カメラで稼ぐには、
年齢・性別・有名無名も関係がないのも
大きな魅力です。
重要なのは、
撮影技術以上に、稼ぐコツ。
「稼げる副業カメラマン」になるために、
カメラ歴0日からの「撮影技術」はもちろん、
「集客」「リピーターづくり」「売上アップ」といった
必要不可欠なポイントを徹底解説します。
旧版に比べて、
今回の増補改訂版では、
稼ぐために求められるノウハウを
大幅アップデートしています。
加えて、
カメラマン業界最注目の
「ニューボーンフォト」についても解説しています。
「増補改訂版」という域を超え、
大幅加筆・更新した1冊に仕上がりました。
カメラに興味がある人以上に、
副業に興味がある人におすすめの1冊です。
気になる本書の内容
本書の内容は以下のとおりです。
はじめに――──副業するなら、カメラマンがいい
第1章 カメラマンで人生を変える──自由と収入を両立させる、具体的な第一歩
◎副業するなら「カメラマン」をおすすめする4つの理由
◎【理由1】市場は広がっているのに、人材がまだまだ足りていない
◎【理由2】「スキルが直接〝お金〟に換わる」という即金性の高さ
◎【理由3】時間・場所・人間関係に縛られない働き方ができる
◎【理由4】初期投資が少なく、在庫リスクがない
◎カメラマンとして持っておきたい自覚と心得
◎カメラ未経験でもOK!月収10万円を目指せる3ステップ──初心者が最短ルートで売上を出す道筋
◎忘れてはいけない考え
◎どんな撮影ジャンルで稼げる?──カメラ副業の仕事マップ
◎ジャンルに関係なく、求められること
◎平日昼・夜や週末だけでもOK!「撮影スタイル」の選び方──本業と両立した働き方
◎「案件シェア」という働き方も可能
◎稼ぐ人はココが違う!副業カメラマンの収入事例5選
◎月5万円の売上を目指すために最低限必要な機材と予算一覧──初心者向けスタートセット
◎高額の機材と売上は比例しない
◎高い技術より大切な「お客様満足」を生む撮影の心得
◎売上が上がるカメラマン、上がらないカメラマンの違い
◎「喜ばれるカメラマン」になる方法
◎さらに喜ばれるためのひと工夫
◎副業カメラマンが「やってはいけない」3つの落とし穴
◎カメラマンにしかできない「AI時代の仕事の価値」とは?──人の感情を残す力
◎カメラで人生を変えたいあなたへ──次にやるべき1つの行動
第2章 カメラ初心者から売上をつくる!副業カメラマンの「最初の一歩」
◎副業カメラマンとしての心構えとは?
◎カメラ設定の基本をマスターする──シャッタースピード、絞り、ISO感度の基本
◎「撮影モード」の基本と「マニュアルモード」の活用
◎慣れるまでのおすすめ設定
◎最初の撮影を経験する──理論を実践に変える最初の一歩
◎撮影した写真を編集して仕上げる──編集のやり方
◎集客はSNSから!簡単にできる集客方法と投稿のコツ
◎初仕事の受注方法!最初のお客様を獲得するための営業手法
◎初めてのお客様に安心感を与えるための撮影の流れと心構え
◎スムーズなデータ納品方法──納品時に気をつけるべきポイント
◎お店として素人感から脱却する方法──プロフェッショナルな体制づくり
◎プロとしての在り方を追究する
第3章 副業カメラマンの成長戦略──信頼を築き、売上倍増
◎専門性を活かしたブランディング戦略──市場での差別化を狙ったブランディングの基礎とステップ
◎リピーターを獲得するための仕組みづくり──お客様に「またお願いしたい」と思わせる戦略
◎AIDMAの法則を活用した集客戦略──効果的な集客を実現する方法
◎プロフィールと世界観づくりのチェックポイント──初心者でも「ブランド感」を出せる整え方
◎テストマーケティングとABテストを活用した集客戦略
◎ファンが増える投稿の型と続け方──反応率が高まるキャプション・写真・頻度とは?
◎「自分らしさ」が伝わるポートフォリオのつくり方──少ない実績でも仕事につながる見せ方戦略
◎仕事につながるLINE・DM対応のコツ──初対面から信頼を得るコミュニケーション術
◎ライバルと差がつく「自分だけの強み」の見つけ方──ポジションとコンセプト
◎ビジネスの安定化を図るための財務管理と税務の基本
第4章 「選ばれる写真」のための撮影力・表現力の磨き方
◎「なんとなく撮る」から卒業するために必要なこと──写真の価値を決めるのは「技術」より「意図」
◎自然な笑顔を引き出すコミュニケーション術──撮影前3分の雑談で変わる
◎「いい写真」をつくる3つの基本──構図・光・背景というカメラの土台力
◎どんな場所でも「撮れる場所」に変える方法──実家・公園・カフェで絵になる工夫
◎作品撮りで技術も集客も一気にアップ──クックパッドの法則
◎「この人らしい」と言われる写真の共通点──表情・しぐさ・空気感を残す撮り方
◎「なんか垢抜けてる」と感じさせる写真の秘密──初心者でもすぐ実践できる「仕上がり」の工夫
◎編集で「安っぽさ」をなくす!色と明るさの整え方──Lightroom・スマホアプリで魅せる写真に変える
◎納品後に「センスいい!」と言われる仕上げ方──スライドショー・モノクロ仕上げ・余白の魔法
◎技術を磨き続けたくなる人になる方法──成長が楽しくなる「学び方の設計図」
第5章 ママが一番輝ける仕事「ニューボーンフォトグラファー」という選択
◎ニューボーンフォト市場の可能性──個人フォトグラファーの最注目ジャンル
◎ママこそニューボーンフォトに向いている理由──子育ての経験が最大の武器になる
◎ママに最もおすすめの職業──ママに最適な柔軟な働き方
◎具体的な時給と、平均月28万円売り上げられる理由
◎先輩ママとしての強み
◎看護師・助産師・保育士にもおすすめ!その資格と経験が活かせる
◎どこで学ぶ?ニューボーンフォト学校徹底比較
◎赤ちゃんのかわいさを引き出す2つのスタイル──「ポーズドニューボーン」「ナチュラルニューボーン」
◎「開業届」という就業証明としての強み──フリーランスとして働くための第一歩
◎夫の理解を得るには?家庭内説得のポイント
◎妊娠中・妊活中でもできる!柔軟な働き方が叶う理由
◎ママが笑顔になると、家族みんなが豊かになる
第6章 マーケティングの力で売上を倍増させる
◎リサーチで差をつける!ターゲット市場の徹底分析
◎「売れるカメラマン」の条件とは?──ペルソナ設計で魅力的なサービスをつくる
◎自分だけの「USP(独自の強み)」を打ち出す方法
◎リピート・紹介で収益を伸ばす!LTVを最大化する戦略──長期的に収益を上げる方法
◎オプション販売・クロスセルで収益倍増!売上を最大化する戦略
◎少ない投資で集客力を最大化する方法──ROI(投資対効果)を意識した広告戦略
◎イノベーター理論を活用したカメラマン戦略──口コミと紹介で集客を加速させる方法
◎価格設計と価値提供のバランスを取る!売れる価格帯の見極め方
◎売上の上げ方は3つしかない
◎ビジョンとミッションに基づく「今後の拡大戦略」
第7章 副業カメラマンがステージアップするための戦略
◎お客様が心から欲しくなる商品をつくる方法
◎パートナーシップとコラボレーション──大規模案件を手に入れるための戦略
◎クレーム対応と難しいお客様への応対
◎カメラマンとお客様をつなぐマッチングサイト攻略法
◎少ない予算で高い効果を得るための、メタ広告の設定方法&ターゲティング戦略
◎撮影のクオリティを劇的に向上させる機材とアクセサリー選び
◎お客様をファン化させるポイント
◎価格戦略の見直しと高単価へのシフト──価格設定術
◎短期・中期・長期目標を明確にする──効率よくビジネスを加速させる方法
◎モチベーションが上がる「事業計画書」の書き方
第8章 プレーヤー思考からオーナー思考へ
◎オーナー思考へのシフト
◎自分に制限をかけないマインドセットの構築──制限を乗り越える思考法
◎目指すべき崇高なビジョンを掲げる──持続可能な成功を手に入れる方法
◎夢を現実に変える「決断力」の鍛え方
◎自分の成功と他者への影響力を意識する
おわりに──副業カメラマンとして、人生を変えたいあなたへ -
忙しい人ほど、「時間をどう使うか」よりも「最初に何をするか」を意識したほうが1日の質が大きく変わります。本書は、努力や根性に頼らず、行動の“始まり”を整えることで、人生がうまく回り始める仕組みをまとめました。皆さんそれぞれの生活に無理なくはめ込める、実用性の高い一冊に仕上がりました。

POSTED BY美馬
View More「時間をどう使うか」よりも「最初に何をするか」が重要!
仕事に追われ、気づけば1日が終わり、やりたいことはまた明日へ。そんな毎日を送っている人は少なくないはずです。本書が扱うのは、「もっと効率よく動こう」とか「気合で朝活しよう」といった話ではありません。むしろ逆で、頑張らなくても自然に回る1日のつくり方を具体的にお示ししています。
キーワードは「最初の10分」。
何かを大きく変えようとするのではなく、行動の入り口だけを整えることができればOK。朝起きてからの10分、仕事に取りかかる前の10分、帰宅後の10分、寝る前の10分を意識すると、その後の行動が驚くほどスムーズに回り始めます。
さらに本書では、1日を24時間として考えるのではなく、7つの時間ブロックに分けて捉える考え方が紹介されます。
ブロック1 就寝前1時間30分の「DOWN TIME」
ブロック2 就寝7時間30分の「SLEEP TIME」
ブロック3 起床後1時間の「WAKE TIME」
ブロック4 仕事前1時間30分の「FOCUS TIME」
ブロック5 仕事9時間の「WORK TIME」
ブロック6 帰宅1時間の「GRADATION TIME」
ブロック7 帰宅後2時間30分の「FREE TIME」
それぞれのブロックごとに役割を決めておくことで、「なんとなく流される時間」が減っていきます。
「10分」という短い時間だからこそ、今日から試せることばかりです。時間を管理するというより、時間の主導権を少しずつ自分に戻していくようなイメージ。本書は、そんな感覚を取り戻したい人に向けた一冊です。読み終えた後、明日の朝の10分は、きっと今までと少し違って見えるはずです。
主要目次
第1章 人生がうまくいかないのは「生きるリズム」を失っているから
第2章 「DOWN TIME」「SLEEP TIME」「WAKE TIME」
10分でスマホを手放して明日のリズムを手に入れる
第3章 「FOCUS TIME」「WORK TIME」
仕事の質は「最初の10分」で決まる
第4章 「GRADATION TIME」「FREE TIME」
自分で意思決定できる時間を確保する
第5章 「最初の10分」を自動化する仕組み作り -
15年前から読み継がれてきた苫米地博士のロングセラー金字塔『コンフォートゾーンの作り方』の新版です。時代を問わないエバーグリーンな内容ゆえ、今後も多くの人の人生を変える、唯一のバイブルとしての輝きをこれまで以上に増すことでしょう。

POSTED BY寺崎
View More15年間支持されて累計10万部突破!
2010年に刊行以来、
圧倒的な「変化」の報告が途絶えない伝説の書がリニューアル。
☑年収が1億円を超えた
☑人間関係がうまくいくようになった
☑長年のトラウマが消えた
☑転職に成功した
☑志望校に受かった
☑本当にやりたいことが見つかった
☑自分に自信が持てるようになった
☑夢が実現した
このような読者の反響が
この15年間、絶えず編集部に届いてきました。
「もっと早く知りたかった」
「自分の殻を破りたいと思ったら、この本しかない」
15年の時を経て、読者の熱い支持のもと
このたび装い新たに新版が誕生しました。
あなたと、世界的な大富豪に
世界的な大富豪とあなたとの唯一の違いはたった一つ。
能力の違いはありません
「どこに居心地の良さを感じるか(=コンフォートゾーン)」
この設定だけです。
脳にとっては
年収500万円も年収1億円も
単なる「設定値」にすぎません。
残念ながら、努力や才能は関係ありません。
本書で脳の“設定”さえ書き換えれば
あなたの脳は勝手に強制的に
「成功」への最短ルートを選び取ります。
全世界の英知を尽くしたメソッド
本書で紹介するプログラム「TPIE®」は
脳科学と心理学のこれまでの成果の粋を尽くしたもの。
ビジネスの世界のみならず
トップアスリートの世界、政財界などで、圧倒的な結果を出しています。
◎NASA、米国国防総省など米政府機関が公式採用
◎フォーチュン1000の50%超が導入
◎全米の州政府、警察、刑務所、小中学校、大学で教育プログラムとして採用
一介の高校教師から億万長者となり
コーチングの始祖と呼ばれるルー・タイスをはじめ
脳科学、心理学、認知科学の世界的権威たちが開発したプログラムに
苫米地博士が最先端の研究成果を加えたものが
本書の理論と実践のベースとなっています。
コンフォートゾーンの外側に一歩踏み出す
この本のタイトルにもなっている「コンフォートゾーン」とは何か?
もし、あなたが年収500万円なら、
あなたのコンフォートゾーンは年収500万円のところにあります。
ところが、コンフォートゾーンを
年収1億円のところに持っていけばどうなるか。
あなたも年収1億円が可能となります。
つまり、あなたが現状から抜け出すためには
今のコンフォートゾーンを変える必要があるのです。
コンフォートゾーンが年収500万円のうちは、
目の前に年収1億円のチャンスがきても
残念ながら気づくことができません。
これは「脳のメカニズム」の問題です。
人が成長し、目標を達成しようと思うなら、変化が必要です。
そのためには、慣れ親しんだコンフォートゾーンの外側に、
自分にとってなじみのない世界に足を踏み出し、
新しいコンフォートゾーンを広げていかなくてはならないのです。
そのために本書があります。
本書で紹介するTPIE®プログラムなら
あなたが望むコンフォートゾーンを
思い描いた形で手に入れることができるようになります。
本書の構成
Prologue 脳科学と心理学の世界的権威たちの頭脳が
監修した能力開発プログラムTPIE®とは?
UNIT1 TPIE® の世界へ
UNIT2 スコトーマとRAS リアリティーを見えなくするもの
UNIT3 情動記憶があなたをつくる
UNIT4 人は過去に生きている
UNIT5 自分を過小評価していないか
UNIT6 セルフ・トークで自己イメージを高める
UNIT7 コンフォートゾーンは自己イメージが決める
UNIT8 他人の言動を選別する
UNIT9 ハイ・パフォーマンスの実現
UNIT10 エネルギーと創造性の源
UNIT11 現状を超えたゴール設定
UNIT12 公式 I×V=R イメージの再構築
UNIT13 映像で思考し、思考が実現する
UNIT14 最初にゴールがある
UNIT15 したいことをやりなさい
UNIT16 イエス・アイム・グッド
UNIT17 未来の記憶をつくる
UNIT18 新しい「自分らしさ」をつくる
UNIT19 さらに先のゴール
UNIT20 バランス
UNIT21 さらなる夢に向かって
購入者限定無料特典
特典1
伝説の音声教材「苫米地式目標達成プログラム」(音声)
現在、完売しており、再販売の予定もない入手困難な音声教材の導入レッスンを収録
特典2
特別音声ファイル「結果が出る人と出ない人の違い」(音声)
□いつの時代にも求められる「結果を出す人」とは?
□結果を出す人の脳の使い方とは?
□結果を出すためにはどうすればいいのか?
□結果が出ない人の共通点とは?______天才認知科学者・苫米地英人が完全解説!
※無料特典は、お客様ご自身で別途お申し込みが必要です。
※無料特典は、サイト上で公開するものであり、小冊子・CD・DVDなどをお送りするものではございません。
※上記無料特典のご提供は予告なく終了となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※新版は、初版『コンフォートゾーンの作り方』(2010年刊行)と同じ内容となります。
※特典1は初版に付属していたCDROMに収録されていた音源です。
特典2は初版の書籍購入者限定でプレゼントした音声ファイルです。 -
金融という言葉には、「難しそう」「自分には関係ない」という印象がつきまといがちです。しかし、物価や金利、円安といったニュースは、すべて私たちの暮らしと直結しています。本書は、そうした金融の話題を、生活や社会のしくみと結びつけながら、基礎から丁寧に整理した一冊です。専門知識を前提とせず、図解を多用しながら読み進められる構成にこだわりました。金融を「お金儲けのための知識」ではなく、「不安な時代を落ち着いて判断するための教養」として捉え直すきっかけになればと思います。

POSTED BYかばを
View More不確実な時代を生きるための「金融」という基礎教養
物価上昇、円安、金利の変動、少子高齢化、地政学リスク、AIの進展──。
私たちの暮らしや仕事は、金融と切り離せない問題に囲まれています。
にもかかわらず、「金融」は難しそう、専門家向けの話だと感じている人も少なくありません。
本書は、そうした不安や距離感を取り払い、金融を社会を理解し、自分の生活を守るための教養として捉え直す一冊です。
金融のしくみを、ニュースと暮らしにつなげて理解する
本書では、金融の基本をゼロから整理しながら、銀行や中央銀行、証券会社、国際機関など、金融を動かす担い手の役割を丁寧に解説します。
金利と為替の関係、日銀の金融政策、住宅ローンや為替介入といったテーマも、図解を交えて平易に説明。
日々のニュースが「わかった気がする」から「理解できる」へと変わっていきます。
投資・テクノロジー・社会課題まで見渡す金融の全体像
株式、債券、投資信託、不動産、NISA・iDeCoなどの投資の基本から、デリバティブやブロックチェーン、AIやフィンテックといった最新動向まで、本書は現代の金融を幅広くカバーします。
投資ブームの中で振り回されないための視点や、金融と環境・教育・社会課題との関わりにも目を向け、金融を「お金の話」に終わらせません。
金融を理解することが、将来への不安を減らし、よりよい社会を考える力につながる──その実感を得られる構成となっています。
目次
CHAPTER1 金融のキホン
CHAPTER2 さまざまな金融の担い手たち
CHAPTER3 金利と為替について知る
CHAPTER4 投資の基礎としくみを学ぶ
CHAPTER5 進化する金融商品と技術
CHAPTER6 これからの金融はどうなる? -
いまの日本で幸せを感じている人はどれくらいいるでしょうか。幸せの尺度はお金でははかれないとは言いますが、国の力が弱まるいっぽうのなか株価は最高値を更新する状況で、いったい誰がその恩恵にあずかっているでしょうか。
私たちがいる世界は、あるお金のルールのもとに存在しています。それは「欧米の作り上げたマネールール」です。これは言い換えれば、ひと握り者だけが富を得る世界です。彼らのマネールールは格差社会を生み出し、真面目に働くことはわずかな収入しか得られないという仕組みを築き上げました。
それはさかのぼること約300年前。ルネサンス期から産業革命、帝国主義へと向かう時代です。私たちはこのときに出来上がったルールを当たり前のように思って生活していますが、実はこのルールが終わりを告げ、新しいマネールールの時代がやってくるかもしれないのです。
私たちはそんな過渡期にいます。欧米の都合のいいように作られたルールが崩壊したとき、私たちは本当に幸せがやってくるのでしょうか。
この本は現在のマネールールがいかにして作られたか、なぜ終焉を迎えようとしているのか、そして新しい世界にどう乗り出すのかを提示する1冊です。
POSTED BY稲川
View More「なぜあなたの給料は増えないのか?」を探り、お金の真相を暴く
あなたがいま、当たり前に生活している世界は、実はたかだか約300年前につくられたものです。
金融のルール、資本主義や民主主義といった枠組みは、17世紀から18世紀のヨーロッパで誕生しました。
それはニュートンによって金本位制の土台が生まれ、デカルトによって人間至上主義に取って変わり、ゴールド・スミスによって銀行という仕組みに発展したなかで生まれていきました。それが今日まで続いているのがいまの世界です。
しかし、彼らの築き上げたルールによって、私たちは幸せになれたのかというと疑問を感じるのではないでしょうか。
彼らのルールは人類の発展に寄与したことは間違いありませんが、いっぽうで数パーセントの富を得る者だけが生まれる格差社会をつくりました。
つまり欧米のルール、彼らによって都合のいいルールで私たちは生きているかぎり、私たちの給料は増えないどころか、幸福感すら得ることがないのです。
しかし、文明論からも言えることがあります。それは現在のルールが終わりを告げ、新しい枠組みが生まれる過渡期にきているということです。
お金とはいったい何なのか、お金とはいったい誰のものなのか。
この本では、欧米がつくったルールの正体を「事件・人物・歴史」を軸に暴いていきます。そして、「世界は誰の都合で動いているのか?」知ったとき、あなたの人生戦略が変わります。
「敵を知って己を知る」ことが幸せになるための第一歩
この本では、欧米によってつくられた社会のルールやマネーのルールを知ることによって、現代社会のひずみを読み解こうという試みです。そして、こうしたルールが終焉を迎えるときにあなたがどう行動し、どうすれば幸せになるかを考えるヒントにしていただくことが目的です。
序章では、あなたの仕事とお金が現在の社会の仕組みにいかに直結しているかを理解していただき、あなたの給料が何に使われているかという驚愕の事実をお伝えしていきます。
第1章では、いまの社会の仕組みのもととなる考え方をつくったニュートンとデカルトという人物の足跡をたどりつつ、彼らの考え方に異を唱えるときがきているのではないかということを提示していきます。
第2章では、マネーの仕組みを錬金術に変えた「マネールール」を解き明かし、現在進行しつつあるマネーの変容についても考えていきます。
第3章では、富を得る者と搾取される者が生まれ、マネー資本主義からいまの民主主義がどのようにしてでき上がり、私たちに何を残したのか見直していきます。
第4章では、欧米が自分たちにとっていかに都合よく歴史を塗り変えていったかを、その歴史をひも解きながら、欧米のルールが限界を迎えているという事実に迫っていきます。
第5章では、文明そのものが引っ繰り返るのではないかという壮大な仮説を展開し、現在の不平等社会についての考え方も大きく変容している様を解説していきます。
第6章では、富を得る者がいまもって自分たちに有利に動かそうとしているのか、私たちがだまされている株式を操る数字のカラクリを暴いていきます。
第7章では、お金とはいったい何なのかといったお金の本質をとらえながら、人間の本来のあるべき社会とは何なのかを一緒に考えていただければと思います。
そして、次の新しいルールをけん引するのはどの国(地域)なのか考える際、私たちの日本が浮上します。それはなぜなのか。
私たちはマネーのあとの世界を知るときがきたのです。
目次
序章 見えない支配者——お金は誰のために流れているのか?
欧米人と日本人が考える「お金とは何だろう?」という視点
「ビジネスとお金」を切り離して考えてしまいがちな日本人
ビジネスパーソンでも自分の会社の「中期経営計画」を知らなければならない理由
あなたの給料はめぐりめぐって「あるもの」に使われている
これまでの思考がガラリと変わる西欧社会が作り上げたマネールールの真相
第1章 禁断のルール——欧米が仕掛けた「マネーの方程式」
科学のルールを作ったニュートンと人間至上主義を唱えたデカルト
日本人が抱く違和感を代弁していた「スピノザと多神教」
「ルネサンス、宗教改革、大航海時代、絶対王政」の時代を迎え衰退したキリスト教
西欧社会のルールに切り離すことのできない「キリスト教社会」
時代は約300年のサイクルを経て大変化を起こす
今いる当たり前の世界がついに〝賞味期限〞を迎える
第2章 錬金術師の誕生——ゴールド・スミスが作った“紙幣”という幻想
「異教徒からは利子を取っていい」という理屈から生まれた金利
金庫に眠っていたゴールドから錬金術に変えたゴールド・スミス
マネーがマネーを生み出す「信用創造」というルール
暗号通貨「ステーブルコイン」で覇権を握ろうとするアメリカ
第3章 市民の奴隷化——株式会社と資本主義という遺産。
国王の特権で生まれた「東インド会社」は本当に世界初の株式会社なのか?
民主主義とはほど遠い、市民の“奴隷化”と資本主義の誕生
“市民”という新しい社会階級で「民主主義」が生まれた
民主主義のルールに従う株式会社の「51%ルール」
投資は資産を投げ打つのではない「インベスト」の本当の意味
第4章 マネーの帝国——巨万の富を得た者と戦争経済の系譜
ナポレオンの以前以後、平和をもたらすことのできなかった形だけの「ウィーン体制」
「金本位制」が破たんを迎える二度の世界大戦
世界45カ国の自由貿易の未来図という幻想。30年で終わりを迎える「ブレトンウッズ体制」
アメリカファーストは変わっていない。日本叩きの「プラザ合意」
米ドルの覇権を守り続けた「ペトロダラー」の正体
ドル基軸通貨にダメを押した「リーマン・ショックとコロナ」
第5章 見えざる方程式——あなたの給料が誰かの兵器になるまで
東洋と西洋で覇権が入れ替わる「文明の800年サイクル」
文明サイクル300年で作られた欧米の社会ルールの転換期
アダム・スミスの「神の見えざる手」が幸せな社会を作るというウソ
格差社会が生んだ「平等」と「公平」というジレンマ
公平か平等か。結局は今の社会は「不平等で不公平」な社会
地球に住む“人間という巨人”をはるかに上回る社会システムを持つ昆虫たち
第6章 マネールールの崩壊——企業価値を決めるまやかしの数字と脱・株主第一主義
矛盾する会計基準で、正しい利益が見えてこないために生まれた「キャッシュフロー」
こじつけの数字「ディスカウント・キャッシュフロー(DCF)」の正体
株主第一主義という悪のためだけに作られた「ROE」のカラクリ
第7章 日本の夜明け——ルールの外で生きる力
富を持つ者だけがすべてを得る「人の幸福度」まで奪っていく欧米ルール
「お金は腐る」と提唱した経済学者シルビオ・ゲゼル
ドル基軸通貨にダメを押した「リーマン・ショックとコロナ」
終章 マネーのあとの世界へ——「働く」と「稼ぐ」を取り戻す
「国」というのは、そもそも何なのか?
たとえ社会秩序が大きく変わっても「日本の会社」は生き残る
「会社」という組織から見えてくる新しい未来。そして、幸福になるための人生の選択肢