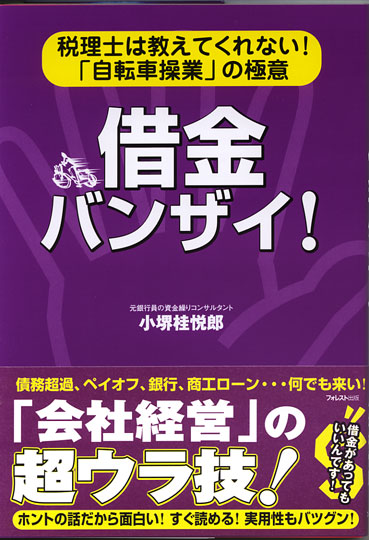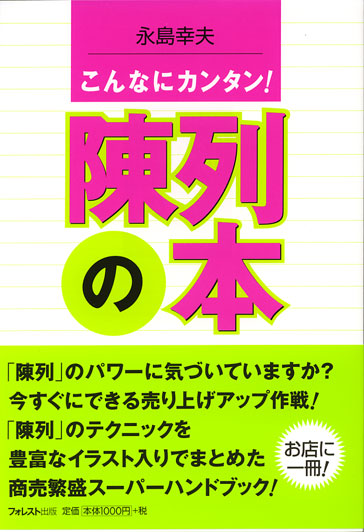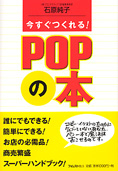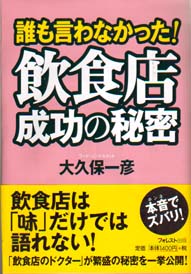著者の関連商品
著者の関連商品
-
バブル崩壊前約十年銀行にいました。その後は税理士事務所で、ずっと資金繰りの相談にのってきました。View More
平たく言うと、借金の相談です。
じつはほとんどの中小企業が自転車操業ではないのか?
でもそれはけして悪いことではありません。
ただ、そのコツを知って、上手に資金繰りのペダルを漕いでいきましょう!
借金だって同じことが言えます。
借金には借金の法則があります。
さあ、あなたにこの自転車操業クラブの面々を紹介しましょう。
[目次]
はじめに 上手に借金と付き合っていく極意
▼プロローグ
ようこそ自転車操業クラブへ
第1章 ほとんどの会社は「自転車操業」
▼社長は今夜も眠れない 26
▼実は、ほとんどの会社が「自転車操業」 30
▼売り上げという名のペダル 34
▼「自転車操業の定義」を知っていますか? 36
▼計画的に自転車操業? 37
▼だいたい借金ってなんだ? 39
▼借入金だけが借金じゃない! 41
第2章 貸す側を理解すれば、借りられる!
▼銀行だって金融屋 46
▼銀行? マチ金? どっちが大事? 48
▼決めるのはウチら銀行 51
▼最初に「制度ありき」じゃない 53
▼貸したいから貸す 55
▼とれる(回収できる)うちにとる(回収) 59
▼回収に入る瞬間 61
▼回収は、とれるものから 63
▼回収の極意は貸すときにあり 66
第3章 実践!「借りる」
「返さない」の交渉術
▼交渉の始まり始まり 70
▼借りられるかどうかの見極め 72
▼「融資が出るか」の見極めのポイント・
融資残高が月商の三カ月 73
▼「融資が出るか」の見極めのポイント・
決算書の赤字は「本当の赤字」か? 74
▼「本当の赤字」ってなに?
▼そのための保証協会 78
▼めぐる季節の中で 80
▼眠れないお盆休み 84
▼まだまだ借りられる 86
▼資金繰り表読めない銀行員は多い? 89
▼銀行との交渉をラクにする秘訣 90
▼借りられないなら、返すのやめよう! 91
▼お嫁さんでもリスケはできる! 94
▼リスケをする目安・
償却前利益が返済額に比べて少なすぎる 95
▼リスケをする目安・
赤字が二期続いたら 96
▼リスケをする目安・
折り返し融資が遅れるようなら、減るようなら 97
▼リスケをする目安・
一年間で返すべき金額と償却前利益が一桁違ったら 97
▼リスケ交渉のスタート 98
▼入金口座はこっそり移して延滞、延滞・・・ 99
▼目指せ! U字回復 100
▼借りなくてもできること 103
▼単純じゃない! リスケ後のペダルのこぎ方 104
▼赤字を止めるときの注意点・
赤字の店を急に閉めない 106
▼赤字を止めるときの注意点・
急に宣伝費を削らない 108
▼赤字を止めるときの注意点・
成績の悪い営業マンをクビにしない! 110
▼赤字を止めるときの注意点・
掛け売りお断り 111
▼小売できるものをさがせ 113
第4章 実践!イザというときの
「自転車操業」のウラ技
▼ジャンプ! ジャンプ! ジャンプ! 118
▼スキップ! スキップ! スキップ! 122
▼融通きかせていきましょう! 124
▼これがご法度!「融通手形」 126
▼商工ローンで借りたっていいじゃん! 130
▼こんなときこそ商工ローン 133
▼このぐらいなら商工ローンで借りても平気 134
▼商工ローン返済に裏技 136
▼借り換えのローテーション 140
▼手形と小切手は取り扱い要注意 144
第5章「借りるため」の経理と決算のやり方
▼商工ローンの経理処理・手形金融の場合 150
▼商工ローンの経理処理・社長個人が
商工ローンから借りてきた場合 153
▼「借りるための」粉飾決算? 154
▼「借りるための」バランスシートの作り方 157
▼それは節税? 脱税? 161
▼税務署の取立てはキツイ! 164
▼税理士との付き合い方 166
第6章 知っておくと使える!「借金の法則」
▼負の遺産 170
▼取引銀行の倒産 173
▼このままでもいい 175
▼どうして倒産しなかったのか? 178
▼借金の「原因と対処の法則」 181
▼借金ある人は魅力的? 184
▼借金のS字カーブ 186
▼夢のあとさき 191
おわりに 196
●編集担当者より一言●
「会社経営の超ウラ技」、
「税理士は教えてくれない自転車操業の極意」を教えます!
本書は、今まで誰も教えてくれなかった借金のことを、
ホントの話をベースにして面白くお話した本です。
はっきり言って、こんな本は初めてです!
借金って悪いイメージがあるせいか、
誰も本質を言ってくれなかったからでしょうか。
借金の本質から、借り方、返し方、
経理のやり方、決算のやり方・・・などを、
「借金があってもいいんだ!」ということ感じで、
面白おかしく解説。
しかも、ウラ技!
債務超過、ペイオフ、銀行、商工ローン・・・など、
いろいろありますが、本書のノウハウがあれば
「会社は絶対潰れません!」
とくにこんな人に読んでもらいたいです。
- 経営者
- 税理士さん
- 借金のある人
- 起業を考えてる人
- 経理担当者
でも、編集担当としては、面白さに自信があるので、
いろんな人に読んでもらいたいです! -
だれにでもカンタンにできる「陳列」のテクニックを、View More
豊富なイラスト・図表とわかりやすい解説で紹介したスーパーハンドブック。
売り上げアップのための陳列のコツがよくわかります。
あの大好評の『今すぐ作れる!POPの本』につづく、シリーズ第2弾!
目次
第1章 これが「陳列の力」です!
1.売り場づくりを忘れてはいませんか?
2.せっかくご来店のお客様を逃がしていませんか?
3.気持ちのいい売り場は気分を楽しくさせる
4.簡単な工夫でワクワクする陳列ができる
第2章 感じのいい陳列にしたらお客が増えた!
1.「補充陳列」で好感度No.1の売り場をつくる
2.「前出し」で商品の豊富感を!
3.「先入れ先出し陳列」で商品ロスをなくす
4.入荷商品が多すぎて困っていませんか?
5.「サンプル陳列」でお買い上げ客が増える
6.「縦列陳列」ですべての商品を見せる!
7.一見乱雑な「投げ込み陳列」。実は工夫が大切
8.陳列の乱れが生じにくい商品を取り扱う
第3章 こんな簡単テクニックで売り上げが伸びた!
1.「ゴールデンスペース」で売り上げアップ!
2.最も選びやすいのは90センチの陳列幅
3.「縦割り陳列」にすれば売り逃がしがなくなる
4.中置陳列台の陳列は見逃しに気をつけて!
5.関連陳列」で買い上げ点数と客数と利益が増える
6.ワクワクするバリエーションの豊富さ
7.試用しやすい陳列で売り上げが20倍に!
8.商品の違いがひと目でわかる「比較陳列」
第4章 これがお客様が喜ぶ陳列!
1.「フック陳列」にはこんなにメリットがある
2.品薄感のある時は棚間隔を調節!
3.ゴンドラエンドでお祭りイベント開催中!
4.「積み重ね陳列」で圧倒的な商品量をアピール
5.壁面全体を商品で埋め尽くす超量感陳列
6.「ひな段陳列」で一日の売り上げが15個増えた
7.立体感を出して、見やすく手に取りやすく
8.「ストック陳列」で在庫品も売り場へ!
第5章 商品を魅力的に見せる陳列テクニック
1.カラフルで楽しい売り場が簡単にできる
2.「スロット陳列」で単調な陳列に変化をつける
3.商品のセールスポイントを見せて売り上げ倍増!
4.集視ポイントをつくって注目を集める
5.リズミカルな「繰り返し陳列」で楽しさを演出!
6.ディスプレイが上手になるディスプレイ構成の基本
7.「コーディネート陳列」で客単価が上がる
8.「シンメトリー陳列」で見栄えのよい陳列がすぐできる
●編集担当者より一言●
『今すぐ作れる!POPの本』に続く、
商売繁盛スーパーハンドブック第2弾です。
「たかが商品の並べ方」なんて思わないでください。
著者・永島先生の語る「陳列のパワー」を感じたら、
あなたもすぐに始めたくなるハズ! -
繁盛店の必需品、「反応のいいPOP」をつくるための考え方、ちょっとしたコツをわかりやすく紹介。POPづくりの実践家である著者ならではの、誰にでもできる、今すぐできる、楽しいPOPのつくり方を伝授する、商売繁盛スーパーハンドブック登場!View More
●もくじ
第1章 なぜPOPが必要なの?
■POPって何のことだか知っていますか?
■POPはあなたの「声」の代わり!
■お客さんは「怖がっている」?
■じゃあ、POPで何を伝えればいいの?
■POPって、こんなこともできるんだ!
■で、POPを使うと、こうなります
第2章 POPの種類はこんなにいっぱい!
■気づかないで損をしていませんか?
■店内POPの種類
■お客さんを動機づけできる「最強ツール」①
メッセージPOP
■お客さんを動機づけできる「最強ツール」②
プライスカード
■お客さんを動機づけできる「最強ツール」③
タイトルボード
■売り場を演出!
サービス案内/売り場案内設備案内/設備案内
■コミュニティづくりの強い味方①
ミッションボード
■コミュニティづくりの強い味方②
スタッフボード/ネームプレート
■コミュニティづくりの強い味方③
コミュニケーションボード
■あれもこれもPOPです(店外POP)
■店外POPだってみんな自分でつくれる!
第3章 こうすればあなたの思いが伝わる!
■POPはキャッチコピーで決まる!
■あなたの商品をよく知ろう
■キャッチコピーのヒント
■『安心』を引き起こすキャッチコピーの例
■『信頼』を引き起こすキャッチコピーの例
■『共感』を引き起こすキャッチコピーの例
■キャッチコピーの注意事項
■イラストはどうすればいい?
■「POP文字」ってありますが
第4章 実践編
反応のいいPOPのつくり方
■POPづくりの基本は「自由」です
■私が使っている道具たち
■メッセージPOPのつくり方
■メッセージを考えるときの注意点
■メッセージPOPのビジュアルテクニックを一部公開!
テクニカル事例①・②
別紙に描いて貼り込む!/イラストを入れる!
テクニカル事例③・④
地塗りの上に文字を書く!/メリハリをつけるライン使い!
テクニカル事例⑤・⑥
生写真を使う!/フレーミング!
■プライスカードのつくり方
■プライスカードを数多くつくる裏技
■タイトルボードのつくり方(初心者用)
■取り付け方にもひと工夫
■さらに、あなただけに特別に……
●編集担当者より一言
コンサルタントではなく、実際に現場=売り場を舞台に活躍する著者によるPOPの本は、きわめて実用的です。「よし、さっそくPOPをつくってみよう!」と思っていただければうれしいです。 -
飲食店は「味」だけでは語れない!View More
「飲食店のお医者さん」大久保一彦が、繁盛の秘密をお見せします。
●もくじ
メニュー1:「まずいお店」なのになぜ流行る?
~飲食店「味」の話~
常識的な「おいしさ」にこだわるな!
外食は、家庭よりずっとおいしい味より、少しおいしい味を!
食通を相手にせず、大衆を相手にする!
「お客様の評価」に頼るな!
偶然の発見が成功を呼ぶ
味と価格の微妙な関係
自信を持って価格を上げろ!
お客様の満足度って何だ?
失敗したときこそ、お客様を感動させるチャンスだ!
「感激」したという経験を売るのがプロだ!
メニュー2:お金をかけなくても店は甦る
~飲食店「経営」のツボ~
経営者は「売れない」という言葉を使ってはいけない
小規模店は、ハンデを頭と労力でカバーする
極限まで挑めば、道は開ける!
忙しい店よりも、暇な店のほうが食器の破損が多い
情報を精するものは、戦いを制する!
中小企業は従業員の心に投資せよ!
マネジメントは悪役と救世主のペアで!
お金をかけずに売り上げを上げる方法!
中小規模店が客数を増やす方法
成功するためのチャンスは二度ない
「非常に満足した」お客様にはお礼のはがきを
ありがたい苦情のお客様!
商売っ気のない心のこもったはがきはお客様を癒す
メニュー3:従業員はこう使え!
~飲食店の「人材活用法」~
社員は社長の願望についてくるものだ!
会社を伸ばす「宣教師」のような存在
小さな輝きが大きな会社を作る
アルバイトも経営の貴重な戦力になる
人に喜ばれてこそ会社は発展する
アルバイトがやった失敗のコストも人件費のうち
マニュアル導入のわけ
これが「教え方」の基本だ!
新入社員の指導はその人間の一生を左右する
「達成感」が人間を成長させ、「保身」が人間をだめにする
メニュー4:売れるメニュー 売れないメニュー
~飲食店「商品」研究~
お客様の心理をくすぐる売れるメニュー
商品のネーミングとグラム単価の重要性
大手企業なら知っているメニュー作りの基礎知識
アフターサービスと店外でのコミュニケーション
アソートメントの重要性を知る
行列に勝るお客様作りはない
見込み客を来店させ、それを顧客にしていくステップ
飲食店の知らない価格のつけ方
メニューを魅力のないものにするのは「一律価格」である
定食屋のプラスオン作戦
お客様を呼ぶメニューの作り方
ネーミングがあなたを救う
メニュー5:儲からないのは「場所」のせい?
~飲食店「立地」論~
店によって違う好立地の意味
家賃は採算の大きなウエイトを占める
これから店を始めるなら、モノマネはやめろ
僻地に店を出した場合、店があることがサービスになる
チェーン店の出店競争に学ぶ
店選びの基礎知識――商圏について
視認性と導線評価が立地判断のふたつ目のポイント
生き残るには弱い店を狙え
メニュー6:人気の飲食店に変身できる!
~今すぐにできるノウハウ~
効果的な顧客作りを実践せよ!
はがき作戦こそ中小企業の顧客作りの原点!
従業員を使った顧客作りはユニーク
自分にしかないことを生かせ!
テイストの高い店を作りたければ、採用面接を変えよ!
零細企業のメニュー作り
大手は一騎打ちに弱い
●編集担当者より一言
凄腕フードコンサルタント・大久保一彦氏の第1弾単行本。
数々の飲食チェーン店を成功させた著者の手法が、わかりやすく書かれています。
飲食店経営者の皆様のみならず、グルメの方や、従業員教育でお悩みの一般店の方にもぜひ読んでいただきたい1冊です。 -
大繁盛の「キホン」を捜査せよ!View More
日本でただ一人の「元刑事」の経営コンサルタントが、「お店がまずやらなくてはならないこと」をわかりやすく解説!
売り上げの上がらない架空のお店を舞台に、あの手この手の捜査法でお客様を呼び戻します。
●もくじ
第一話 事件発生! お客はどこへ?
○怒りの店長
○はい、捜査ゼロ課ですが
○ボスの口癖
○現場主義
○捜査心得五ヶ条
○備忘録
○新米刑事登場!
○現場出動
○被害者の言い分
○瀬戸際……続投? 閉店?
○店長の決断
第二話 捜査開始!……厳しい現状
○捜査は出来ることから始まった
○急がず、焦らず
○一人で出来ること
○「ネタ取り」
○現場一〇〇回
○捜査の第一歩「実況見分」
○現状
第三話 現場に埋もれたネタ(情報)を探せ!
○使えるネタは眠らさない
○実況見分その一・視認性(お店の位置)
○実況見分その二・出入口(お店の顔)
○実況見分その三・クリンリネス(清潔なお店)
○実況見分その四・鮮度(お店の目新しさや工夫)
○実況見分その五・アピールポイント(おすすめとこだわり)
○実況見分その六・コミュニケーション機能(お客さんの顔と名前)
○実況見分その七・商品管理(チャンスロス)
○実況見分その八・お店の統一感
○見分を終えて
○リニューアルはちょっと待った!
○早朝五時三〇分。出来ることからスタートした
第四話 あの手この手! ホシを追え!
○なんか、良くなったんじゃない?
○まず、己を知って敵を知る。そして、己を磨く
○捜査は、自分たちだけでは進まない
○聞き込み調査
○張り込み調査
○的割(まとわり)調査
○よう撃調査
○地味な捜査があるからこそ……
○逮捕状
○顧客名簿獲得法
○着々と……
第五話 逃がすな! ホシだ!
○創業祭の準備
○故意・過失・未必の故意
○一年間は五二週
○ホシは、泳がせろ
○店内でのリズムとテンポ
○逮捕する瞬間
○創業祭当日
第六話 再犯を防げ! 更生への道
○油断大敵。事件はまた起きる
○ホシの自供
○「ホシ」というのは、そういうもの
○再犯防止
○捜査を継続させる
○一二月三一日、Cマート
○一二月三一日、捜査ゼロ課
○あれから三年……
●編集担当者より一言
刑事時代に培った徹底した現場主義を武器に、多くのお店の業績アップに貢献してきた著者・野元泰秀。
本書は、単に商売の基本を解説したハウ・ツー書ではなく、すべてのお店経営者の方への著者からの熱いメッセージ本としてお読みいただければ幸いです。