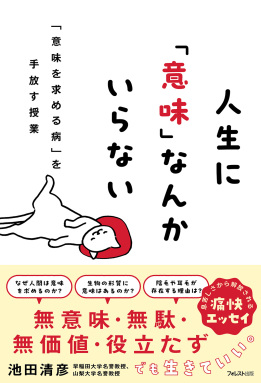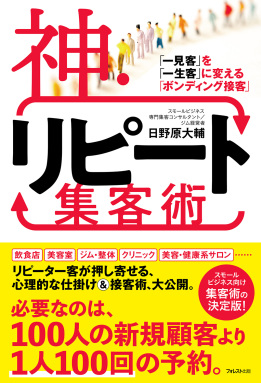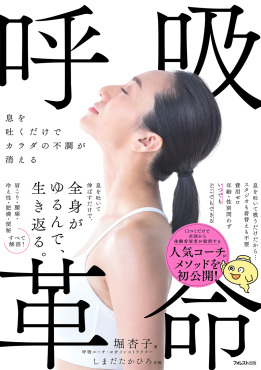著者の関連商品
著者の関連商品
-
私も「意味を求める病」に罹っていたと思います。幼少の頃から「夢を持て」「人に役立つ人になれ」とか言われたし、熱中して読んでいた漫画も、「努力は裏切らない」とか「人生には使命がある」「生きているだけで価値がある」といったセリフが出てきます。半ばそれを普遍的な言説として受け入れていたものです。そして、自分が考える理想の人生と現実が乖離しだすと、自分の人生に何の意味を見いせない虚しさと無力感に押しつぶされるのです。さて、そんな「意味を求める病」を手放すにはどうすればいいでしょう? 本書では、テレビでも活躍する生物学者の池田清彦先生が、「そもそも人生に意味なんかねえよ」「自分の好きなことをして楽しく生きればいい」という主張のもと、生物学や科学哲学のなどの観点から私たちを雁字搦めにする「意味」の呪縛を解きほぐしていきます。読み応え抜群かつ読後の心が軽くなること間違いなし!

POSTED BYかばを
View More私たちを息苦しくさせる「意味を求める病」を手放す
人間は「私は何のために生きているのだろう」「私は何かに役に立つのだろうか」など、自分の生きる意味や役割について考えてしまう生き物だ。
とくに、幼少の頃から「夢を叶えよう」「誰かの役に立つ人になろう」「一生懸命に働こう」などという甘言を浴びせられて生きてきた現代人だったらなおさらだ。
なぜなら、こうした言葉は「夢を叶えず、誰かの役にも立たず、ろくに働かない人生は失敗」という呪いの言葉に容易に変換されしまうからだ。
だから、必死に自分の人生の意味を探し、それが見つからないと絶望してしまう。
さながら「意味を求める病」に罹ってるかのようだ。
しかし、本書では「人生には意味があるべきだ」とかいった言説に普遍的だったり超越的だったりする価値はないと喝破する。
そのうえで、「人生に意味なんかなくてもいいじゃないか」「そもそも人生に意味なんてない」と主張し、「意味を求める病」を手放す生き方を提案する。
生物学や科学哲学の観点から、「意味」にまつわるテーマを縦横に掘り下げ、語り尽くす!
◎そもそもなぜ人間は意味を求めるのか?
◎ミッドライフクライシス(中年期の精神的危機)の原因は「意味を求める病」?
◎意味を求めすぎると至ってしまう反出生主義やスピリチュアリティ。
◎生物の形質にはすべて、環境に適応するためという意味があるのか?
◎なくても困らない陰毛や耳毛が存在する意味とは?
◎無意味・無駄・無価値・役立たずは本当に悪なのか?
◎なぜ人間は意味のわからないものを恐れるのか?...etc
目次
私が「人生に意味はない」と考えたわけ――まえがきに代えて
第1章 人生に意味はなくても楽しく生きられる
第2章 資本主義思考と意味の呪縛
第3章 本当はたくさんある意味不明な生物の形質
第4章 「無意味」への恐怖を克服しよう
あとがき――意味などないけど楽しく生きよう
-
起業の「本当の壁」とは何か? 頑張って集客しても、1回限りでリピート客にならないことだといわれています。しかも、「新規客の獲得」コストは、「リピート客の確保」コストの5倍かかるともいわれています。では、どのようにしてリピート客を増やしていけばいいのか? スモールビジネスにおいて切実な課題である「リピート集客」の極意を教えてくださったのが著者の日野原大輔さんです。自分がお客の立場だったら、間違いなくリピートしてしまうだろうと思ってしまう、実績に裏付けされた「心理的な仕掛け&接客術」が満載の1冊です。大手にはできない、スモールビジネスならではの闘い方がよくわかります。

POSTED BY森上
View Moreスモールビジネス専門集客コンサルタントが伝授!
飲食店、美容室、ジム・整体、
リピーターが押し寄せる仕掛け&接客術、大公開!
クリニック、美容・健康系サロン……。
これらスモールビジネスビジネスにおいて、
多くの方が悩んでいる、
一番の課題が「集客」でしょう。
もちろん、オープン当初の集客は、
SNSやチラシ、DMなどで認知・告知で、
それなりに大変です。
ただ、安定的な経営を続けていくために
一番重要なのは、
「リピーター」の確保です。
ある調査によると、
リピート客が定着せず、
オープン1年未満で閉店に追い込まれるお店は、
約60%ともいわれています。
せっかく新規で来てくれたのに、
2回目から音沙汰なし……。
せっかく集めたお客様を
どのやってリピート客にするのか?
その秘訣は、
【心理的な仕掛け&接客術】にあります。
それが、
スモールビジネス専門集客コンサルタントとして
多くの実績を出している著者が体系化した、
「一見客」を「一生客」に変える
【ボンディング接客】メソッドです。
お客様が積極的にリピートしてくれる
「ボンディング接客術」の6原則があります。
◆原則1:ボンディング・タイミング(間)
◆原則2:ボンディング・ディスタンス(距離感)
◆原則3:ボンディング・ボリューム(会話量・相槌)
◆原則4:ボンディング・ボルテージ(興味づけ・アピール熱血度)
◆原則5:ボンディング・アチーブメント(目標共有)
◆原則6:ボンディング・インターバル(接触頻度)
この6原則に基づいた
具体的な思考法と実践法を
徹底解説したのが本書です。
「新規客の獲得」コストは、
「リピート客の確保」コストの5倍かかる
といわれています。
必要なのは、
100人の新規顧客より
1人100回の予約です。
あなたも、
お客様と確実に心の絆をつくる
最強接客メソッドを身につけて、
「リピーターに支えられるストック型ビジネス」
をぜひ実現してください。
気になる本書の内容
本書の内容は以下のとおりです。
はじめに
第1章 うまくいくビジネスはリピートが9割
小手先の集客テクニックはお客さまに刺さらない
起業における「本当の壁」とは?
「本当の壁」に当たって気づいたこと
今さらブルーオーシャンを狙ってはいけない.
なぜ「ブルーオーシャン」参入は危険なのか?
自分がやりたいことで、最小限のコストで集客する方法
対象客の望み&行動導線に、徹底的に合わせる
不況に強いのは「ちりつも少売」
リピーター心理の原点
コロナ後にお客が戻ってきた店、戻らない店の違い
「人の気」を集めるから、「人気店」になる
実力があっても人気者になれない人に足りないもの
人気度を計るために必要な3要素と計算式
知識も技術も超える「力」の正体
100人の新規顧客より1人100回の予約
「リピーターによるストック型経営」実現に向けた基本的な考え方
「新規客より既存客を大事にする」という発想
「本音で接客する」とはどういうことか?
お客さまが帰ってきたくなる「サードプレイス」の特徴
演じない自分でいられる場所
お客さまにとっての「サードプレイス」になるために
自分のサードプレイスから学んだこと
ファンは「お店」ではなく、「スタッフ」につけなさい
スモールビジネスが大手に勝つ、唯一の方法
お客さまに本気で興味を持つとは、どういうことか?
うまくいく商売の法則「リピーター8割:新規2割」
リピーターがいるメリット
店側は、リピーターをコントロールできない
リピーター客と新規客の理想的な比率
リピート客から新規客を紹介されたときの最大の注意点
第2章 どんなビジネスも「つなぎとめる技術」でうまくいく
一度の感動で「リピ決定」、一度のがっかりで「星1」の評価
初回客にまず伝えるべきこと
「なぜ」を伝える重要性
「なぜ」「誰を」をしっかり伝えても、リピート客にならない原因
お客さまは「通わなくなった理由」を説明しない
来なくなった理由の向こう側にあるもの
お客さまが黙っていなくなる前に講じたい接客メソッド
「マンツーマン・コミュニケーション」のやり方
「相手に寄り添う」とは、どういうことか?
「ボンディング」はスタッフとお客さんをつなぐ〝接着剤〟
いきなり接着させようとしない
接着する前に、お客さまの3つの情報を知る
よかれと思っても、まず細かく確認
「すぐに思い出される人」VS「スルーされる人」
「誰がやるか」で変わる
「高級ホテルの接客」と「小さな旅館の接客」で、求められるものが違う
お客さまの脳に刻まれやすいもの
エピソード以外で印象に残す方法
お客さまのサポーター&伴走者になる
人は「変わること」に恐れているから、こちらができることがある
お客さまの夢・目標の実現に向けて伴走する
長期のパートナーシップを築くコツ
「間合い」がいいと、「息ピッタリ」の信頼関係ができる
「ボンディング・タイミング」の3つのポイント
間が合うと、人は素直になる
タイプ別で「間」の合わせ方を使い分けよ
ボンディング・ディタンスで、間合いを合わせる
相手の「間」に合わせるポイント
売れるアパレル販売員の間合い
会話量の理想的な割合──ボンディング・ボリューム
「無言の相槌」が最強のエンゲージメントをつくる
お客さまの本音は、最後に出てくる
傾聴力が身につく「うなずきの練習」のポイント
第3章 また会いたくなるコミュニケーション・テクニック
本心に気づかせてあげるのが最強のサービス
お客さま自身に気づかせるコツ
お客さまに結果を言語化させて、プロとして承認する
「1人ビジネス」は、専門性が期待されている
専門性がスモールビジネスの最強の武器
専門性をリピートにつなげる方法
お客さまが熱くなる「キラー話題」をつかみなさい
お客さまとの距離をグッと近づけるプライベート・コミュニケーションとは?
キラー話題の探り方
キラー話題が重要である、本当の理由
「買わないと損」「やらないと損」と思わせるテクニック
自分の商品・サービスの希少性は何か?
希少性の種類
「買ってください」より「売ってあげます」に人は集まる
商品・サービスに、絶対の自信があればできること
お客さま視点で、ライバル店を紹介する理由
自分の商品・サービスに自信があれば、返金はいとわないという覚悟
買ってもらわなくてもいいお客さまには無理に売らない
お客さまをほめていいシーン、ダメなシーン
お客さまに対して「お世辞になっていないか」と思ったら……
ほめ上手のコミュニケーション術
ほめる練習のポイント
ほめテクニック(上級編)
旧世代コミュニケーションの効力を無視してはいけない
自動化しないほうがいいサービス
アナログなコミュニケーションの効用
共通点の言語化で、「相棒感」を創出
ラポール形成力は、環境・経験で変わる
お客さまとの相性を意識したスタッフマネジメント
ラポール形成力を上げるテクニック
第4章 お客さまの「目的の裏側」を知る
お客さまは「メリット」より「ベネフィット」を求める
「メリット」と「ベネフィット」の違い
トレーニング業界での、メリットとベネフィットの違いとは?
あなたの商品・サービスの「ベネフィット」は何?
お客さまに未来の姿を想像させる──ボンディング・ボルテージ
お客さまの「隠れた目的」を知る3つの質問
「潜在ニーズ」のさらに深層にある「インサイト」を引き出せ
顧客インサイトを引き出す質問──ボンディング・アチーブメント
顧客インサイトを引き出す質問の使い方
お客さまとの会話を通じて、一緒に答えを見つけていく
「ワークライフバランスに沿わない」要望は却下する
自分の商品やサービスがお客さまの日常生活の一部になる喜び
お客さまのライフワークバランスを崩してはいけない
無理が生じるお客さまにやめさせる提言は、逆に信頼をつくる
目的達成の寸前に「次の夢」を語らせなさい
予約の無限リピートを実現する秘策──感動の創出
ダイエットのあとに見つけた次の夢
次の目標を設定する、理想的なタイミング
「この先、さらに素敵な世界がある」ことを教える
リバウンドする「劇薬」より「10年後の幸せ」を売る
未来の幸せを語る責任
10年後の幸せをプロ目線で語る
第5章 「スタッフ」から「人生の相談相手」になる方法
売っているのは、商品ではなく、あなた自身
「売っている人も商品の一部」の時代
「自分を商品化する」3つのポイント
どんな商品も「悩みを解決するため」に存在する
相手の心を開くボタンはどこにある?
相手の心のボタンを押すための2つの秘策
なぜ帰り際の雑談が大事なのか?
売り手が世界一の愛用者であるべきたった1つの理由
知識を知恵に変える方法
お客さま目線で見えてくる、新たな気づき
自己開示すると「特別な関係」が始まる
本音を聞き出すのが難しいお客さまへの対策法
お客さまの心の扉が閉じてしまう禁止事項
自己開示から生まれる3つのメリット
お客さまからの「相談ごと」は、「追い風」のサイン
もしお客さまから相談されたら……
ある保険セールスレディに学ぶ、信頼関係のつくり方
お客さまの「人生の一部」になれていますか?
3年以上の付き合いは、知識も経験も超える
お客さまの人生に必要な存在たれ
「やっぱり、この仕事っていいな」と心から思えたこと
ゆるぎない信頼関係とは何か?
第6章 「お客さま」扱いすると「お客さま」が来なくなる理由――接客の落とし穴
お客さまを「神様」扱いすると「モンスター」が増える
「お客さまの言いなりになれ」ではない
ルールを破る人は、お客さまではない
スタッフと大切なお客さまを守るために
「広く浅くたくさん」集めるより、「狭く深く少なく」集める
スモールビジネスに合った市場規模がある
ターゲットに合った広告媒体、広告を出す時期を探る
ウェブサイトと紹介キャンペーンのポイント
見込み客を探しに行く「イベント出店」のポイント
お客さまに「先生」と呼ばれると、生涯の関係性ができる
「先生」という言葉だけの独り歩きにご用心
先生としてやってはいけないこと
「家でできること」を教えると、来店しなくなる
まず1回、断ったほうがいい理由
宿題を欲しがるお客さまの共通点と対処法
宿題を出さないほうが、再来店率がアップ!?
「同業他社」の批判は、「自信のなさ」の裏返し
同業他社の批判で、どんなメリットがあるか?
他業界のプロモーション手法を取り入れてみる
他社をリスペクトしつつ、自社をポジティブに伝える
第7章 お客さまがファンになる質問の仕方――予約のルーティン化
店に来なければいけない「仕掛け」をつくる
次の予約を取る、絶好のタイミングとは?
なぜ先に予約を取ったほうがいいのか?
開始前の予約取りは、お客さまにもメリットあり!?
直接言わずに、次の予約を取る「仕掛け」
リピートには「進捗チェック」が必須
変化を追いかけ、不安を取り除く
リピート率が上がる「アフターフォロー」のやり方
「目標達成」の絶対条件として「2回先」までの予約を取る
「2回先」までの予約を取るために、絶対やるべきこと
業種別で解説、2回先までの予約の取るアイデア
「オーダーメイド」で浮気防止
お金も人手もかからない、「オーダーメイド」サービスのつくり方
こんな「オーダーメイド」は逆効果
「あの話の続き」をしたくなる「雑談テクニック」
雑談が苦手な人のための、7つの雑談ネタ
雑談をリピートにつなげるコツ
顧客タイプ別「辞めたい」と言われたときの対応策
嫌われるのは承知で、コレを聞く
再び戻ってきていただける関係づくり
おわりに
-
嬉しいことに編集者の元にはたくさんの持ち込み企画が届きます。ボツになるものがほとんどというなか、堀さんの企画書にはなにか光るものを感じて連絡したところ・・・「まずは体験レッスン受けてみませんか?」と誘われ、実際に呼吸トレをやってみてビックリ!鼻からふんっと息を吐きながら体を動かすだけで体中が軽くなり、なにより不思議と体幹がしっかり入るのです!堀さんのレッスンの特徴は最後に「ヘッドスタンド(三点倒立)」がやすやすとできるようになること。とにかくびっくりの連続からスタートした企画でした。毎日を健康的にすっきりした気持ちで過ごしたい万人におすすめできます!

POSTED BY寺崎
View Moreふだんの呼吸を
ふだん、あなたはどんな呼吸をしていますか?
「鼻から吐く呼吸」に変えるだけ
「胸の上のだけの浅い呼吸になっていませんか?」
「仕事中、無意識に呼吸が止まっていませんか?」
「鼻ではなく、口呼吸になっていませんか?」
この本では、ふだんの呼吸を鼻呼吸に変えるだけで、体や脳のすみずみまで元気になるのはもちろんのこと、あなたが自分でも気づいていない可能性を思いっきり開いて、ガラリと人生を変える、呼吸で最高の自分を引き出して、人生に革命を起こす方法をお伝えします。
やり方は簡単。
ただ、鼻から吐く呼吸にだけ意識して、「ふーっ」と吐くだけ。
それだけです。
呼吸は、私たちが生きていくうえで欠かせない生命活動です。
人は、30日間食べなくても、水は3日間飲まなくても、死にません。
ところが、呼吸はたった3分間しないだけで死んでしまいます。
しかし、これほど重要な呼吸について、私たちはわざわざ教わったりしません。
あらゆる不調が改善し
本書でご紹介する「呼吸トレ」を実践して呼吸する力が強くなると、あらゆる不調が改善するだけでなく、体に軸が入ると同時に、心にも軸が入るため、迷ったり、悩んだり、落ち込んだりという時間が圧倒的に減ります。
潜在的なエネルギーが引き出される!
「呼吸トレ」は、いつでもどこでも、お金をかけずに、老若男女問わずできる、とてもシンプルかつ効果の高い実践的なトレーニングです。
ただ、鼻から息を吐く呼吸に合わせて動いていくだけですが、心身の不調を改善する効果は絶大。
にわかには信じがたいかもしれませんが、著者の生徒さんトの中にも、呼吸を変えただけで長年の睡眠障害が改善したり、プロアスリートとしてパフォーマンスが飛躍的に向上した方など、健康を取り戻すとともに、自身の可能性を大いに羽ばたかせている人がたくさんいらっしゃいます。
そして本書でいちばん伝えたいのは「呼吸のすごさ」です。
鼻から吐く呼吸に変えることが、あなたの体と心を整え、呼吸で引き出される潜在的なパワーを実感することでしょう。
あなたの中にまだ眠る潜在的なパワーを、呼吸革命で引き出していきましょう。
本書のオリジナルキャラクター「呼吸ちゃん」がトレーニングの伴走をしてくれます。
※「呼吸トレ」LESSON1~16すべてにQR動画付き
本書の構成
プロローグ 呼吸ちゃんとの出会い
はじめに 不調だらけのドン底人生から呼吸コーチになるまで
Chapter1 自分を変える呼吸革命――呼吸が変わると人生が変わりだす
「浅い呼吸」が脳の酸欠を引き起こす
過度な「活動モードON」の状態で緊張状態にある私たち
脳は酸素を貯蔵できない
吐く息で脳のクリーニング習慣を身につけて頭のノイズとさようなら
行動に移せない原因の多くは「脳の酸欠」
「吐いて吸う」への意識革命を起こす
呼吸トレ① 基本の鼻呼吸・首~頭部
LESSON1 「吐いて吸う呼吸」の基本
LESSON2 首から上すっきり呼吸トレ①
LESSON3 首から上すっきり呼吸トレ②
LESSON4 呼吸トレによる変化のチェック
LESSON5 寝起きの体の起こし方
Chapter2 呼吸トレが改善する〝体の詰まり〟
〝体の詰まり〟があらゆる不調を引き起こす
呼吸トレで体の詰まりを解消する
マッサージでは届かないところに効く「呼吸トレ」――〝絞り〟と〝伸ばし〟で深部にアプローチ
呼吸トレで自分とコミュニケーションをとる
「1日ひと呼吸」の習慣化
息を吐くことで心と体をリンクさせる
呼吸トレ② 肩甲骨・肋骨・横隔膜
LESSON6 肩甲骨の呼吸トレ①
LESSON7 肩甲骨の呼吸トレ②
LESSON8 呼吸トレによる姿勢の変化のチェック
LESSON9 横隔膜の呼吸トレ①
LESSON10 横隔膜の呼吸トレ②
LESSON11 横隔膜のらくちん呼吸トレ
LESSON12 おなか回りの呼吸トレ
呼吸トレ体験者の声 ①
Chapter3 呼吸トレで全身デトックス
呼吸トレで体の中のゴミを洗い流す
呼吸トレで快便体質を手に入れる──ポイントは「横隔膜」
滞りやすい場所は体の「際(きわ)」
リンパ液が滞るとむくみの原因に
動かしていない筋肉はボケて滞る
身体からのメッセージを受け取る──痛みは患者ではなくあなたのパートナー
呼吸トレ③ 下半身
LESSON13 もも裏の呼吸トレ
LESSON14 おしりの呼吸トレ
LESSON15 背骨の呼吸トレ
LESSON16 足のむくみスッキリ呼吸トレ
呼吸トレ体験者の声 ②
Chapter4 「吐く息」で潜在パワーを引き出す
潜在意識が私たちの生命を支えている
たった10%以下の潜在意識だけで頑張るからうまくいかない
息を吐くことに集中して「潜在意識」の力を活性化させる
息を抜ける人ほど、人生の流れはよくなる
息をしっかり吐いていれば、何が来たって大丈夫!
無意識に意識を向けると、人生は劇的に変わる
エピローグ ずっと一緒だよ
おわりに 息をすることは、生きること
購入者限定無料プレゼント
SNS非公開の秘伝の呼吸法(動画)
「吐く息」の極意、そして本書ではお伝えしきれなかった呼吸トレを数種ご紹介します。
この動画は本書をご購入いただいた読者限定の特典です。
※無料プレゼントは、お客様ご自身で別途お申し込みが必要です。
※無料プレゼントは、サイト上で公開するものであり、
CD・DVDなどをお送りするものではありません。
※無料プレゼントのご提供は予告なく終了となる場合がございます。
あらかじめご了承ください。
-
医者も栄養士も知らない「食生活の落とし穴」ミネラル不足View More
その実態を明らかにする本
不調が続いていたり、病気が治らないでいる方、そんな家族、知人がいる方に、不調や病気の原因を取り除いて、食事で良くする方法を知っていただくのが本書です。
医者も栄養士もほとんど知りませんが、不調や病気が多い原因は、微量栄養素とミネラル不足です。
私たちは14年前からミネラルを検査してきました。大手スーパーやコンビニで、よく売れている人気の食品を買い、信頼できる検査機関に依頼して検査した数は200を超えました。その実測値を「日本人の食事摂取基準」(厚生労働省のガイドライン)に当てはめると、ミネラル不足で心身に障害が起きている人は、国民の半数をはるかに超えます。
もくじ
まえがき
第1章 17の「違反食品」
市販弁当で1日をすごす
調理済み冷凍食品で1日をすごす
レトルト食品で1日をすごす
コンビニの食品で1日をすごす
違反食品①:コンビニ幕の内弁当
違反食品②:高齢者向け宅配弁当
違反食品③:ねぎ塩豚カルビ弁当
違反食品④:天丼
違反食品⑤:コンビニおにぎり
違反食品⑥:ランチパック
マクドナルド・ハンバーガー
ベースブレッド
完全メシあんぱん
違反食品⑦:冷凍・とり加工品
違反食品⑧:冷凍チャーハン
違反食品⑨:冷凍海老ピラフ
違反食品⑩:冷凍シュウマイ
冷凍総菜カップ「竹の子煮」
違反食品⑪:レトルトカレー「プロクオリティ」
違反食品⑫:レトルトカレー「ホテル・シェフ仕様」
違反食品⑬:レトルト・ナポリタン
違反食品⑭:レトルト・ミートソース
違反食品⑮:コンビニ・スーパーの肉じゃが
違反食品⑯:コンビニ・スーパーの筑前煮
違反食品⑰:コンビニ・ハンバーグ
完全メシ 豚辛ラ王 油そば
ミネラルラーメン
第2章 発達障害児が激増する原因
第3章 ミネラルが少ない理由
第4章 笑顔を取り戻した子どもたち
第5章 子どもの成績が上がった
第6章 健康になり、人生が変わった
第7章 シニアも高齢者も元気になった
第8章 ミネラルが不足するとこうなる
第9章 「失われた30年」の原因
第10章 「いつでも、どこでも、誰でもできる」ミネラル摂取法
あとがき
【発行】三五館シンシャ/【発売】フォレスト出版 -
旧版が出たのが2019年。コロナ禍を経た2023年現在でも、日本の人財不足はいまだ深刻な状態です。そんな「人手不足」が起こっている現実がありながらも、国内に働き手がいないのかといえばそうではありません。失業率は年々改善されているものの、就職ができない人たちが存在しています。
では、日本の採用市場には何が起こっているのか?
企業側と求職側の「マッチング」がうまくいっていないのです。
というのも、国際競争力が年々加速する今、企業側に求められるのは、単なる「人手」ではなく、優秀な「人財」の採用です。そうなってくると、数が限られている「人財」は奪い合いになるわけです。そんな限られたいい「人財」を、どのように集めて、見抜いて、つかまえ、離さないようにすればいいのか? いい人財が「集まる」会社は、どういう考え方で採用活動をし、採用戦略を練っているのか? ロングセラーの採用バイブルが、最新データを盛り込み、200ページ超の大幅加筆という超パワーアップした形で新登場しました。
POSTED BY森上
View More最新データを盛り込んで、200ページ超の大幅加筆!
ベストセラー『日本でいちばん大切にしたい会社』著者が完全監修、
ロングセラーの採用バイブルが、
超パワーアップして新登場!
中小企業の採用コンサルのスペシャリストが説いた
いい人財を集めて、見抜き、つかまえ、離さない技術――。
採用関連本のロングセラー作品
『いい人財が集まる会社の採用の思考法』が、
最新データはもとより、
いい人財を採用するための採用ステップメソッドを
新たに大幅加筆して、
【増補改訂版】として新登場しました。
大幅加筆の分量は、驚きの200ページ超……!
新たに加わった図版分量も旧版の2倍以上!
もはや、旧版に書籍1冊分がプラスされたと言っても過言ではありません。
「ウチは無名・中小だから人が集まらない」
「人手不足だから採用基準を下げる」
「採用してみないとわからない」
「コミュニケーション能力が高い人が欲しい」
「とにかく即戦力!」
「志望動機が言えないから不採用」
などなど、
旧版でも好評だった
多くの採用担当者や経営者が陥りがちな
残念な採用の思考法を覆す、
いい人財を集めて、見抜き、つかまえ、離さない技術は、
最新データを織り交ぜながら、
よりリアルに、よりわかりやすく解説しています。
今回の目玉は、何と言っても、
いい人財を採用するための「採用の5ステップ」メソッドを
本書で初公開している点です。
採用の5ステップとは、
①WHY:何のために採用するか?(採用目的の言語化)
②WHO:どんな人を採用するか?(採用人物像の言語化)
③WHAT:提供できる価値は?(入社するベネフィットの言語化)
④WHEN:いつ伝えるか?(動機づけ&見極めプロセスの設計)
⑤HOW:どうやって伝えるか?(募集手段の選定)
この順番で整理し、
「採用の戦略策定を練る」というものです。
5つそれぞれのフェーズで
何を、どのように整理し、実施していけばいいのかを
具体的にわかりやすく解説しています。
そのなかには、
◎自社に合った採用基準のつくり方
◎求職者のペルソナ設定法やその言語化の手順
◎いい人財を自社に惹きつける動機づけの方法
◎エントリーシートの有無
◎効果的なスカウトメールの書き方
◎いい人財をつかむ面接の流れ
◎オンライン面接のポイント
などなど、
より具体的な現場に則したノウハウも
盛りだくさんです。
「人手」ではなく、
「人財」を集めるために
どういう考え方で採用活動をし、
採用戦略を練っていけばいいのか?
その思考法&実践法を完全公開しています。
著者は、
中小企業の採用コンサルのスペシャリスト。
加えて、
ベストセラー『日本でいちばん大切にしたい会社』
著者が完全監修。
この最強タッグが、
最新データと最強のノウハウを交えながら、
人財不足で悩む中小企業のために、
いい人財を集めて、
見抜き、つかまえ、離さない技術を徹底解説します。
気になる本書の内容
本書の内容は以下のとおりです。
はじめに――あの会社はどうして優秀な人財を採用できるのか?
第1章 採用をなめてはいけない──採用の失敗が与える影響とは?
いい採用ができない会社に共通する「最悪の勘違い」
「人さえいれば……」という時代!?──急増する「人手不足倒産」
あなたの会社の採用がうまくいかない、根本的な原因
やっぱり、採用も「始めが大事」── A good beginning makes a good ending.
「始め」を疎かにするデメリット
「採用を真剣に考える」とは、実際どういうことか?
焦って人を採用すると、ロクなことがない
イメージしていた人物像に近い人が応募してきた!
採用後に発覚した期待外れの「即戦力」
採用にはこんな責任が伴う
採用は「点」でなく、「線」と「面」で考える
確かに「人手不足にあえいでいる」けれど……
たった1人の採用が変えた未来
組織力も売上アップも、まずは素材から
成果が上がる組織の公式
一流のリーダーでも、限界はある
人を見抜く力こそ、経営力である
採用は「競争」だと、ホントにわかっていますか?
採用の市場原理
「採用してみないとわからない」のウソ
選考で特にどこを重視したかで、その会社の経営力がわかる
採用は、勝つか負けるか
求職者の心理プロセスの中身
なぜ営業活動より採用活動のほうが厳しいのか?──限られたパイを奪い合う戦い
採用活動に必要な精神は、「ギブ・アンド・ギブ」
学生が成長する機会
「企業の社会的責任」を果たすのが採用活動──選考する企業側の社会的責任(CSR)
本気で向き合う選考プロセスが生み出す大きなメリット
「インターンシップ」での注意点
だから、採用をなめてはいけない──第1章のまとめとして
第2章 いい採用ができない会社の5つの理由
いい採用ができない会社の5つの理由
ダメ採用は、ダメ営業?
ダメ営業マンは何が間違っていたのか?
ダメ営業マンも、採用に苦戦している人も、変われる
「片手間でやっている」から、うまくいかない──いい採用ができない理由①
片手間でやっているかどうかの基準
大企業のいい採用ができる理由は、知名度以外にある
いい採用ができる中小企業にあって、いい採用ができない中小企業にないもの
「他責にする」から、うまくいかない──いい採用ができない理由②
同じ商品でも売れる営業、売れない営業の違い
トップセールスマンの「商品への自信」に学ぶ「自社への自信」のつけ方
他責にした瞬間に起こること
「相手を知らない」から、うまくいかない──いい採用ができない理由③
知らなければ、戦略も立てられない
求職者について知っておくべきこと
情報は、待っていても入ってこない
「マーケットを知らない」から、うまくいかない──いい採用ができない理由④
「マーケットを知っている」とは、どういうことか?
採用のマーケティング
「計画性がない」から、うまくいかない──いい採用ができない理由⑤
「あたりまえ」になっているか?
採用のPDCAサイクル
自社の採用活動を再チェック──第2章のまとめとして
第3章 いい採用を実現させるために案外やっていないこと
「どんな人を採用するか」を決めていない
経営の問題の根源とは?
採用の質を下げても、お客様への提供の質は下げられない──誰を採用するか①
質の優先度を下げる会社、増加中
採用するうえで、一番やってはいけないこと
安易に採用基準を下げると、組織は疲弊する──誰を採用するか②
「採用基準」を下げていいのは、この2パターン
採用基準を下げるかどうかは、入社後の教育をセットで考える
3つの覚悟があれば、採用基準を下げてもいい
誰をバスに乗せるか──誰を採用するか③
行き先を決める前にやるべきこと
「誰をバスに乗せて行きたいか?」を言語化する
採用を妥協したらどうなるか?──誰を採用するか④
採用後の教育でなんとかなる!?──私の失敗談を交えて
「採用の失敗」のデメリットは、売上減だけにとどまらない
「人財」ではなく、「人手」の採用になっていないか?
常に探し続ける
いい人財を見抜く基準──採用基準を設定する正しい方法①
採用要件を盛り込みすぎない
人財の素質を見抜く2つのポイント
「先天的・後天的能力」を見抜く──採用基準を設定する正しい方法②
人間の意識レベルには5つの階層がある──ニューロロジカルレベル
人の意識を変える手順──正しい「場」を設計する
コミュニケーション能力は、入社時には必要のない能力
「後天的に」伸ばせる能力は、採用基準から外す
採用後に、簡単に伸ばせる能力、伸ばすのに時間を要する能力
「価値観」のマッチングを重視する──採用基準を設定する正しい方法③
教育しても変えられないもの
絶対に外せない採用基準
価値観が合う人を採用する──第3章のまとめとして
第4章 採用戦略を5ステップで立てる
貴社の採用活動の「あたりまえの基準」チェックテスト
採用活動を3つに分解する
貴社における「自社にとって適切」が決まっているか?
いい人財を採用する戦略策定の5ステップの効用
いい人財を採用する戦略策定の5ステップとは?
なぜHOWから始める採用活動がダメなのか
急がば回れ!
問題は募集手段(メディア)ではない
採用がうまい会社が、メディア選びの前に決めていること
過去の成功体験というワナ
WHY:何のために採用するか?──採用目的の言語化
人の心は、WHATではなく、WHYで動かされる
WHYのマッチングこそ、真のマッチング
あなたの会社にしかないコンテンツをつくるベースがWHYである
「WHY」とは、「何のために」と考える
実際に「WHY」を言語化する際の注意点
「WHY」を言語化するための切り口①
「WHY」を言語化するための切り口②
「人手募集」では集まらないワケ
WHYを求人票に反映させた一例
WHO:どんな人を採用するか?──採用人物像の言語化
「WHY」の次に「WHO」である2つの理由
受け手が誰かによって、メッセージは変わる
自社の特徴を誰に伝えるか?
求職者のペルソナ設定が重要な理由
採用人物像(WHO)の言語化手順
WHAT:求職者に提供できる価値は何か?──入社するベネフィットの言語化
求職者の内面に徹底的に目を向ける
従業員12名の会社に1・5カ月で37名の応募者があった理由
企業側と求職者側に存在する「情報の非対称性」を認識しているか?
完璧な会社はない
言葉は「約束」
WHYから始め、WHOとWHATを整理する──第4章のまとめとして
第5章 いい採用を実現させる具体的なステップ
WHEN:いつ伝えるか?──動機づけ&見極めプロセスの設計
必要かどうかは、受け手が決める
ご縁がなくても、「受けてよかった」と思わせる
求人票、説明会、面接……それぞれの場面で伝わり方は変わる
認識を一致させるのに、言葉だけでは限界がある
言葉に体験を組み合わせて、初めて理解する──理解=言葉×体験
そのメッセージには一貫性があるか?
まずは認知! 御社を「知らない」から応募がない──いい人財を集める①
人は未知のものを怖がり、不安だから近寄らない
知らない=怖い
「知らない」を「知っている」に変えなければ始まらない
求職者に何と声をかけて、振り向かせるか?
採用に成功する会社は、「写真」を大事にする
採用する「人数」と「期限」を定める──どう採用するか①
なぜ「期限」設定が必要なのか?
理想的な期限設定
中途採用で「期限なし」は危ないワケ
採用戦略・シナリオをつくる──どう採用するか②
採用活動の数値化はできているか?──採用パイプライン
採用パイプラインを使ってシナリオを作成してみる──採用活動をスムーズにするためのシナリオ作成術
「これまでこうやってきたから」という前提を見直す──そのエントリーシート、必要?
エントリーシートでハードルを上げることに意味はあるか?
エントリーシートによって奪われるもの
エントリーシートを廃止しても、こうすれば大丈夫
「誰が採用するか」で採用の結果は変わる
人生を変えた1冊の本と1本の電話
「何をするか」より「誰がするか」
買い手が企業? 売り手が求職者?
採用担当者に求められるスキル
HOW:どうやって伝えるか?──募集手段の選定
どうやって求職者に伝える?
採用の歴史からひも解く、採用活動の変遷
自社に合った募集方法を選ぶ際の注意点
「リアル」「早期化」重視の時代
中途採用における8つの募集手段
強くて愛される会社がやっていること
「将来のお金で買えない利益」の真意
自社に合った採用方法の見つけ方
エントリーは、「量」より「質」──いい人財を集める②
量に比例してかかる3つのコスト
「はじめまして」で伝えるべき情報──いい人財を集める③
人が動かない4つの理由
目には入っても、脳には入っていない
「知らない」を「知ってもらう」に変える秘策──「インパクト」×「コンパクト」
「はじめまして」のあとにつなげるべきこと
効果的なスカウトメールの書き方①──件名
効果的なスカウトメールの書き方②──メール本文
求職者に興味を持たせる技術──いい人財を惹きつける
会社説明会では、説明はいらない
求職者が求める知りたい情報とは?
知名度が低い会社がマッチングの精度を上げた方法
見極め、惹きつける技術──いい人財をつかむ面接術
採用面接を行なう2つの目的
面接官が持つべきスタンス
面接官は誰がやるのか?──いい人財をつかむ2つの役割分担
オンライン面接でのポイント
相手のホンネを引き出し、こちらに惹きつける面接の流れ
面接中に、面接官として心がけておきたいポイント
見極めるポイントは、結果主義でなく、プロセス主義──できる面接官が持っている「掘り下げ力」
掘り下げることで、惹きつけられる
候補者が話しやすい配慮のコツ
適性検査と人間の役割
志望動機は聞かない
志望動機とは、自分と会社をつなぐもの
自社が候補者にどういうポイントで選ばれたいか?
いい人財を逃さず「動機づけ」する技術──内定者フォローの方法
内定辞退者続出の時代
内定者フォローは延長戦
内定者フォローの目的とスタンス
内定者フォローの3つのポイント
採用活動に行き詰まったら……──候補者からひも解いて、採用活動を再構築
問題解決の3つのステップ
問題を特定する
候補者を主語にして議論する
間違った採用をリカバリーする方法
人間が幸せを実感するとき
「日本でいちばん大切にしたい会社」に学ぶ人財採用の目的
「間違った採用」の定義
ミスマッチを防ぐ施策
間違った採用をしてしまったら
おわりに