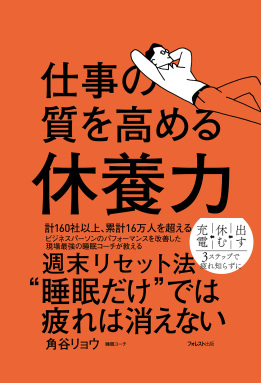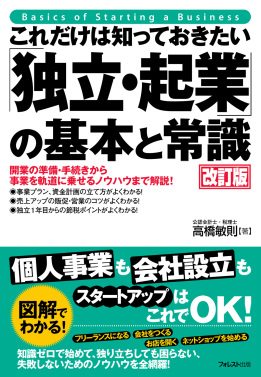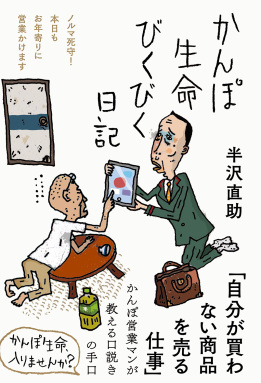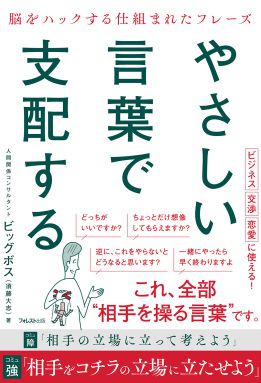著者の関連商品
著者の関連商品
-
「パワハラ・モラハラ」「心理的安全性」「早期退職」……。時代が変わり、ビジネスの現場では、部下への指示や依頼をする際のコミュニケーションでとまどい、思い悩むリーダーやマネージャーが急増しているようです。時には、組織や部下にとって、耳の痛い話、言いにくいことを言わなければならないときもあるでしょう。でも、「パワハラ・モラハラ」を気にしすぎて、言うに言えない。私のまわりでも、そのような愚痴や悩みを見聞きします。だから、できるだけ余計なことは言わない。指摘しない。すると今度は「注意してくれない」「教えてくれない」「成長機会の損失」と言われる。上からは「上司としての指導力が足りない」と言われる始末……。このような状態であれば、「管理職は罰ゲーム」といった言葉が湧き上がってくるのも無理ありません。それぐらい、今のリーダーやマネージャーは、とても窮屈な状態にあると言っても過言ではありません。
そんな悩みに対して、コミュニケーショントレーナーとして活躍中の司さんは、心理学ベースで体系化したコミュニケーション・メソッドを開発。そのメソッドを、実用性の高い形でわかりやすく解説してくださったのが本書です。部下とのコミュニケーションに悩むリーダー、マネージャーにお役立ていただける仕上がりとなりました。
POSTED BY森上
View More【パワハラ・モラハラを気にして
部下にフィードバックをするとき、
「言いにくいこと」を言えない
全マネージャー、リーダー必読の書】
「反発されたらどうしよう」
「雰囲気が悪くなったら嫌だな」
「モラハラ、パワハラと言われたらどうしよう」
「こんなことを言ったら、明日から来なくなるかも……」
そんなふうに思って、
言うのをためらった経験がある
リーダーやマネージャーが近年急増しているようです。
でも、言わなければ、
部下が変わらない。
チームや組織も良くならない。
では、どのように伝えればいいのか?
そんな悩みを抱えている
全リーダー、マネージャーに向けて、
部下を傷つけず、
パワハラとも受け取られずに、
「言いにくいこと」や「耳の痛いこと」を
上手に伝える技術
を徹底解説したのが本書です。
そのベースとなるのが、
日本随一のコミュニケーショントレーナーとして知られる
著者が体系化した
「QFB-3SC」コーチングメソッドです。
このメソッドを使えば、
相手に「言いにくいこと」「耳の痛いこと」を
ストレスフリーで的確に伝えることができます。
そしてなにより、
このメソッドで伝えられた相手は、
自ら考え、動き出します。
「心理的安全性」「パワハラ防止法」「早期退職」……、
このように上司にとって息苦しい環境であっても、
リーダーやマネージャーは、
上司として言わなければいけないことを、
しっかり相手に伝えられるようになります。
部下とのコミュニケーション、育成に悩む
全リーダー、マネージャーに役立つ1冊です。
気になる本書の内容
本書の内容は以下のとおりです。
第1章 部下を萎縮させる「NG対応」を
やめることから始めよう
◎なぜ基本的なタブーを知っておいたほうがいいのか?
◎「ハラスメント回避」6つのポイント
◎【回避ポイント①】1対1で個別に伝える
──第三者の前で指摘せず、本人のプライドに配慮する
◎【回避ポイント②】事実に基づき、具体的に伝える
──憶測で話さず、客観的事実で納得感を高める
◎【回避ポイント③】感情的にならず、冷静に伝える
──怒りをぶつげず、冷静な対話で反発を防ぐ
◎【回避ポイント④】相手の言い分も聞く
──一方的に話さず、相手の考えや事情も理解する
◎【回避ポイント⑤】改善策を一緒に考える
──突き放し厳禁!改善策は知恵を出し合う姿勢で
◎【回避ポイント⑥】いいところを見つける
──短所だけでなく長所も認め、成長意欲を高める
◎「言いにくいこと」をストレスフリーで伝えるメソッド
◎組織を内側から変える3つの隠れた効果
――「QFB-3SC」コーチングメソッドの真価
第2章 部下が自ら成長する対話の「仕込み」術――「QFB–3SC」コーチングメソッド
◎現場で発生しているリーダーシップコミュニケーションの壁
◎「QFB–3SC」コーチングメソッドの基本
◎メソッド開発の原点
◎Tさんの指導と「QFB–3SC」メソッド
◎事例で見る「QFB–3SC」メソッド活用法
◎【ケーススタディ】取引先へのプレゼンで失敗した部下
◎なぜ部下はやる気をなくすのか?──従来型のフィードバックの問題点
◎なぜこのフィードバックは、機能しないのか?
◎【解決策】「QFB–3SC」メソッドを使ったフィードバック──QFB編
◎なぜこのフィードバックは心に響くのか?
◎【解決策】「QFB–3SC」メソッドを使ったフィードバック──3SC編
◎Summarizeの効果
◎Suggestのポイント
◎Supportで伝えるべきこと
◎Commitで計画を現実に変える
◎上司は「監視者」ではなく「支援者」という発想
第3章 クセのある相手との対話の「仕込み」術
◎クセのある相手への対策
◎【ケース1】指示が適切に伝わらない場合──「誤解のない指示」を実現する技術
◎「QFB–3SC」メソッドに則した対策法
◎【ケース2】同じことを何度も質問してくる部下への自立を促す対話手法
◎「QFB–3SC」メソッドに則した対策法
◎【ケース3】部下が自分の考えを率直に伝えてこない場合──「声なき声」を引き出す技術
◎「QFB–3SC」メソッドに則した対策法
◎【ケース4】意見が出ない部下たちへの対処──「忖度の壁」を取り払う技術
◎「QFB–3SC」メソッドに則した対策法
◎【ケース5】指示通りに動かない部下との対話──「指示と工夫のバランス」を実現する
◎「QFB–3SC」メソッドに則した対策法
◎【ケース6】仕事の進捗が遅い──納期遅延を未然に防ぐ対話のアプローチ
◎「QFB–3SC」メソッドに則した対策法
◎【ケース7】ミスや危機感のなさがある──小さなミスを大きな成長へと変える対話術
◎「QFB–3SC」メソッドに則した対策法
◎【ケース8】自己中心的姿勢の改善──「チームの視点」を引き出す対話術
◎「QFB–3SC」メソッドに則した対策法
◎【ケース9】チャレンジ精神の育成──小さな成功体験から挑戦心を引き出す
◎「QFB–3SC」メソッドに則した対策法
第4章 部下に心穏やかにフィードバックする方法――BRIDGEワーク
◎言いたいことが言えないことに毎日イライラしているあなたへ
◎フィードバックがうまくいかない本当の理由
◎リーダーの「こうするべき」「こうあるべき」
◎部下の「こうするべき」「こうあるべき」
◎「べき論のぶつかり合い」からの脱却
◎「わからない」ことを受け入れる勇気
◎「わかろうとする姿勢」そのものが上司の仕事
◎「BRIDGEワーク」とは何か?
◎「BRIDGEワーク」の進め方
◎「BRIDGEワーク」がもたらす効果
◎【事例1】在宅勤務をめぐる不公平感に苛立つ営業課長の場合
◎「BRIDGEワーク」の実践
◎対話の実現
◎「BRIDGEワーク」実践プロセス
◎【事例2】時間管理が甘い部下に苛立つ企画課リーダーの場合
◎「BRIDGEワーク」の実践
◎対話の実現
◎「BRIDGEワーク」実践プロセス
◎【事例3】顧客対応で不安を見せる若手社員に苛立つサービス課長の場合
◎対話の実現
◎「BRIDGEワーク」実践プロセス
◎「BRIDGEワーク」でよくある質問と回答
◎支えるひと言は、指導以上に人を動かす
第5章 「言えない」が「言える」に変わる身体と心の「仕込み」術
◎優しいマネージャーほど陥る「フィードバック恐怖症」の正体
◎心が動揺するとき、あなたの身体はどうなっている?
◎身体が記憶する恐怖──「喉の締め付け」の正体
◎メンタルを鍛えるな、身体をハックせよ
◎身体をハックする3つのステップ
◎【ステップ①】身体の「姿勢」を変える──不安は「形」から消していく
◎【ステップ②】相手との「位置」を変える──対立から協働へ
◎【応用編】オンライン会議での「心理的な位置」の変え方
◎【ステップ③】心の中の「敵」を変える──問題こそが、倒すべき相手
◎行動を変え、感情をハックする――「C-A-R-E(ケア)」フレームワーク
◎あなたはもう、一人で悩まなくていい
◎身体と行動を変えることから心は変わっていく -
ベストセラー『働くあなたの快眠地図』『働く50代の快眠法則』に続く、日本一の睡眠コーチ・角谷リョウさんによる第3弾です。今回のテーマは「休養」。休養と睡眠は密接な関係にありますが、実は睡眠は「休養」にとって手段のひとつに過ぎません。「疲れたら寝る」だけでは疲労は取れません。では、どうすればよいか?→本書に答えあり

POSTED BY寺崎
View More休まない働き方から、
「とにかく頑張る」「疲れは美徳」──
休みを戦略的に取る時代へ――。
そんな価値観で走り続けてきた私たちは、
いま確実に限界を迎えています。
残業時間は減り、便利なツールは増えたのに、
なぜか疲労スコアは年々上昇。
週末に温泉へ行っても、マッサージを受けても、
月曜にはまたぐったり……。
そんな“疲労沼”から抜け出せない現代人に
本書は根本的な解決策を示します。
著者は、日本屈指の睡眠コーチとして、
16万人以上のビジネスパーソンを指導してきた疲労回復のプロ。
現場での豊富な指導経験と最新の科学的エビデンスを融合し、
「疲労を出す」→「休む」→「充電する」という
疲れを根本から取り去る3ステップを体系化しました。
「働き方改革」から「休み方改革」へ
残業削減、テレワーク導入、業務効率化──。
「働き方改革」はこの数年で大きく進みました。
しかし、肝心の“疲労”は減るどころか、
むしろ増えている人が多いのが現実です。
原因はシンプルです。
「働き方」だけを変えて、「休み方」は昔のままだから。
睡眠不足を無理やり補うためのエナジードリンク、
サウナやマッサージ、溜まり続ける情報と疲労……。
こうした“その場しのぎ”の休養では、
心身をゼロにリセットすることはできません。
本書が提案するのは、
3ステップで心身をリセットする“戦略的休養”という新しい習慣。
これは、単なるリラックス法ではなく、
アグレッシブに働いて、豊かな人生を手に入れる方法です。
人生100年時代。
まずは「正しい休み方」を身につけることから始めてみませんか。
もくじ
第1章 現代人を悩ませる「疲労」の正体
日本にようやく本物の「休養時代」が到来した
世に溢れる疲労回復は「疲労感」を取っているだけ
「疲労」にははっきりした「定義」や「種類」がない
実は疲労研究の先進国「お疲れ様の国ニッポン」
なぜ、疲労回復することがダイエットにつながるのか? など
第2章 まちがいだらけの「休み方」
なぜ、日本は働く時間が減っているのに「疲れている人」が増えているのか?
なぜ、温泉に行くと余計に疲れるのか?
なぜ、厚生労働省は「8時間以上寝ないよう」に警告するのか?
なぜ、日曜日をゆったり過ごすと月曜日の朝がしんどいのか?
なぜ、リカバリーウェアで逆に疲労が増す人がいるのか?
なぜ、サウナはスッキリするのに疲労が取れないのか? など
第3章 疲労をゼロにする「出す」「休む」「充電」の3ステップ
古いタンパク質が残っていると疲労は絶対に回復しない
じっと休んでいても疲労物質は出ていかない
疲労が溜まると部屋のゴミや情報のゴミも溜まる
「休む」前に「疲労やゴミ」を出す
意図して「完全に休む」を目指す
「疲労を出し」「完全に休んだ」あとに「充電する」で仕上げる など
第4章 ステップ➊疲労を出す――疲労・脳・胃腸・モノ・情報の「不要」を全部出す
第5章 ステップ➋完全に休む――徹底的に「休み切る」
第6章 ステップ➌充電する――出し切って休ませた心身を充電する
第7章 蓄積疲労をゼロにする週末リセット術
第8章 疲労を溜めない生活習慣
購入者限定無料特典
自分に足りない栄養素を簡単に調べる方法(動画)
完全回復の3つのステップの最後「充電する」フェーズにおいて、栄養素を充電するにあたって、
「自分に足りない栄養素」をどうやって把握するか、具体的な方法を解説します。
※無料特典は、お客様ご自身で別途お申し込みが必要です。
※無料特典は、サイト上で公開するものであり、小冊子・CD・DVDなどをお送りするものではございません。
※上記無料特典のご提供は予告なく終了となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
-
2012年初版のロングセラーの改訂版です。「独立したい」「起業したい」と考えるビジネスパーソンにとって頼れる実務指南書の決定版。最初の1冊としておすすめします。

POSTED BY寺崎
View More「独立したい!」と思ったら、まずはこの本から
本書は独立・起業を考えている人向けの入門書です。
初めて事業を立ち上げるとなると、
本来の業務だけでなく、
あなたがこれまで経験したことのない、
数多くの業務をこなさなければなりません。
経験したことのない業務を無難にこなすには、
事前の情報収集や学習、準備が欠かせません。
そのためには――
新規開業者向けのセミナーに参加したり、
起業した先輩の体験談を聞いてみるのもよいでしょう。
経験者の話を直接聞いて、ナマの情報が得られれば、
大いに参考になるかと思います。
もっとも、自分の身近に
起業経験者がいるケースは限られるし
人から聞く話はどうしても断片的な情報です。
そこで――
起業に必要な知識を網羅した本を読んで
起業とはどういうことで、何が必要になるのかといった
全体像を理解しておく必要があります。
そのために書かれたのが本書です。
独立・起業のための必要最低限な情報を
図解とともにほぼ網羅しました。
ぜひ、本書を片手に一国一条の主として
自由で豊かな未来を手に入れてください。
もくじ
第1章 はじめの一歩を踏み出す前に
1 ほんとうに独立・起業しますか?
2 起業する前にシミュレーションしよう
3 起業で成功する8つの資質とは?
4 いまやっている仕事で起業するなら?
5 資格や趣味を生かして起業するなら?
6 アイデアを形にして起業するなら?
7 フランチャイズで起業するなら?
8 独立・起業までの流れは?
9 在職中に準備することは?
10 円満退職するポイントは?
11 失業保険・社会保険はどうなる?
【コラム】頼れる専門家の相談相手をもとう
第2章 事業プランと資金計画の立て方
1 事業プランで検討することは?
2 事業コンセプトはどうする?
3 マーケット環境はどうか?
4 ターゲット客はどうする?
5 自社の強みをもつには?
6 経営プランを立てるには?
7 個人事業にするか、会社を設立するか?
8 資金計画を立てるには?
9 資金調達の方法には何がある?
10 日本政策金融公庫の融資制度とは?
11 自治体の制度融資とは?
12 助成金・補助金を利用するには?
【コラム】会社なら赤字を10年間もちこせる
第3章 開業に向けた具体的な準備
1 許認可が必要な事業か?
2 屋号・商号を決めるには?
3 印鑑はどんな種類が必要か?
4 印象的な名刺をつくるには?
5 パンフレット作成のポイントは?
6 ホームページをつくるには?
7 店舗・事務所を構えるには?
8 SOHOで始めるには?
9 設備・備品の準備はどうする?
10 金融機関とはどうつきあう?
11 運営のルールはどうする?
12 仕事のパートナーはどうする?
13 仕入先の確保と取引の仕方は?
【コラム】レンタルやリースを上手に利用する
第4章 独立1年目の売上アップ術
1 開業当初の営業はどうする?
2 売上を上げる・利益を増やすには?
3 マーケットを調査するには?
4 品揃えやサービスをよくするには?
5 効果的な広告・宣伝をするには?
6 顧客を増やすにはどうする?
7 インターネットを使った集客はどうする?
8 人脈や情報網を広げるには?
【コラム】経営セーフティ共済と小規模企業共済
第5章 個人事業はこうして始める
1 開業に必要な届出は?
2 個人事業の開業・廃業等届出書を出す
3 所得税の青色申告承認申請書を出す
4 家族従業員に給与を払うときに出す届出
5 従業員を雇ったときに出す届出
6 源泉所得税の納付を年2回にする届出
【コラム】事業が大きくなったら「法人成り」する
第6章 株式会社はこうしてつくる
1 会社の種類にはどんなものがあるか?
2 株式会社を設立する手順
3 定款を作成して認証を受ける
4 会社に出資する
5 会社の設立登記を申請する
6 税務署に届出をする
【コラム】設立登記の申請書類は慎重につくろう
第7章 従業員を雇うときの実務
1 従業員の募集の仕方は?
2 従業員を採用するときは?
3 労働保険に加入するには?
4 社会保険に加入するには?
5 給与計算はどうやる?
6 年末調整と源泉徴収票の作成は?
【コラム】労働基準法のあらましを知ろう
第8章 経理のやり方と節税ポイント
1 領収書や請求書の整理の仕方は?
2 毎日の経理はどうやる?
3 支払う税金はどうなっている?
4 消費税はどうなるか?
5 確定申告の手続きはどうする?
6 決算書を経営に生かすには?
7 個人事業の節税のポイントは?
8 株式会社の節税のポイントは?
【コラム】面倒な経理は会計ソフトで解決! -
「自分が買わない商品を売る仕事」View More
かんぽ営業マンが教える
口説きの手口
――かんぽ生命、入りませんか?
今から数年前、私は東海地方にある郵便局に勤務し、かんぽ生命の苛烈なノルマに追われながら仕事に勤しんだ。数十件におよぶ契約を獲得し、東海支社管内での「ルーキー賞」なる賞を受けた。
さらに在籍中、当時のかんぽ営業のあり方をいくつかのメディアに告発した。そういう意味では、かんぽ生命の不適切営業問題が表面化するきっかけを作った一人ともいえる。
かんぽ営業の裏も表も経験した1年あまりにおよぶ歳月はいい意味でも悪い意味でも濃密な時間だった。
私はかんぽ営業の現場で何を見て、何を考え、なぜ退職を決断したのか。
――本書に記すのは、すべて私がかんぽ営業の現場で体験したありのままの事実である。
もくじ
まえがき――かんぽ営業の裏も表も
第1章 かんぽ生命、入りませんか?
某月某日「正社員/金融部門」:リクナビエントリー
某月某日 配属先:〝ボテ〟が稼げる環境だから
某月某日 精鋭たち:中央郵政研修センターへ
某月某日 ボテ計算:研修で教わらなかったこと
某月某日 金融のプロとは?:私が考えるプロフェッショナル
某月某日 前代未聞:不合格になりました
某月某日 タランラップ:営業のコツ
第2章 かんぽ!かんぽ!かんぽ!
某月某日 銀行か、信用金庫か:世間知らずでピュアな大学生
某月某日 人生の分岐点:メガバンクを去る
某月某日 話が違う!:乗合保険代理店の実態
某月某日 お客さま本位の提案:メットライフ生命を推すワケ
某月某日 着任:誰もが欲しがる顧客リスト
某月某日 初荷:定額貯金360万円作成
某月某日 戦々恐々:人事異動の季節
某月某日 アポ取り:制度改正のご説明
某月某日 1000万超え:休憩できる場所
某月某日 直立不動:俺が言ったことはすぐにやれ!
某月某日 休日出勤:郵便局の謎ルール
某月某日 販売会議:噴火を免れる
某月某日 不告知教唆:超えてはならないライン
某月某日 復職:歯を食いしばってでも
某月某日 初訪契約:それ〝勝負〟?
某月某日 エース社員:「乗り換え契約」と「料済み契約」
第3章 ボテを稼ぐ日々
某月某日 10倍保障型養老保険:会社も私もオイシイ商品
某月某日 ミーハー気分:「クローズアップ現代」出演
某月某日 バーター取引:購読してくれない?
某月某日 脱落者:お荷物社員に居場所はない
某月某日 投資信託を売る:二足のわらじ
某月某日 不思議な口座:蒸し暑い夏の思い出
某月某日 営業したくないお客:いつでも来てちょうだい
某月某日 うまい棒とカップ麺:アメとムチ
某月某日 掘り出し物:自動車保険契約第1号
某月某日 がん保険:がんは2人に1人はかかる病気か?
某月某日 ツーカーの仲:院長を口説く
某月某日 掛けオーバー:再研修の地で
某月某日 あっちに行きたい:辞めてどうするんですか?
某月某日 横取り:ベストな形のご提案
某月某日 マイカー営業:ガソリン代は自腹やぞ
第4章 郵便局は変わらない
某月某日 営業停止処分:変わらない組織
某月某日 ネタ元:「週刊東洋経済」での告発
某月某日 ご褒美旅行:幹事、拝命しました
某月某日 感謝の言葉:タッコー定年
某月某日 ルーキー賞:新部長、就任
某月某日 さよなら郵便局:「せっかく大きな会社に入ったんでしょう?」
あとがき――終の棲家にて
【発行】三五館シンシャ/【発売】フォレスト出版 -
小学生のころから数十年間、「コミュニケーションは相手の立場に立って考えるべき」をずっと真理だと思って生きてきました。この本を編集するまでは……。本書は「相手の立場に立って考えるのはフェアじゃない」と語ります。いくらコチラが相手の立場に立っても、相手が自分の立場に立ってくれる保証はないから。だったら、「相手をコチラの立場に立たせる」ことを意識して言葉を選んだほうが、自分の思い通りのコミュニケーションができるというのが本書の主張です。「なるほど。相手を振り回す高圧的だったり、狡猾な言葉を使うんだな」と思われるかもしれませんが、本書で紹介するフレーズはすべて「やさしい言葉」であるところがミソなのです。

POSTED BYかばを
View More言葉を少し変えるだけで状況を一変
セールス担当者から「これ、すごくいい話ですよ!」と言われたら、どう感じますか。
おそらく多くの人は「うさんくさい」「怪しい」と身構えるでしょう。
では、「これ、悪い話じゃないと思いますよ」と言われたらどうでしょう。
「少なくとも損にはならなそうだ」「話だけでも聞いてみようかな」と思う人はいるはずです。
このように、ほんの少し言葉を変えるだけで、相手が受け取る印象は大きく変わります。
すなわち、もしあなたが愚直に営業しても売れない、部下に心を開いてもらえないといった悩みがあれば、もっといえば、他人に振り回されてばかり、いつも遠慮を強いられて自己主張できないなど、コミュニケーションに不満があったとしても、言葉を少し変えるだけで状況を一変させることができるということです。
本書ではこのような、自分が期待する方向に相手を動かすフレーズをまとめました。
脳をハックする仕組まれたフレーズ
「どっちがいいですか?」
「ちょっとだけ想像してもらえますか?」
「逆に、これをやらないとどうなると思います?」
「一緒にやったら早く終わりますよ」
一見、よく聞くし、使いもするフレーズですが、状況を間違わなければ、他人を自分の思い通りにコントロールする言葉になります。
おそらく、多くのフレーズを見て「え?こんな普通の言葉でいいの?」と感じるでしょう。
しかし、人はコントロールしたい、利用したいという願望が見え透いた言葉には動かされません。
大切なのは、自分を思ってくれている、自分に利益をもたらしてくれる――そう感じさせる「やさしい言葉」です。
たとえその奥に、支配欲やわずかな悪意が潜んでいたとしても……。
コミュ障「相手の立場に立って考えよう」
本書で紹介するフレーズすべてに、ある“仕掛け”が仕組まれています。
コミュ強「相手をコチラの立場に立たせよう」
それが〝相手を自分の立場に立たせる仕掛け〟です。
「相手の立場に立って考えなさい」とは、良好なコミュニケーションのための、疑いようもない真理と考えられています。
しかし、現実はどうでしょうか?
「相手の立場に立ちすぎた人」ほど損をしているのです。
「相手の気持ちを考えて遠慮した結果、断れずに搾取される」
「相手のわがままを優先して、自分の主張は飲み込んでしまう」
「強く言えず、押しの強い相手のペースに巻き込まれる」
「相手の立場に立って考える」姿勢をあなたが見せても、相手があなたの立場に立って考えてくれる保証は一切ありません。
したがって、「相手の立場に立つ」のではなく、「相手を自分の立場に立たせる」という戦略的会話術が必要とされるのです。
この発想はコミュニケーションにおいて邪道と見なされてきましたが、こちらが「相手の立場に立つ」ならば「相手もこちらの立場に立たせる」のがフェアというもの。
そうした意識で言葉を選ぶと、パワーバランスが対等になり自分を優位な立場に立たせやすくなります。
本書ではそのためのフレーズをまとめています。
本書の構成について
序章では、まわりに振り回される人生から抜け出すために、本書全体を貫く考え方を解説します。それは、相手を「感情タイプ」と「論理タイプ」に分けてとらえること、そして「相手の立場に立つ」のではなく、「相手を自分の場に引き込む」ことです。第1章以降で紹介するすべてのフレーズは、この考えを土台に練り上げられています。
第1章では、こちらの要望を受け入れてもらい、相手を説得するためのフレーズをまとめました。〝お願いをする側〟から、〝お願いを受け入れられる側〟へと立場を変えましょう。
第2章では、なかなか行動しない、思い通りに動いてくれない相手の背中を押したり、うまく誘導するフレーズを紹介します。うまく使えば、好感度を上げることさえ可能です。
第3章では、相手を指導・注意したり、その意見に反論するためのフレーズをまとめました。部下に気をつかいすぎて注意できない上司が増えている昨今、ぜひ武器として活用してください。
第4章では、Z世代とのコミュニケーションに役立つフレーズを紹介します。上の世代には理解しにくい彼らの価値観を踏まえ、円滑な対話を生むための考え方です。
目次
まえがき 非モテ・吃音・根暗な人間が見つけた相手を動かす言葉
序章 相手の立場に立つな!コチラの土俵に立たせろ!
第1章 自然と相手が納得してくれる依頼と説得のフレーズ
第2章 腰が重い相手が前向きに動き出す背中を押すフレーズ
第3章 厄介な相手を一瞬で止める注意と反論フレーズ
第4章 言葉にシビアなZ世代攻略のための鉄板フレーズ