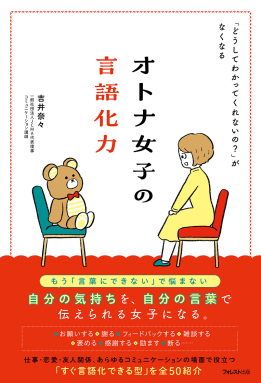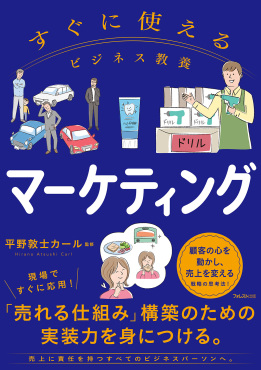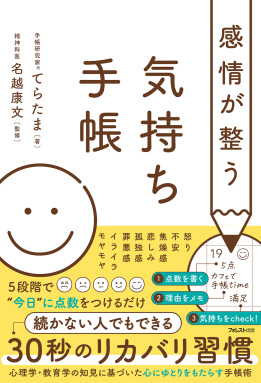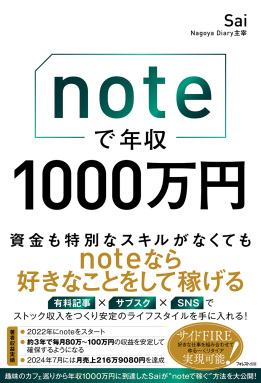著者の関連商品
著者の関連商品
-
「ちゃんと言いたいことがあったのに、言えなかった……。そもそも私のこの気持ちってどうやって言語化したらいいの?」、私自身うまく言葉にできなくて悩んだ経験が何度もありました。本書には、気持ちを整理するかんたんなワークと、仕事・恋愛・友人関係などいろんな場面で使える言い回しや“言語化の型”がたくさん載っています。きっと、読んだその日から使えるあなただけの言葉に出会えるはずです。言葉が変わると、少しだけ自分に自信が持てますし、人間関係の風通しもよくなると思います。「言葉にできない」で悩んでいるすべての女子に読んでほしい一冊です。

POSTED BY美馬
View More自分の気持ちを、自分の言葉で伝えられる
職場で言いたいことが言えなかったり、パートナーとすれ違ったり、SNSでは余計な誤解が生まれたり……。本書は、そんな日常で起きる上手に“言語化できない”を、ちょっとした言葉の選び方・組み合わせ方で解消する一冊です。
素敵なオトナ女子になれる本!
喉まで出かかっているのに上手く言葉にできない、そんなオトナ女子あるあるのモヤモヤした気持ちを整理するワークで感情の解像度を高めつつ、状況に応じて選べる言い回しや、仕事・家庭・恋愛・友人関係など幅広いコミュニケーションの場面で、そのまま使える会話テンプレを収録しています。
難しい理論は一切ありません! 使い慣れた言葉にさらに自分らしい“ひと言”を足すだけで、上手に言語化できるようになります。
仕事や恋愛、友人関係など、あらゆる場面でのコミュニケーションで役立つ「言語化の型」も全50掲載!◎依頼・お願いする◎謝る・非を認める◎評価・フィードバックする◎雑談・関係を構築する◎褒める・リスペクトを伝える◎感謝する・労う◎励ます・応援する◎断る・距離を取る……など。
本書の主要目次
第1章 人生をもっと楽しむために「言語化力」を磨こう
第2章 感情や思考をどんどん言葉にしてみよう
第3章 言葉の解像度アップ&バリエーションを増やそう
第4章 言語化した言葉で「伝える力」を高めよう
第5章 「型」に倣って言葉を組み合わせて使おう
第6章 自分だけの文章で言語化のアウトプットを楽しもう -
マーケティングという言葉には難しい印象を持つ方も多いかもしれません。しかし本書は、理論を“知る”だけでなく“使う”ための実践書です。「STP」「4P」といった定番のフレームワークから、AIやデジタル時代の最新動向までを一冊に凝縮。どのページから読んでも現場で役立つヒントが得られる構成にしました。マーケティングを「誰かの仕事」ではなく「自分ごと」として学びたい人に、最初の一冊としておすすめします。

POSTED BYかばを
View More偶然に見える出会いの裏に「仕組み」がある
朝、コンビニで新商品を手に取る。電車の広告にふと目を留める。
そんな“なんとなく”の行動も、実は綿密に設計されたマーケティングの一部です。
かつて企業の利益を追求するための手法とみなされていたマーケティングは、いまや生活をより便利に、社会をより豊かにする「社会的な技術」へと進化しました。
本書は、その仕組みをやさしく解き明かし、日常や仕事に活かせる形で再構成した一冊です。
マーケティングは、一部の専門家のためのものではなく、誰にとっても役立つ「思考の技術」。
企画、営業、プレゼン、交渉、SNS運用――あらゆる場面で応用できる知恵が詰まっています。
理論を“知る”だけで終わらせず、“使える力”へと変える――。
本書は、あなたの実践を後押しする、最初の一歩にふさわしい入門書です。
本書の構成
第1章では「マーケティングって何?」という根本から出発。「ニーズとウォンツの違い」「ベネフィットの捉え方」「デジタル化の意味」など、ビジネス教養として必ず押さえておきたい土台を整理します。
第2章では、「STP→4P」や「3C分析」「SWOT」「PPM」など、戦略立案に役立つフレームワークを体系的に学びます。基礎を固めながらも、実務ですぐ使える思考法を身につけられる構成です。
第3章では、企業がKGI(最終目標)を達成するための具体的戦略を紹介。「製品ライフサイクル」「LTV」「RFM分析」「フリー戦略」「CRM」など、マーケティングの“成果を出す”考え方を豊富な事例で解説しています。データと心理の両輪で顧客を理解する力を磨ける内容です。
第4章では、デジタルマーケティングの基礎をやさしく解説。「AISASモデル」や「トリプルメディア」「GA4」「ビッグデータ」「生成AI」など、急速に変化する現代の潮流を網羅します。単なる用語解説にとどまらず、実際にどう活用すれば成果につながるかを具体的に示しています。
第5章では、「ドン・キホーテ」「テスラ」「カンロ」「IKEA」「Netflix」「スターバックス」など、国内外の最新事例を分析。
「なぜヒットしたのか」「なぜ売れなかったのか」を行動経済学の視点も交えて解説し、実践的な洞察を得られます。
教科書では得られない“生きたマーケティング”の感覚を養うことができるでしょう。
目次
はじめに
第1章 マーケティングって何?
第2章 マーケティングの基本
第3章 企業のKGIを達成するためのマーケティング戦略
第4章 デジタルマーケティングの基本
第5章 マーケティングの実践例~成功例と失敗例 -
著者のてらたまさんは、幼少期から教師を志し、大学院では、発達心理学、教育心理学などを含む教育学を学んで来られた方。約10年間の教師生活を経て、第一子の出産・育児休業期間中に、これまでに感じたことのない“心の揺れ”や“感情の波”に直面されました。
詳細は本書に譲りますが、子育てと家事、ご主人の仕事のサポートと、驚くほどのタスクを抱え、「気持ちの置き場がない」と感じる日々があったそうです。そんな中で、少しずつ心を整える方法を模索し、誕生したのが「気持ち手帳」の手法です。
秋から冬にかけて、気持ちが落ち込みがちという方もいらっしゃると思います。この本をきっかけに、まずは1日30秒から、“自分の気持ちを見つめる時間”をつくってみてください。きっと、感情に振り回されない穏やかな自分、そして“ご機嫌の波”を自分で整えられる自分に出会えると思います。
POSTED BY時
View More感情を整える。続かない人でもできるたった30秒のリカバリ習慣
「最近、気持ちが不安定でイライラしやすい」
「モヤモヤが続いて、気分の切り替えがうまくできない」
「他人の機嫌や環境に左右されて、自分のペースが保てない」
「感情が爆発してしまい、あとで自己嫌悪に陥る」
そんな“感情の波”に悩む方におすすめしたいのが、
『感情が整う気持ち手帳』です。
本書で紹介するのは、毎日たった30秒でできる心の整え方。
やり方はとてもシンプル。
一日の終わりに“今日”を振り返って点数をつけ、
手帳やカレンダーに記録していくだけ。
この「気持ち手帳」を続けることで、
感情の浮き沈みを客観的に見つめられるようになり、
感情に振り回されにくくなっていきます。
実践した方からは、
「感情を整えるコツがつかめた」
「自己肯定感が高まり、毎日が少し楽になった」
「小さなことにイライラしなくなった」
といった声が多数寄せられています。
忙しい毎日でも、無理なくできるメンタルケア習慣。
自分のご機嫌を自分で整えたい方、心を穏やかに保ちたい方にぴったりの一冊です。
『感情が整う気持ち手帳』で、
“気分の波”に振り回されない自分へ。
今日から、心が軽くなる習慣をはじめてみませんか?
気になる本書の内容
本書の内容は以下のとおりです。
はじめに 感情が整う「気持ち手帳」をはじめよう
監修者解説〝なんとなく〟の感情に目を向けよう
Chapter1 たった30秒の習慣が起こす大きな変化
気持ちが整うしくみ
気持ちの変化に気づくことができる
自分の状態をシェアしやすくなり、人間関係が改善する
31事実と感情を分けて考えられるようになる
どうすればいいかがわかるようになる
自分の「ご機嫌パターン」がわかる
自分だけのモチベーションコントロール法がわかる
気持ちの対処方法を見つけやすい
気持ちを客観視できるようになる
〝大切なもの〟がわかり、より良い選択ができる
脳が活性化する
自己否定から抜け出せる
心地良い眠りにつながる
「変化を裏づける証拠」が見える
気持ちのセルフケアができる
「なんとなく不調」が減る
安心感をもたらす「日常ルーティン」ができる
Chapter2 感情が整う「気持ち手帳」3つのステップ
〝なんとなく〟の感情を放置しない
ステップ1 1日のおわりに「今日」を5段階で数値化する(5〜10秒)
ステップ2 点数の「理由」と「感情」をメモする(20秒前後)
ステップ3 1〜2カ月、記録を続けてみる
Chapter3 気持ちの波に名前をつけよう(感情のラベリング)
「怒り」にもいろんな種類がある
感情を表す語彙が増えるとコントロール力が上がる
感情に名前をつけることの科学的効果
感情ランキングをつくるワーク
Chapter4 「気持ち手帳」と仲良くなろう
5点の理由を知ろう
ご機嫌な時間(5点)を増やすアイデア
1点の理由を探ろう
不機嫌な時間(1点)を減らすアイデア
Chapter5 気持ちと体はつながっている
気持ちに影響を与える5つの要素
「ボディチェック欄」で気持ちとのつながりがわかる
体調と自己評価は結びつけなくていい
Chapter6 毎日をご機嫌にする3つのリスト
タスクに追われると不足感が増してしまう
リスト① ほめリスト
リスト② できたことリスト
リスト③ やりたいことリスト
Chapter7 毎日をブラッシュアップする+αのメモ&リスト
自分を「もっといいな」と思えるアイデア
Chapter8 ご機嫌な自分を育てるマインドセット
ネガティブは悪ではなく「メッセージ」
「なぜこんなに落ち込むの?」の答え
感情をひもとく「なぜなぜファイブ」
比較の気持ちにさよならする
Chapter9 感情マネジメントができる人になる
身近な人に伝染する「ご機嫌の波」
タスクに追われても「私はOK」といえる自分になる
余裕がある人は、感情にスペースがある人
怒りや焦りを「無視しない」スキル
他人の機嫌に振り回されない距離のとり方
Chapter10 継続のコツとつまずいたときの処方箋
継続のコツと、つまずいたときの処方箋
「3日坊主でもOK」な理由
書けないときは「思い出す」だけ
書けなかった日の翌日の対処法
思い出すのがつらいとき
ラクに習慣化できるたった1つの方法
続かない理由別アドバイス
〝自分なりの「気持ち手帳」スタイル〟を見つける
書けなかった日は、何かを頑張った日
おわりに〝なんとなく〟の感情とともに自分と向き合う -
顔がいい人を指す「イケメン」という言葉は、私が高校生の頃(90年代末頃)に生まれました。ただ、社会人になると、「容姿がいいイケメン」よりも、「精神的なイケメン」のほうが魅力的だと思うことが増えていきました。気遣いができ、人のために真剣に考え、行動したり、助けたり、時には自己犠牲もできる人。人間性や心の器が大きい人。 それが精神的なイケメン、『イケメンタル』です。
本書には「顔や容姿は変えられなくても、心なら変えられる」という言葉があります。つまり、精神的なイケメンは、心がけや習慣次第で誰でもなることができるということ。 ぜひ本書を通じて、人としてのカッコよさや良きあり方を身につけるきっかけにしていただきたいと思います。
POSTED BYシカラボ
View Moreメンタルは「弱いか強いか」ではなく
・なぜか人が自然と集まる。
「ダサいかカッコイイか」で決まる
・いろんな人から好かれ、信頼される。
・特別、顔や容姿がイケメンというわけでもないのに、異性からも同性からもモテる。
・自然と周りが協力してくれる。
あなたの近くに、そんな人はいないでしょうか?
そして、あなたもそのような人になりたくはありませんか。
その人たちは生まれつき人に好かれる才能を持っていたわけでも、
特別なコミュニケーションスキルを身につけているわけでもありません。
共通しているのは「メンタルがイケメン」ということです。
相手のことを思って行動できたり、人を助け、尽力したりすることを苦にしない。
愚痴や不満を言いふらさず、感情に振り回されず、他人に配慮でき、心が広く、必要なときには許す。
そんな精神的に余裕がある「メンタルがイケメンな人」は、
仕事でもプライベートでも人を惹きつけることができます。
この精神的なイケメンの人のことを「イケメンタル」と呼びます。
本書では、イケメンタルの人たちの思考法と行動習慣を、ビジネスや日常ですぐに活かせる形で紹介しています。
イケメンタルの大原則やマインド、観察力・想像力・ポジティブな捉え方、仕事や人との向き合い方、覚悟や責任感、許す力、自分を肯定する力など、イケメンタルになるための方法とスキルを具体的に解説しています。
顔や容姿を変えたいと思っても、それは簡単にはできません。
でも、「心(メンタル)」なら誰でも変えられます。
「イケメンタル=イケてるメンタル」を持つことは、
人間関係だけでなく、仕事や人生も驚くほど好転させる可能性を持っています。
「もっと人から好かれたり、評価されるようになりたい」
「仕事のできる人になり、人間関係もいい関係を作れる人になりたい」
「人としての魅力を高めたい、もっと成長したい」
「忙しい毎日でも余裕のある人になりたい」
「他人や周りに振り回されたくない」
そんな方にこそ読んでほしい一冊です。
100のスキルを学ぶよりも、たった1つのメンタルを磨くことで、
人生は大きく変えられるはずです。
この本を通じて、イケメンタルな人を目指してみてください。 -
FIREや投資の本は数多くありますが、どこか遠い世界の話に聞こえます。この本の魅力的な部分は、カフェ巡りや日常の発信といった“すぐに始められること”を収入に変える方を解説してくれている点。“年収1000万円”と書かれていると、一見ハードルが高そうに思えるかもしれません。けれど、“自分の生活がそのまま仕事になる”ことに気づけば、「私でもできるかも」ときっと思えてしまいます。好きなことをして生きるのは夢物語ではなく、仕組み化の問題。本書はその仕組みをゼロから教えてくれます。

POSTED BY美馬
View More資金も特別なスキルがなくても
いま注目を集めるプラットフォーム「note」は、自分の文章を誰でも手軽に発信できるサービスです。特別なスキルや知名度がなくても、コンテンツを通じて共感してくれる読者と出会うことができます。そして有料記事やマガジン、サブスクの仕組みを活用すれば、発信をそのまま収益に変えることができます。実際にnoteから安定した副収入を得ている人、さらには年収1000万円を超える人まで現れています。近頃話題のサイドFIRE(不労所得と副業などの収入を組み合わせて生活すること)も夢ではありません!
noteなら好きなことをして稼げる
本書は、そんなライフスタイルを手にするための方法を6つのステップにわけてまとめています。趣味のカフェ巡り情報の発信で、実際に年収1000万円を達成した著者自身の経験と、数々の成功事例をもとに「ゼロから始めても成果を出せる方法」を丁寧に解説しています。
具体的には、
・noteへの導線をつくるSNSの活用法
・読まれる、買われる記事の書き方
・サブスクを使った収益化の仕組みづくり
・読者を「フォロワー」から「ファン」に変えるコミュニティ運営術
・継続して発信を続けるためのマインドセット
といったテーマを、わかりやすく紹介しています。
「文章に自信がない」「特別な才能なんてない」と感じている人ほど、本書の内容は役立ちます。なぜなら、本書が伝えているのは普通の人が等身大の発信を続けることでファンを増やし、収益を積み上げていったリアルな方法だからです。
本業のかたわらで副収入を得たい人も、将来的に独立を考えている人も、まずはnoteを始めてみることをおすすめします。
本書の主要目次
STEP1 noteで年収1000万円を目指すには?
STEP2 好きなことをしているだけで稼げる仕組みをつくる
STEP3 収益を生むnote有料記事を書く
STEP4 サブスクリプション型サービスを展開する
STEP5 高価格サブスクリプション型サービスに挑戦する
STEP6 売上の拡大&安定を目指すための戦略