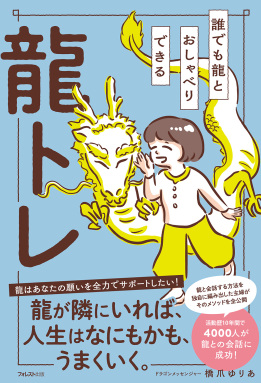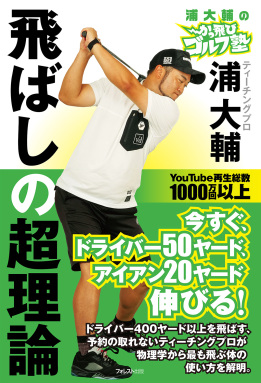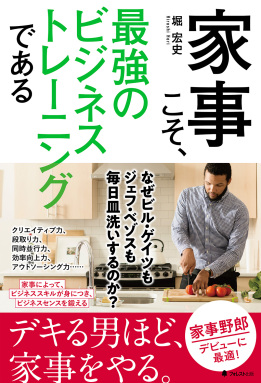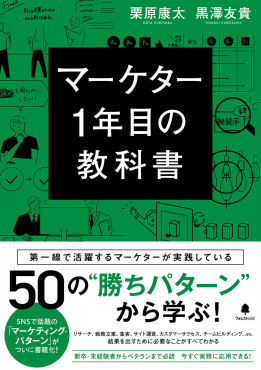著者の関連商品
著者の関連商品
-
著者の橋爪さんとは、ある出版コンペで出会いました。参加された著者候補の方々はみなさんとても魅力的だったのですが、普通の主婦だった方が、あることをきっかけに龍と話ができるようになり、そのやり方を4000人に教えている……という、なんだかとんでもないことをやっている事実にビックリ。しかも、これまで「龍と話す方法」が書かれた本なんてありません。「ぜひ、これはうちから出しましょう!」と。その後、トントン拍子でこうして本になりました。橋爪さんとの出会いから出版に至るまで、あれもこれも龍のおかげかもしれません。

POSTED BY寺崎
View More龍を「人生のサポーター」として味方につける
はじめまして。
橋爪ゆりあと申します。
私は犬と猫と旦那様と暮らしているごく普通の主婦です。
仕事は「ドラゴンメッセンジャー®」です。龍とともに毎日を自分らしくエキサイティングに暮らしたいと思っている方のサポートをしています。
「ドラゴンメッセンジャー? ちっとも普通の主婦なんかじゃない」
こう思った方もいらっしゃるかもしれませんね。
確かに、「龍とおしゃべりできる」とか、「龍からのメッセージが受け取れる」というと、サイキックな能力がある特別な人を連想するかもしれません。
実際に、龍にまつわる本を出されている方だったり、「龍のエネルギーを扱う」といったことが得意なスピリチュアル系のセラピストの方などは、幼い頃から何らかの目には見えない力をお持ちの方だったり、何かをきっかけに、スピリチュアル能力が開花したという方が多いように思います。
でも、私に関していえば、そういう特殊能力は一切ありません。
私も当初は龍の存在を信じていませんでした。ところが、サイキック能力の有無とはまったく関係なく、実は誰でも龍とコミュニケーションをとることはできるのです。
ちゃんとトレーニングをすることで、あなたも龍と話せるようになります。
人とコミュニケーションをとりたいと願っている龍、そして龍とともに生きたい人との縁結びをしたいと思って、私はこの本を書くことにしました。
龍とともに生きると、〝人生の質〟が変わる!
空を見上げて龍に見える雲を見たことはありませんか?
「龍と話すことができたら、いろいろと教えてもらえるのに」
こんな風に思ったことはないですか?
そんなことできるわけないと思っていますか?
龍とおしゃべりできるようになると、〝人生の質〞そのものが変わります。
知りたいことがあれば、ほとんど龍が教えてくれるようになります。あなたが望むなら、龍という最強のサポーターとともに、人生をすっかり思い通りにつくり替えることもできるのです。
著者が主宰する「ドラゴンメッセンジャー講座」累計4000人の受講生のうち、なんと約9割以上の方は龍から何らかのメッセージを受け取れるようになっています。
龍たちは、意思疎通ができる人が増えるのを望んでいます。また、人間とともに成長することが、龍にとっても成長の証であり、生きがいになるのです。
龍とコミュニケーションをとるようになって、人生がガラリと好転した人がたくさん生まれています。
ぜひ、あなたも試してみませんか?
本書の内容
はじめに「誰でも龍とおしゃべりできるんです」
第1章 「龍」ってどんな存在なの?
龍はどこにでもいる
龍が好む場所はどんなところ?
龍はどんな姿をしているの?
「龍はこんな感じ」という思い込みは手放そう
〝宇宙龍〞が地球に増えている
宇宙龍は断トツで仕事が速い!
「神さまの近くにいる龍」と「人間のそばにいる龍」
【コラム】私の不思議体験 〜龍とたまご〜
第2章 「龍」と一緒にいると、どんないいことがあるの?
龍は相棒であり友達
「龍がいるような気がする」からスタートする
私が龍をはじめて感じた不思議体験
龍からのメッセージの受け取り方は人それぞれ
〝3倍速〞で夢が叶い出す
龍の背に乗っているかのようにダイナミックに物事が進展する
想定外のワクワクする出来事がお膳立てされる
たくさんの龍とチームを組むこともある
夢やゴールに合わせてコンビを組む龍は変わる
「風の時代」の到来により、〝龍とおしゃべりできる人〞が望まれている
龍はなぜ人を助けるのか?
第3章 龍とおしゃべりするには「夢」の設定が鍵
龍はあなたの夢を叶えるために存在している
龍が一番困るのは「あなたに『夢』がないこと」
もし、夢を忘れてしまっているならば……
「うまくいかないこと」も龍のサポートの結果かもしれない
夢がたくさんある人を龍は大歓迎する
「子どもの幸せ」を願う夢があるときの注意点
夢の見つけ方「小さい頃に好きだったことは何?」
龍は〝お金〞の望みも叶えてくれる
パートナーがほしいなら、行動は必須!
困ったときは龍と戦略会議をしよう
龍はビジネスパートナーであり、優秀なコンサルタント
自分で決めることが大事
第4章 龍活トレーニング 龍とおしゃべりする方法【実践編】
誰でも龍とおしゃべりできるようになる「龍活トレーニング」
《STEP 1-1》龍と前進する「覚悟」を確認する
《STEP 1-2》龍にあなたの夢を伝えてゴールを設定する
わからないことはここで明確に。途中であきらめないで!
《STEP 1-3》夢を叶えるプロジェクト名と期限を決める
《STEP 2-1》あなたのそばにいる龍をイメージしてみる
《STEP 2-2》あなたの龍に会ってみる
もう一度、龍と一緒にあなたの夢を確認する
あなたの龍にニックネームを付けよう
龍の気配、エネルギーを感じてみよう
さらに龍と仲良くなるコツ「龍に毎日挨拶しよう」
《STEP 2-3》龍とのコミュニケーションを深める
第5章 龍活トレーニング 龍とおしゃべりする方法【体と心編】
自分軸を整えよう
《実践ワーク》センタリング&グラウンディング
《実践ワーク》龍と一緒にオーラの浄化・調整をやってみよう
《実践ワーク》龍と一緒にチャクラの浄化・調整をやってみよう
「睡眠・食事・運動」で肉体を大事にしよう
不要なものは思い切って手放そう
第6章 龍トレ体験談
おわりに 風の時代を龍と一緒に前身しよう!
購入者限定無料プレゼント
本書をお読みくださったみなさんに、スペシャル動画をプレゼント!
4000人を指導した日本一のドラゴンメッセンジャーである著者が龍からこっそり聞いたひそひそ話を初公開!
※読者のみなさんだけにお伝えします。
龍に聞いてみた!!シリーズ
その1 夢を叶えるために必要なお金を「宇宙銀行」から引き出す方法
その2 あなたの行動をブロックしている○○を龍に頼んで手放す方法
その3 あなたの前世を龍と旅する「前世ツアー」の方法
※無料プレゼントは、お客様ご自身で別途お申し込みが必要です。
※無料プレゼントは、サイト上で公開するものであり、
CD・DVDなどをお送りするものではございません。
※上記無料プレゼントのご提供は予告なく終了となる場合がございます。
あらかじめご了承ください。
-
ビジネスパーソンにとってメジャーなスポーツであるゴルフ。弊社の営業マンから、「すごいティーチングプロがYouTubeで大人気。この人の理論をぜひまとめてほしい」ということで生まれた企画です。実際に400ヤード以上飛ばす彼のスイングを見た私は正直、度肝を抜かれました。しかも、彼の生徒さんは普通に300ヤードを超えるというのです。その秘密は、クラブという道具で飛ばす物理学的な理論に裏打ちされたもので、これまでのゴルフ本の常識を一瞬で吹っ飛ばすものです。読むだけでも飛距離が30ヤード伸びるのではないでしょうか。ぜひお試しください。

POSTED BY稲川
View More400ヤード以上飛ばす、予約の取れないティーチングプロの常識を覆す理論
今、YouTubeで大人気の「かっ飛びゴルフ塾」の浦大輔氏が、グリップ・アドレス・スイングまでの流れをまとめた、誰でも300ヤードを飛ばせる理論を開陳。
現在、日本一高額にもかかわらず予約が取れないティーチングプロとして人気がうなぎ登り。プロテスト合格者も輩出する著者が、これまでのゴルフ理論の常識を覆します。
「はじめに」で著者はこう述べています。
『当時、日本に出回っていたゴルフ理論で「セオリー」と言われている事柄の中にも、多くの「ウソ」があることがよくわかりました。「ウソ」ではないにしろ、「勘違い」あるいは、「説明の足りないこと」「条件によって、人によって変わること」があるのもよくわかってきました。
そして、論理的に正しいものだけで組み立てた、ゴルフスイングの本当のベースとなる「だれにでも当てはまる、本当にやらなくてはいけないこと」を独自にまとめあげました。
クラブの正しい使い方、体の正しい使い方だけを抽出して、組み立てた理論です。
(中略)
「これで間違いない」というこの理論の核ができあがったので、それで勝負しようと上京し、ゴルフスタジオを始めました。教え始めて、「300ヤード程度」なら多くの人にも飛ばせるようになるという手応えを得ました。そんな飛距離を出せるのは、物理的、体の構造的にも正しい動きだからであり、だからこそケガなども起こさず、再現性も高いので必然的にスコアも良くなる。
ということで、クラブをはじめて握って、2年経たずに70台のスコアを出している生徒もいます。
(中略)
まあ、読んだだけだと30ヤードくらいしか伸びないかもしれません。でもそこから練習して、自分なりの感覚をつかんだり、自分なりの調整を加えていけば、さらにもっともっと伸ばしていけます。それを実現した、たくさんの生徒さんたちは、本当にうれしそうです。ゴルフが今まで以上に楽しくなっているからです。
多くの人が、著者の飛ばしの理論で飛距離を劇的に伸ばしています。それは老若男女関係なし。ゴルフ理論の流行に惑わされてきたあなたにも、夢の300ヤードが待っています。
300ヤードも夢じゃない。あなたもドライバーで50ヤード以上伸ばすことができる!
これまでの常識を覆す、誰でも300ヤード飛ばせる理論とは何でしょうか。
実は、ゴルフ道具はどんどん進化しています。しかし、多くの人がそれを活かしていません。そこで著者は、物理学的な見地からあらゆる研究をして飛ばす理論を構築しました。
あくまでも一端ですが、おそらくこれまでとはまったく違う考え方のはずです。
・「これからつくる大きな衝撃」に備える意識をもつこと
・衝撃に備えるための力の使い方を考える
・グリップの基本コンセプトは指先を使って「つまむ」
・グリッププレッシャーは強いまま一定にする
・足からではなく手からアドレスは決まっていく
・体重配分は左右で5対5か4対6前後ではつま先に乗る
・加速のための助走はバックスイングから始める
・つま先体重キープのための「左サイドの押し」
・前傾角度はインパクトまでキープ
・切り返しのタイミングは切り返す前にある
・インパクト以降はすでにすべて「終わっている」・・・など。
グリップ・アドレス・スイングから飛距離を伸ばす練習法まで全75項目。
この本を手に練習すれば、ドライバーで50ヤード、アイアンで20ヤード伸ばせるのは間違いなし。
300ヤードも夢ではありません。
目次
第1章 300ヤード飛ばす前提をつくる
飛ばすスイングをつくる前に本気で飛ばす意識をもつ
①「これからつくる大きな衝撃」に備える意識をもつことから始まる
② スイングの途中に「インパクト=衝撃」がある
③ インパクトで起きる衝撃の大きさと方向を意識する
④ 2種類の衝撃はつまり飛距離と方向性を決めている
⑤ 衝撃に備えるための力の使い方を考える
⑥ 脳を安心させるから、限界まで速く振れる
【コラム1】スイングづくりにおいて本当に大切なこと
第2章 300ヤード飛ばすグリップをつくる
強い衝撃を受けても揺るがない。グリップは「つまむ」がベース
① 手のひらを使うのは大きな間違いである
② グリップの基本コンセプトは指先を使って「つまむ」
③ 左手グリップのつくり方「4本の指先ではさむ」
④ 左手グリップの仕上げ方「親指で上からはさむ」
⑤ 右手のグリップのつくり方「2本指の間のV字をあてがう」
⑥ 右手は「グリップ」というより「V字で支える」だけでいい
⑦ クラブと腕の角度を左手の力でキープする
⑧ グリップのつまみ方は目的ごとに変わる
⑨ 飛ばすクラブはショートサムで腕とクラブの角度をつくる
⑩ 両手のひらの向きに決まりは一切ない
⑪ 両手の間隔は狭く。でもインターロッキングは勧めない
⑫ グリップは「ソフト」ではなく「しっかりはさんで」支える
⑬ グリッププレッシャーは強いまま一定にする
⑭ フェースの向きがスクエアなら手の甲の向きはどうでもいい
⑮ ボールの捕まりが悪いならストロンググリップを試す
【コラム2】理論に「合う・合わない」はあり得ない!
第3章 300ヤード飛ばすアドレスをつくる
強い衝撃を跳ね返すくらい全身の力を使い切るための構え
① アドレスはインパクトのイメージからつくられる
② アドレスの目的のひとつ目はアラインメント(方向)どり
③ アドレスの目的のふたつ目は力を出す際の基準点の確認
④ ボールのどこを叩くかのイメージをもっておく
⑤ クラブのポジションに対してグリップの位置が決まる
⑥ 足からではなく手からアドレスは決まっていく
⑦ 骨盤を前に倒しておくと回転中の起き上がりを防げる
⑧ 背中の上だけ少し丸めるのがゴルフに適した姿勢
⑨ 背中は丸めるけれど腰は丸めてはいけない
⑩ 捻転の大きさ(深さ)でエネルギーを増す
⑪ 足先の向きで、体の回り具合が変わる
⑫ 最大の力を出せる足の幅は、日によって違う
⑬ ボールの位置も人それぞれ、日によっても変わる
⑭ 体重配分は左右で5対5か4対6前後ではつま先に乗る
⑮ アドレスの仕上げはヘッドを浮かせたワッグル
【コラム3】細かな動きを取り入れる際の注意点
第4章 300ヤード飛ばすスイングをつくる
自分のもてる力を出し切って飛距離を伸ばす振り方を理解しよう
① 動き出す前にもう一度「衝撃に備える」を考える
② スイングの全体像=「全体の円の形」をイメージする
③「全体の円」を大きくし楕円にして助走距離を稼ぐ
④ 加速のための助走はバックスイングから始める
⑤ バックスイングの重さを切り返しでしっかり受け止める
⑥ 手に持ったボールを地面に叩きつけるための位置を探す
⑦ 自分で「最強」の動き・形を見つけることがスイングづくり
⑧ 衝撃のイメージから動きをつくっていく
⑨ 理想の「スタンバイ状態」をワッグルで仕上げておく
⑩ グリッププレッシャーはワッグルからずっと変えない
⑪ 始動の動きは「真っすぐ」。でも、左腰も同時に動き出す
⑫ 全体の円のサイズは始動直後に決まる
⑬ つま先体重キープのための「左サイドの押し」
⑭ リーディングエッジは腰の高さで前傾角と平行
⑮ 手は胸の前から外さないでトップをつくる
⑯ 切り返しでヘッド自身が加速しながら下りてくる
⑰ 腰の高さより上でヘッドを加速する
⑱ 前傾角度はインパクトまでキープ
⑲ 全員に当てはまる要素はここまで。あとは個別対応部分
【コラム4】右足の蹴りについてのもうひとつの答え
第5章 300ヤード飛ばす練習法に取り組む
インパクトの衝撃を大きくするための技術と体のトレーニング
① 飛距離を伸ばすために① 体の右側で音を鳴らす
② 飛距離を伸ばすために② つま先立ちで電車に乗る
③ 飛距離を伸ばすために③ 布団叩きで布団を叩く
④ 飛距離を伸ばすために④ グリップを潰す
⑤ 練習場の使い方① スイングづくりについて
⑥ 練習場の使い方② 練習場での練習について
⑦ 練習場の使い方③ 右足で立って打つ
⑧ 練習場の使い方④ ティーアップしたボールをアイアンで打つ
⑨ 練習のテーマ案① 曲げて曲げて曲げまくる
⑩ 練習のテーマ案② もっと飛ばす、もっと飛ばさない
⑪ とにかく練習場では遊べ
⑫ スイングづくりは9番アイアン
【コラム5】「自分の100「%を知る」ことの大切さ
第6章 300ヤード飛ばす発想を育む
飛ばしのスイングの試行錯誤の中でヒントにしてほしいこと
① 切り返しでの「重さ」を支えるのは、全身
② 切り返しのタイミングは切り返す前にある
③ 切り返しの直前に最大の力を注ぎ込む
④ インパクト以降はすでにすべて「終わっている」
⑤ インパクトゾーンでのフェースの動きについての意識
⑥「f=ma」というお話もしてみましょう
⑦ 大きな筋肉だけでなく、全身使い尽くしましょう!
⑧ トッププロが細かなことをしている理由
おわりに ゴルフ理論の流行に惑わされてきたあなたへ
-
「自社のサービスをサブスクリプションにしたい」という要望を持つ方も多いことでしょう。しかしながら、世にあるサブスク指南書は大企業の事例を中心に概念的なビジネスモデルの解説に終始しています。そこで本書は徹底的に「現場目線」にこだわり、いますぐ実践できる点にこだわりました。中小企業向けの初のサブスク実践書です。

POSTED BY寺崎
View Moreスモールカンパニーのサブスク事業ノウハウを凝縮!
サブスクリプションサービスの国内市場規模は、2020年度には前年度比28.3%増の8759億6000万円に到達。2023年度には1兆1490億円まで成長すると予想されています(矢野経済研究所調べ)。
サブスクリプションが注目されたのはアドビ、マイクロソフトといったSaaS系ビジネスが発端でしたが、今ではありとあらゆる商品・サービスのサブスク化が進んでいます。
市場拡大とともにサブスクリプション関連の書籍が数多く登場しています。
ところが、残念なことに、中小規模の事業者にスポットを当てたものはほとんど見当たりません。大企業の事例分析にとどまるものが多く、中小規模の事業者が取るべきサブスクリプションの戦略や戦術を伝えるものは皆無に等しいのが現状です。
そこで、自らのビジネスもサブスクリプション型を採用しており、数多くの中小事業者のサブスクリプション支援に尽力した著者が、徹底的な「現場視点」で捉えた中小企業が本当に使えるサブスクビジネスの実践ノウハウをまとめました。
いままさに急成長を遂げるサブスクリプションの世界では、中小規模の事業者が次々と参入し、大きな成功をつかんでいます。その具体的な事例も詰め込みました。
著者がビジネスの立ち上げで経験したこと、顧客であるさまざまな事業者との関わりを通して学んだ実践的な知識を1冊に凝縮しました。サブスクリプションを基本から学べる、まさに教科書と呼べるバイブルです。
本書の内容
第1章 「所有」から「所属と体験」の時代へ
1 サブスクリプションの時代が来た
「古くて新しい」サブスクリプション/大企業の英断が転換点……
2 モノの「所有」よりも「体験」が価値となる
サブスクリプションは一過性のブームなのか?……
3 「所属」と「体験」を求める人々
オンラインサロンが人々を惹きつける理由……
4 サブスクリプションの民主化が企業を救う
市場の景色を変えた「既存ビジネスのサブスク化」……
5 迫られるデジタルシフト
国の支援も続々。今こそ波に乗れ! /D2Cとサブスクリプション……
第2章 サブスクリプションの基礎知識
1 サブスクリプションを始めるべき理由
オンライン市場なら、個人でもニッチなサービスが通用する……
2 サブスクリプションを始めるキホンの「キ」
「1:5の法則」と「5:25の法則」/キーワードは「習慣化」……
3 サブスクリプションのサービス設計
フロー型ビジネスとの決定的な違い/5年先を見通せる魔法の数字「LTV」……
4 さあ、サブスク化の下準備を整えよう
限界費用とサブスク化 /サブスクリプションを構成する6要素……
5 消費者の心をつかむサブスクリプション
固定費の壁。ライバルは電気代 / 心理学で消費者のツボを押さえる……
第3章 サブスクリプション事業者になるための実践ステップ
1 成功に向けたマインドセット
LTVを最大限に活用する方法/サブスクリプションの成長ステップとKPI……
2 「必要ムダ」のサポート力
解約しやすい顧客層は? 消費者の不安を見逃すな!……
3 生命線は「契約管理の自動化」
メディアが伝えないサブスクリプションの難しさは現場にある
4 サブスクリプションのアイデアとテクニック
サブスクリプションアイデア8つの種/サブスク化のトリプル理論……
第4章 サブスクリプション成功のフレームワーク
1 人はどうして解約を選ぶのか
ストレスと満足度の関係/顧客満足度を維持する黄金ルール……
2 サブスクリプションの落とし穴
グラフで体感する解約率のインパクト……
3 サブスクリプション完全攻略法 ① サービス設計編
4 サブスクリプション完全攻略法 ② 組織マネジメント編
5 サブスクリプション完全攻略法 ③ 解約率を圧倒的に下げる仕組み編
第5章 サブスクリプションの事例集
Case Study1 ゴルフレッスンプロMISATO
Case Study2 ナノバブルサーバーSUIREX5
Case Study3 経世史論
Case Study4 ヘアモデルバンク
Case Study5 アカ凸(あかとつ)
Case Study6 臨床心理学総合アカデミア ポルトクオーレ
Case Study7 一般社団法人 終活協議会
Case Study8 KEN YAMAMOTO TECHNIQUE ONLINE
読者特典について
読者限定で2大特典をご用意!
特典①
サブスクリプションビジネス
収益シミュレーションシート(著者独自システムSUBSCTOOLS)
特典②
サブスクリプションビジネス
収益シミュレーションシート解説(PDF)

【SUBSCTOOLSでできること】
◎LTV(顧客生涯価値)を自動計算!
◎収益予測をグラフで視覚化!
◎解約率と獲得コストの関係をバッチリ把握して即改善!
◎広告費のレバレッジ効果を体感!
※無料プレゼントは、お客様ご自身で別途お申し込みが必要です。
※無料プレゼントは、サイト上で公開するものであり、
冊子などをお送りするものではございません。
※上記無料プレゼントのご提供は予告なく終了となる場合がございます。
あらかじめご了承ください。 -
物心がついた頃、母が料理、掃除、片付け、洗濯などを同時進行的にこなしている姿を見て、子どもながらに「段取り力」のすごさに驚いた記憶があります。考えてからやらないと終わらないんだろうな、と。子供のお手伝いレベルではわかりませんでしたが、学生時代にアルバイト、いわゆる「仕事」をするようになって、仕事における段取り力は最低限の必須スキルであることを実感しました。書籍編集者になってからも、いつか家事スキルとビジネススキルの共通点を企画にできたらとずっと思っていました。そんななか、家事スキルとビジネススキルの関係性を体系化され、見事に言語化されていた堀さんに出会い、ついに実現しました。やはり家事スキルが高い人は、仕事のスキルも高い。それをあらためて実感する1冊になりました。

POSTED BY森上
View Moreなぜビル・ゲイツは、毎日皿洗いをするのか?
突然ですが、
世界のビジネスエリートたちがやっている
家事でビジネススキルを鍛える方法
「ビル・ゲイツは、毎日家で皿洗いをしている
という話をご存じでしょうか?
グローバルエリートの頂点に立つ彼なら、
家事代行業者に任せ、
仕事に集中しているイメージがあるでしょう。
でも、彼は毎日皿洗いに精を出している。
そこには、家事に隠された大きなメリットがあるからです。
そのメリットとは、
「脳のアクティブレスト」です。
つまり、
仕事脳になっている自分の脳を
家事に集中することで
リフレッシュさせ、
新たな「ひらめき」「アイデア
が湧き上がる――。
そんな脳のルーティンに
家事を取り入れているのです。
世界中のビジネスエリートたちは、
家事は「やらされる」ものではなく、
積極的にやることで自らの仕事力を鍛えている。
広告の仕事を通じて
多くのグローバルエリートと渡り歩いてきた著者は
その事実に気づき、
家事における脳のリラックス以外のメリットを次々と発見し、
「ビジ家事」理論として体系化。
その理論に基づいた
ビジネストレーニング方法をまとめたのが本書です。
「ビジョニング力」「段取り力」「分析力」
「調整力」「スケジューリング力」「同時並行力」
「効率向上力」「コストコントロール力」「チーム運営力」
「アウトソーシング力」「プロジェクト力」「コミット力」
など、
ビジネスで求められるスキルを
具体的な家事を通じて鍛える方法を解説しています。
「家事」と「ビジネススキル」。
一見、不思議なこの組み合わせから見いだされた
「ビジ家事」理論をマスターすれば、
仕事もプライベートもより良い方向に導いてくれます。
「家事は大人の必須スキル」といわれる時代です。
今まで家事にストレスを感じていた
ビジネスパーソンはもちろん、
家事に積極的に参加できていなかった人が
「家事野郎」デビューするのに最適な1冊です。
気になる本書の内容
本書の内容は以下のとおりです。
はじめに――なぜ仕事ができる人ほど、家事をやるのか?
序 章 「ビジ家事」がもたらす11のメリット
ビジ家事野郎の誕生!
第1部 家事であなたの「仕事力」が向上する
【ビジネストレーニング①】ビジョニング力
「部屋が片付かない」が一気に解消する簡単な方法
理想の部屋を「ビジョニング」する
ビジョンを「プラニング」する
【ビジネストレーニング②】分析力
あなたの家事の「ボトルネック」はどこにあるのか?
一日の家事を「見える化」する
ボトルネックは、見直しのチャンス
家事の「解像度」を高める
【ビジネストレーニング③】スケジューリング力
家事のスケジュールを、朝・昼・夜でざっくり洗い出す
朝は「仕事の準備」をファーストプライオリティに
昼は「ながら家事」のチャンス
夜は「時短家事」で自分の時間を確保する
【ビジネストレーニング④】段取り力
家事も「段取り」! プランなしは逆効果
「段取り八分、仕上げ二分」を意識
プロのシェフに学んだ、皿洗いの「下ごしらえ」
【ビジネストレーニング⑤】マルチタスク力
料理のレシピには「その料理のこと」しか書いていない
事前のシミュレーションでマルチタスクに備えよう
動きは最小限に、事前の準備であわてない
PDCAでマルチタスクをブラッシュアップ
【ビジネストレーニング⑥】調整力
家事の「落としどころ」は、どこにある?
「今日の夕飯何にしようか?」に大きな地雷原が隠されている
「家事ミーティング」で、お互いの落としどころを探れ
【ビジネストレーニング⑦】習慣化力
モーニングルーティンと家事の関係とは?
自分の「家事スイッチ」を自動で入れる
あなたの「モーニング家事ルーティン」をつくろう
モーニングルーティンは気軽に見直そう
第2部 家事がやりたくなる「ビジ家事」理論
【ビジ家事理論──基本篇】「すぐ家事」理論
何もやりたくない……、そんなときは「ビジ家事」だ
家事はいつやるの? 「今」でしょ!
考えるな! 自分はロボットだと思い込む
鍛えるべきは、家事の「反射神経」
【ビジ家事理論──基本篇】「ゆる家事」理論
私たちは「ていねいな生活」で苦しんでいる
今こそ「ゆるい生活」にシフトしよう
どうしたらもっと家事が楽になるのか?
「やらないよりやったほうがマシ」という思考
【ビジ家事理論──基本篇】「単純家事」理論
あなたの「モード」を切り替えるのは、「単純作業」
洗濯物をたたんで、後悔する人はいない
単純作業が、マインドフルネスをもたらす
【ビジ家事理論──基本篇】「家事タスク分解」理論
洗濯の「どのパート」が好きですか?
家事の「タスク分解」が成功への近道
行き過ぎた役割分担は逆効果
朝食の準備も、タスク分解
【ビジ家事理論──基本篇】「楽家事」理論
その行動、果たして合理的な判断?
「お得」より「楽」を選ぶべき理由とは?
ネット通販比較も「ある程度」に
「楽」なビジ家事で長期的なお得を目指す
【ビジ家事理論──お掃除・片付け篇】「角そろえ」理論
そんなに散らかっていないのに、なぜか部屋がキレイに見えない原因
部屋の中の「角」をそろえる効用
目に見える情報を減らして、脳のストレスを減らす
母親から学んだ「角そろえ」の極意
角は「ちょこちょこ」そろえていく
【ビジ家事理論──お掃除・片付け篇】「掃除ロボット化」理論
「アクショントリガー」で、掃除をスタートする
さらに(本当の)掃除ロボットも導入してみよう
掃除ロボットとの連携で、効果倍増
自分を掃除ロボット化して「何も考えない幸せ」を感じる
【ビジ家事理論──お掃除・片付け篇】「ルール化」理論
「計画は実行されない」というリアルな現実
「ルール化」で甘えた自分をコントロール
モノ捨ての先延ばしはしない
毎日1%の影響力
【ビジ家事理論──お掃除・片付け篇】「ゴミ出しリラクゼーション」理論
ゴミ出しを最高のリラクゼーションに変える
ビジネスにおいて、ストレスフルな状況は最高のチャンス
「心の中のゴミ」も一緒に外に捨てちゃおう
【ビジ家事理論──お掃除・片付け篇】「風呂掃除リラクゼーション」理論
お風呂掃除をリラクゼーションに変えられる?
ポイントは、「お風呂から出たらすぐ洗う」
「スッキリした!」という魔法のひと言
思考の切り替えで、家事をデトックスにする
【ビジ家事理論──お掃除・片付け篇】「家事ワイン」理論
アイロンがけは、いつやるか?
「ワインを片手にアイロンがけ」をして気がついたこと
「ながら家事」がイヤな家事を楽しい家事に変える
「ながら作業」が家事の幅を広げる
【ビジ家事理論──キッチン篇】「キッチンコックピット」理論
家事のプロから学んだ「キッチンコックピット理論」
引っ越しの際に教えてもらったコックピット理論
「使うものだけを使う場所に」がコックピットの基本
コックピット理論で料理用具を配置してみよう
あなたのコックピットは、どんなコックピット?
【ビジ家事理論──キッチン篇】「ホームレストラン」理論
献立がストレスになる原因
解決のヒントは「レストランのメニュー」にアリ
あなたの「家メニュー」を作ってみよう
「家というレストラン」をどうマネジメントしていくか?
【ビジ家事理論──キッチン篇】「ブレックファーストフォーマット」理論
朝食はフォーマット化が正解
準備開始から後片付けまでつながるルーティン
フォーマット化で、気持ちが楽になっていく
【ビジ家事理論──キッチン篇】「ゼロ秒家事」理論
食後のひと息が、大きなロスにつながる
自分を皿洗いロボット化すれば大丈夫
皿洗いにも、アート感覚を
「ゼロ秒家事」を連続させる
仕事も溜めずに、「ゼロ秒処理」が原則
【ビジ家事理論──通販・デリバリー篇】「通販エコシステム」理論
日々の買い物を楽にする「エコシステム」
ネットスーパーで食材を買ってみませんか?
自動的に足りないものが家に届くシステム
【ビジ家事理論──通販・デリバリー篇】「通販プロセス管理」理論
「通販の受け取り」は、意外なストレス
ストレスを未然に防ぐ方法
商品を受け取ってからのハードル
フリマアプリでプロセスの「出口」をつくる
【ビジ家事理論──通販・デリバリー篇】「デリバリー家事」理論
クリーニングは、地味に時間が奪われる
クリーニングも、デリバリー活用
「クリーニング+保管」で、さらに便利に
地味にめんどうなタスクほど、アウトソーシング
【ビジ家事理論──ファミリー篇】「子ども家事」理論
子どもと一緒にビジ家事しよう
子ども家事は、「掃除・片付け」から始めよう
料理の手伝いで、「やりとげる力」を伸ばす
部下の育成は、マネージャーの責任
【ビジ家事理論──ファミリー篇】「旅家事」理論
ルーティン疲れを感じたら、旅に出よう
旅が「ビジ家事のPDCA」を進化させる
旅で見つける新しい家事のアプローチ
とりあえず旅の予定を入れてしまう
【ビジ家事理論──継続篇】「家事アウトソーソング」理論
やりたくないことは、やらなくていい
家事の最適配分をマネジメント
お互い苦手な家事は、アウトソーシングへ
あなたは、家事のプロデューサーです
【ビジ家事理論──継続篇】「プラスジョイ」理論
あなたが家事を習慣化できない3つの理由
習慣化に向けて、プラスジョイを意識する
家事の合間の「ごほうびタイム」を忘れずに
【ビジ家事理論──継続篇】「家事キャラ」理論
家事がうまくいかない理由は、あなたの「キャラ」?
役割キャラと習慣キャラをうまく使い分けよう
家事ができないのは、実は思い込みだった?
「家事メンキャラ」で、まわりとの関係を変えていこう
おわりに
-
フレームワークや理論、あるいは成功者の証言など、マーケティングを学ぶための情報は世の中にあふれています。しかし、自分が手がけている仕事にどう当てはめたらよいのか、あるいは今自分がいる組織においてどう活用すればよいのかわからないという方が大半なのではないでしょうか。本書では、さまざまな現場の実務で実際に使われ、さらに成果をあげている思考&行動パターンを抽出し、実践者のインタビューとともに解説しています。それを読むと、マーケティングで成果を出すためには、センス、才能が必要なのではなく、日々の地道な基本行動の繰り返しであることがわかります。本書で紹介されている思考&行動パターンは、マーケターのみならず、「自社の商品(モノ、サービス)を売るためにどうしたらいいのか?」を常に模索しているすべてのビジネスパーソンにとって有益だと思います。私自身も参考になる部分が多く、今後の仕事に反映していきたいと思っています。

POSTED BY貝瀬
View More第一線で活躍するトップマーケターの思考&行動パターンが身につく本
10年以上にわたり
多くの優秀なマーケターとプロジェクトをともにし
意見交換を繰り返した経験を持つ著者2人が
成功しているマーケターに共通する思考&行動パターンを
7つのカテゴリと50個のパターンに分け
誰でも実践できるようにわかりやすく解説!
□選ばれる理由・選ばれない理由を把握する方法
□ペルソナを明確にするためにやるべきこと
□カスタマージャーニーをうまく描くためには?
□最初に「どこでNo.1になるか」を決める
□顧客に届けるメッセージを決める
□自社の顧客がいるチャネルを探し出す方法
□顧客と直接つながるためにすべきこと
□メッセージに一貫性を持たせる
センス、才能、勘に頼らずに成果を出す
「本やネットで勉強はしているが、自分の仕事にどう当てはめて実践すればいいのかわからず、なかなか成果が出ない……」
誰でも再現可能な「成果の出るマーケティング」の思考&行動パターンを大公開!
「限られた予算の中で成果を出したいが、何から手をつけたらいいかわからない……」
多くの若手マーケターは
こんな悩みを抱えながら毎日仕事をしています。
また、若手でなくても、
思ったように成果を上げられていないマーケターの中には
「成功したマーケターは、ほかの人にない優れたセンスや特別な才能を持っているから成果を出せているのだ。凡人の自分には無理」
などと、思ってセンスや才能のせいにしてしまっている人も
少なからずいるのではないでしょうか。
では、「普通の人」は、永久に優れたマーケターにもなれないし、
マーケティングで成果を出すこともできないのでしょうか?
いいえ。
そんなことはありません。
これまで10年以上にわたり
多くの優秀なマーケターとプロジェクトをともにし
意見交換を繰り返した経験を持つ
本書の著者、栗原康太さんと黒澤友貴さんによれば
プロジェクトを成功に導くマーケターには
「共通した思考&行動パターン」があるそうです。
つまり、
「センスの良い人がマーケティングの成果を出しているわけではない」
「センスではなく、その状況において“とるべき行動”を理解し、実践している人が成果を出している」
ということです。
また、その反対に、
結果を残せず苦労しているマーケターは、
やる気や能力・才能・扇子などが足りないのではなく、
結果を残している人たちが持っている
思考&行動のパターンを実践していないだけだと言います。
言いかえれば、
成功している思考&行動のパターンを実践することで
誰でもある程度の成果を出せる可能性があるのです。
本書は、成果を出しているマーケター思考&行動パターンを
「調査」「戦略」「集客」「提案」「支援」「測定」「組織」の
7つのカテゴリーに分け、
50個の「マーケティング・パターン」として、
実践者のインタビューとともに解説しています。
たとえば、次のようなものです。
◎顧客にインタビューする&アンケート調査をする
◎顧客を観察する
◎選ばれる理由・選ばれない理由を把握する
◎ペルソナを明確にする
◎カスタマージャーニーを描く
◎どこでNo.1になるかを決める
◎顧客に届けるメッセージを決める
◎顧客がいるチャネルに露出する
◎顧客と直接つながる
◎メッセージに一貫性を持たせる
もしかしたら、
これらの思考&行動パターンは
人によっては
「すでに知っている」
「当たり前のこと」
「もうやっている」
というものもあるかもしれません。
しかし、
仕事で成果を出すために大切なことは、
「目新しさ」ではなく
「成果につながる基本行動の徹底」です。
事実、「成果を出しているマーケター」は
こうした基本行動を徹底しています。
もし、今あなたが成果を出せずに困っているというのであれば、
本書で紹介する思考&行動パターンを見習わない手はないはずです。
「成果が出ない」と嘆く前に、
ぜひ本書をご一読ください。
成果が出せていないマーケターの悩みを解決するための
ヒントとノウハウがいっぱいに詰まった1冊です。
気になる本書の内容
本書の内容は以下のとおりです。
第1章 調査
◎01-01 顧客にインタビューする ◎01-02 顧客を観察する
◎01-03 自分でサービスを使ってみる
◎01-04 アンケート調査をする
◎01-05 自社の保有データを分析する
◎01-06 独自資源を把握する
◎01-07 戦略を把握する
◎01-08 ユニットエコノミクスを把握する
◎01-09 競合企業を分析する
◎01-10 選ばれる理由・選ばれない理由を把握する
第2章 戦略
◎02-01 ペルソナを明確にする
◎02-02 カスタマージャーニーを描く
◎02-03 3年後のありたい姿を描く
◎02-04 ターゲットセグメントを広げる
◎02-05 戦略を言語化する
◎02-06 やらないことを決める
◎02-07 重要成功要因(KSF)を策定する
◎02-08 実行に必要なリソースを用意する
◎02-09 どこでNo.1になるかを決める
◎02-10 LTVを伸ばす
第3章 集客
◎03-01 顧客がいるチャネルに露出する
◎03-02 顧客に届けるメッセージを決める
◎03-03 顧客と直接つながる
◎03-04 メッセージに一貫性を持たせる
◎03-05 特定のチャネルを独占する
第4章 提案
◎04-01 営業の勝ちパターンを共有する
◎04-02 キーパーソンに営業する
◎04-03 勝率の高いセグメントに営業する
◎04-04 顧客と信頼関係を築く
◎04-05 ヒアリングの質を高める
◎04-06 費用対効果を示す
◎04-07 アップセル・クロスセルを目指す
第5章 支援
◎05-01 オンボーディングプログラムを作る
◎05-02 顧客の問題解決を支援する
◎05-03 優良顧客とのつながりを強化する
◎05-04 既存顧客に会う機会を増やす
◎05-05 解約理由を把握する
◎05-06 優良顧客の特徴を把握する
第6章 測定
◎06-01 顧客に関するデータを整える
◎06-02 重要指標を決める
◎06-03 ダッシュボードを作成する
◎06-04 顧客の行動データを把握する
第7章 組織
◎07-01 会議体を見直す
◎07-02 関連部門とコミュニケーションをとる
◎07-03 意思決定者と共通認識をとる
◎07-04 専任担当者をアサインする
◎07-05 チームの指針を決める
◎07-06 情報を社内共有する仕組みを作る
◎07-07 重要情報は1箇所に集める
◎07-08 第三者の知見を取り入れる