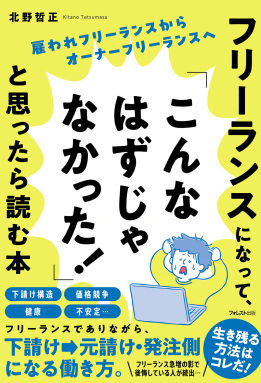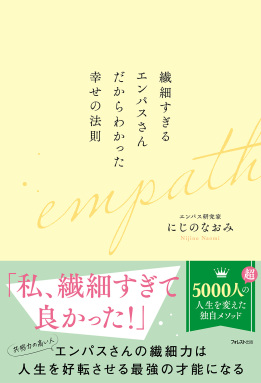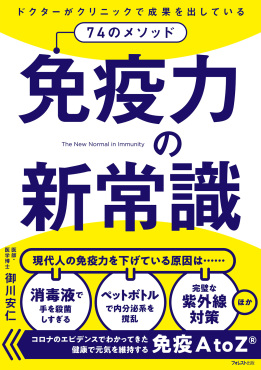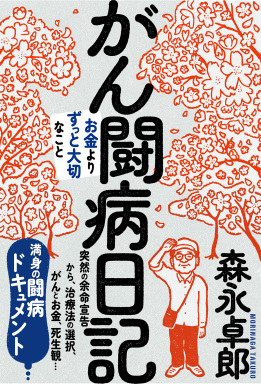著者の関連商品
著者の関連商品
-
私もフリーランスになる可能性を考えたことがありますが、結果としてサラリーマンを続けています。やはり、収入的にも時間的にも不安定になるのではないか、自分の身一つではリスクが高いのではないか、と考えてしまうから。しかしながら、本書で解説されている「オーナーフリーランス」というビジネスモデルを使えば、そうしたリスクを排除できそう。私もフリーランスになったときは、このオーナーフリーランスを選択肢の筆頭として考えることでしょう。そして、現在フリーランスとして働いている方には、ぜひ知ってもらいたいビジネスモデルです。

POSTED BYかばを
View More下請け構造・価格競争・健康・不安定…
夢や希望を抱いてフリーランスになったものの、「こんなはずじゃなかった!」と、現実とのギャップにショックを受けている人も多いはず。
フリーランス急増の影で後悔している人が続出…生き残る方法はコレだ!
事実、フリーランスとして独立したものの1年で廃業する人は3割以上、10年継続している人は1割程度というデータも。
その原因として、フリーランスには次のような課題がある。
◎できるだけ高単価な仕事を大量に受注しなければならないが、1人でこなす仕事量には限界がある。
◎競業フリーランスがいる以上、価格競争に巻き込まれる。
◎元請けが倒産するリスクを考える必要がある。
◎時代に合わせて常にスキルと知識をアップデートしていかなければ、継続的に仕事をもらえない。
もちろん、時給労働のように寝る間を惜しんでがむしゃらに働けば稼ぐことはできる。
しかし、それを継続するためには、やはり時間と心身の健康が必要不可欠。
また、結婚、育児、介護……など、否が応にも変化する家族やライフステージに対応しなければならない。
そこで本書では、以上の課題を克服する方法として、「オーナーフリーランス」という新しいビジネスモデルを提案する。
オーナーフリーランスとは?
「オーナーフリーランス」とはフリーランスでありながら、フリーランスの元締め、経営者のような存在のこと。
フリーランスでありながら、下請け→元請け・発注側になる働き方
自分以外のフリーランスに仕事を発注する仕組みや、最小限の労力で収入を得られる仕組みを持っており、自分自身が働かなくても自分に向かって入ってくる収入源を確保できる。
このビジネスモデルを手に入れることで、不安定な収入や働けないときのリスク、時間的制約など、フリーランスの課題の大部分を解消できるのだ。
「フリーランス」の限界を突破することで、本書中の実例のように年間数千万~数億円の売上を上げことも可能だ。
以上のように、場所や時間に縛られず、経済的にも自由になれる「オーナーフリーランス」になるために、本書では、サラリーマン→副業フリーランス→本業フリーランス→オーナーフリーランスというステップをたどって解説していく。
目次
まえがき フリーランスからオーナーフリーランスへ
第1章「こんなはずじゃ…」とならないためのフリーランスへの入り口
*副業フリーランスからのスタート
フリーランスのメリット・デメリット
心得① 仕事が途切れないようにする
心得② 仕事相手の期待に応える
心得③ 安定収入を確保せよ
第2章 食いっぱぐれないための仕事と仲間のつかみ方
*本業フリーランスとしての土台づくり
SNSを使って仕事を増やす
地方や中小企業を狙おう
プラットフォームを利用しよう
異業種交流会に参加しよう
第3章 絶対に生き残るためのオーナーフリーランスへの3つの道
*本業フリーランスの限界突破
限界を知り、オーナーフリーランスを目指す
オーナーフリーランスの3つの種類
「元請け」になる場合の注意点
第4章 フリーランスが抱える不安からの完全解放
*講座ビジネスのつくり方
講座ビジネスの圧倒的メリット
コーチかコンサルか、あるいはコーチ型コンサルか
まずはコンセプトを決定しよう
自分のビジネスモデルを考える
成果が出る講座コンテンツのつくり方
集客とセールスの正しい手順
第5章 売上数千万~数億超え!圧倒的な結果を出すまでの道のり
*オーナーフリーランス5つの事例
事例1 八百屋の倒産から、ドバイでオンライン集客を指導する立場へ
事例2 内職専業主婦が、オーナーフリーランスとして年商4億円を売り上げる
事例3 トレーナーとして圧倒的ポジションを築き、求心力の高いビジネスを展開
事例4 板前からお金のプロフェッショナルへ転身、経済的自由人に
事例5 リーマンショックでの挫折を経て、ストック型ビジネスで成功
あとがき あなたのビジネス経験は宝になる -
繊細すぎてつらい、苦しい、生きづらい……。こんな悩みを持たれる方が多くなりました。「HSP」などの心理学的な視点では、繊細さとうまく付き合うことでなんとか生きづらさを解消していく方法が述べられがちですが、本書はそうではありません。本書は共感力が高いがゆえに繊細すぎる「エンパス」に着目をし、その繊細さを武器に変える方法が述べられています。「繊細力」は才能であり、幸せや豊かさをつかみ取るための鍵になります。ぜひともエンパシー・メソッドについて理解を深め、実践的なステップを踏んで、豊かなエンパスさんになっていただきたいと思います。

POSTED BY美馬
View More生きづらさを感じやすい「繊細さ」こそが、
本書は、人並み外れて共感力が高く、生まれながらにして人の感情やエネルギーに敏感な気質を持つエンパスさんが幸せをつかみ取るための本です。
豊かさや幸せを⼿に⼊れる鍵になる。
繊細な人を「HSP」や「エンパス」に分類することがありますが、本書では「共感力の高い人」を意味するエンパスな人(エンパスさん)に焦点を当てています。
エンパスさんが持つ「繊細力」をどのように磨いていくのか?磨いた先にどんな未来が待っているのか?新進気鋭のエンパス研究家である著者が独自の「エネルギー理論」をもって紐解いていきます。
幸せの在り方が大きく変容し、先の見えないこの時代。こんな時代にこそ力を発揮するのが、繊細さを持つエンパスさんです。今、エンパスさんに与えられている特性と、その才能の活かし方を知ることが大切です。
繊細さを強みに変えることで、感じるチカラはセンスに変わります。
「繊細力」を輝かせる5つのステップを通して繊細力を開花させることで、新しい時代の豊かな波に乗り、美しい世界へと上昇していくチャンスをつかみ取ることができます。
あなたの中に眠る「繊細力」を磨いていき、豊かなエンパスさんへの扉を開けていきましょう。
本書の目次
はじめに
第1章 「豊かさ」へ導いてくれるエンパシー・メソッド
一口には言えない「繊細さ」の世界
「エンパス」と「HSP」の違い
似ているようでまったく違う「共感」と「同調」
同調が生み出す負のエネルギー
すべてはエネルギーから始まる「エンパシー・メソッド」
エネルギー的な引力を強めるものの正体
自分に合うエネルギーフィールドを見つける
エネルギーには個性がある?
エネルギー的個性をつくり出す4つのエレメンツ
・火タイプの特徴
・土タイプの特徴
・水タイプの特徴
・風タイプの特徴
自分の感覚はどこに向いている?
波長が高くても豊かになれない理由
自分の幸せは自分で定義する
世界は「繊細さ」に新しい扉を開き始めている
繊細すぎるのに豊かな人生を送る成功者の秘密
こうして貧しいエンパスさんが生まれる
不安の欠片を掃除するための浄化
エンパスさんはお金との相性が悪い?
お金を受け取らない「美徳」はただの「偽善」にすり替わる
「欲」のエゴではなく「光」のエゴを持とう
光のエゴで考えるタイプ別のお金の使い方
・火タイプのお金の使い方
・土タイプのお金の使い方
・水タイプのお金の使い方
・風タイプのお金の使い方
豊かなエンパスさんへの扉を開こう
第2章 美意識を覚醒させて「確信力」を高める
繊細だからこそ持っている最強のチカラ
あなただけの美意識は「共感」からつくられる
世界に評価される日本人の繊細さ
才能を輝かせるために「美個性」を知る
・火タイプの美意識
・土タイプの美意識
・水タイプの美意識
・風タイプの美意識
怖れの中の光を見ていくタイプ別浄化法
・火タイプの浄化法
・土タイプの浄化法
・水タイプの浄化法
・風タイプの浄化法
立体的にエネルギーを見つめる
アンテナを鋭くして正確な「感度」を把握する
自分自身との「一致感」を増やす
第3章 「繊細力」を輝かせる5つのステップ
【ステップ0】エネルギーの構造を知る
土台をつくるベース・エネルギー
現実創造を可能にするエネルギーの幹
【ステップ1】ベース・エネルギーを整える
ガラスのハートをダイヤモンドに変える
ベースを整える4つの掃除のポイント
【整】心身のバランスを整える
【優】本音に寄り添い自分を大切にする
【巡】気を動かしてエネルギーに余白をつくる
【爽】思考を整理して再スタートする
【ステップ2】エネルギーのカタチを知る
診断テストの結果がいつも違うのはなぜ?
【ステップ3】現実を動かす美意識を覚醒させる
タイプ別に美意識を覚醒させる方法
・火タイプと土タイプの美意識の覚醒方法
・水タイプの美意識の覚醒方法
・風タイプの美意識の覚醒方法
【ステップ4】感情ではなくエネルギーを読む
人のエネルギーが読めるようになるワーク
【ステップ5】エネルギーを統合させる
意図設定にもタイプ別の型がある
「What」と「How」を統合させる
ジャッジメントをやめて美意識を素直に受け止める
強く長くあらゆることを感じ続ける
第4章 人生は「繊細力」でこんなにうまくいく
風を受け入れて世界に羽ばたいたエンパスさん
自分の美意識に素直になって実をつけたエンパスさん
火の執着から解放されて新たな目標を見つけたエンパスさん
人とのかかわりの中で美意識が改善されたエンパスさん
無秩序の美を楽しめるようになった火と風のエンパスさん
すべてのエネルギー的個性を持つジェネラリストエンパスさん
繊細力を磨けば人生はこんなにうまくいく
第5章 「繊細力」に宿るチカラを感じよう
もっと美意識を覚醒させるために「感情帯」を捉える
すべてのエネルギーを等しく見ていく
真理を知り神のエネルギーと繋がる
セルフ・ラブで存在意義を見つける
究極の浄化は分離エネルギーから卒業すること
神の想いは等しさに宿る
いつでも神はあなたと共に生きている
あなたは光を運ぶ才能を持つ存在
おわりに -
『疲れがとれないのは副腎が9割』(フォレスト2545新書)では、お疲れのビジネスパーソンに向けて本当の疲れの原因を解明、本書はさらに発展し、免疫力を上げて病気にならないようにする方法について360度の角度からまとめました。著者の御川先生は、医療と医学に関しては博覧強記、真のウェルビーングを追求するドクター。本書はコロナ禍から何度も打ち合わせを重ね、ようやく形になりました。これ以上は削れないというエッセンスを集めた結果、かなり存在感のある書籍となっています。一般の方から医療従事者まで手に取っていただけると思います。

POSTED BY水原
View More「普通の免疫」を維持しよう
2019年に始まった新型コロナ感染症(SARS-CoV-2/COVID-19)以降、これほど、「免疫」という言葉が注目された時代はないでしょう。
人類を悩ませるのは、新型コロナウィルスだけではありません。既存の症状である花粉症、アレルギー症状、インフルエンザ、そして今後は未知の因子が現れる可能性があります。数年後(10年以内)には次のパンデミックが来ると予想できます。
しかし、こうした外部の要因に、私たちはなすすべがないわけではありません。極論すれば、ウイルスや花粉は悪者でもなければ、病気やアレルギーの原因でもないのです。それらが、ヒトにとっての「本当の敵なのかどうかを判別する能力」=「免疫力」の低下が問題なのです。つまり、問題は外にあるのではなく、自分自身の身体にあります。
はっきり言えるのは、現代人は免疫力が低下しているということ。そんな現代人にとって、「免疫を高めるのが良い」と言われますが、まずは「普通の免疫状態」でいること、これが大切です。
そして自分で免疫をコントロールし、「普通の免疫」を維持することで、必ずしも医療のお世話にならずとも、健康に、自分らしく生きていくことができるのです。
長年、救急医療の現場で、事故や病気で運ばれてくる、生命の瀬戸際の患者さんを処置し、悲惨な状況に追い込まれる場面も数え切れないくらい見てきた著者。「免疫」の重要性を嫌と言うほど思い知らされ、かつ、標準医療(日本の保険診療)のなかで免疫をコントロールする難しさも痛感してきました。
そういった経緯もあり、救急医療の助けが必要な人を減らし、人が本来持っている自己回復力(病気にならない力)を高める、そして免疫力を高めるための医療を模索。オリジナルのハイブリッド栄養医学®を構築し、病気の予防、免疫の機能を高め維持するため研究し、その実践方法をA からZの事典風資料「免疫A to Z®」としてまとめました。
なんとなくわかったようでわからない「免疫」について、今こそ知ってほしいのです。
本書の目次
Part.1 「免疫」とは何だろう?
「免疫」とは何だろう?
そもそも人はなぜ病気になるのか?
免疫システムとは免疫3兄弟TM「防御」「攻撃」「制御」
【粘膜免疫=防御】
【全身免疫=攻撃】
【免疫制御=制御】
「免疫を上げる」とはどういうこと?
清潔すぎる社会が免疫システムのバランスを崩す
正常な免疫システムのすごい力
大切なのは神経質になりすぎないこと
Part.2 免疫 A to Z®
A
ビタミンA〈天然型〉
IgA抗体
アルコール
不安と怒り
アシュワガンダ
大気汚染、空気汚染
オートファジー
B
ビタミンB群
入浴
C
ビタミンC
コラム1 ステロイドが免疫を高める!?
クルクミン
CBD
D
ビタミンD
DHA EPA
コラム2 適度に必要なアラキドン酸(オメガ6脂肪酸)
E
エキナセア エルダーベリー
EGCG
F
疲労
腸内細菌叢、食物繊維
コラム3 腸内フローラ移植(便移植)と腸内環境
食べ物
G
うがい
グルタミン
グルタチオン
GSE
H
湿度
水分補給
水素
I
免疫
屋内
不確かな情報の伝染
自然の中で
ヨウ素、ヨード
J
自律神経
K
漢方
換気
草津温泉/温泉
基礎疾患
L
リーキーガット症候群、腸漏れ症候群
孤独
リンパ球
M
マグネシウム
想
メラトニン
ミトコンドリア
口腔
N
一酸化窒素
鼻うがい
栄養
O
オリーブ葉抽出エキス
P
歯周病
プラスチック
胃酸抑制剤
プロバイオティクス
タンパク質(アミノ酸)
Q
ケルセチン
R
休息とリラックス
レスベラトロール
S
セレニウム
睡眠
笑い
喫煙
ストレス
砂糖
サン・ゲージング
T
体温
U
運動
紫外線
V
バイブレーショナル・メディスン
ワクチン
W
洗う
X
生体異物、異種エストロゲン
Y
カンジダ菌
葉酸
Z
ザクロ
亜鉛 -
『超一流の雑談力』をはじめ、数々のベストセラーを世に送り出してきた著者による渾身の英語学習法です。そのメソッドは、単語力もいらなければ、発音を覚える必要もないという、非常に画期的なもの。「3つの英語のカタチ」を覚えるだけで、どこへ行っても伝わる英語を話せるようになるのです。しかも、それが10日程度で。信じられないですよね? しかし、それほどシンプルで日本人に合った学習法なんです。何年も英語を勉強しても上達しない人、英語を話すことをあきらめた人、どうしても英語を習得しなければならない人……、そんな英語弱者である日本人全員に試してほしい一冊です。

POSTED BYかばを
View Moreこの方法で無理なら、あきらめるしかない!?
中高大と勉強したのに、なぜ日本人は英語を話せないのでしょうか?
世界一簡単で、10日でマスターできる、日本人のための英語習得法
本人のやる気や置かれた環境もあるでしょうが、一番の理由は学習法が悪いからとしか言いようがありません。
単語や文法、フレーズを暗記し、正確な発音を覚え、リスニング力を鍛える――。
どう考えても、ふつうの日本人には無理ゲーすぎます。
しかし、あきらめないでください。
本書では、著者が英国留学や法人英語研修を通して「英語学習での日本人共通のつまずき」を発見し、その解決法として開発した「日本人のための英語学習方法」を解説します。
この方法なら、たった10日間で英語を話せるようになります。
事実、35万人、上場企業を含む3000社がこの方法を実践し、英語力を高めたのです。
具体的には、以下の英語の3つのカタチ(文法ではない)を駆使した方法です。
●A=B
●主語+動詞+A=B
●主語+動詞+人+物
このカタチに、パズルのように日本語や英語をはめ込むことで、驚くほど伝わる英語力を身につけられるのです。
もし、この方法でも英語をマスターできないならば……、そんな人はいないはずなので心配しないでください。
英単語・表現の暗記は必要なし!
「とはいっても、単語を暗記したり、発音の練習をしたり、リスニング力を上げなければ……」と思うことでしょう。
文法や発音も気にしない!いや、気にするな!
最低限のリスニング力習得もしっかりフォロー!
しかし、心配はいりません。
本書のメソッドは、
◎今持っている単語力だけで話せるから無理に単語を覚えなくてもいい。
◎発音が正しくなくても、きっちり伝わる方法だから気にしなくていい。
◎リスニング力が自然に鍛えられるし、そのコツもしっかりフォロー。
というものだからです。
語学書のベストセラー『英語は「インド式」で学べ!』の著者が、そのメソッドをより進化させ、これまでの経験を凝縮した渾身の一冊です。
目次
まえがき 「表現を暗記する」から「カタチを理解する」英語学習法へ
プロローグ 「このクルーズ船のディナーはおいしそうですね」を英語で言えますか?
CHAPTER 1 10日間で英語がペラペラになる魔法
CHAPTER 2 日本人に合った英語の習得法で学べ
CHAPTER 3 日本人が苦手なカタチ1 A=B
CHAPTER 4 日本人が苦手なカタチ2 主語+動詞+A=B
CHAPTER 5 日本人が苦手なカタチ3 主語+動詞+人+物
CHAPTER 6 前置詞はatとwithのみでOK! 積み残し情報の入れ方
CHAPTER 7 今ある単語力だけで、会話を成り立たせる方法
CHAPTER 8 身につけよう! 日本人が苦手な「伝えるエネルギー」
CHAPTER 9 3つの英語のカタチを自由にあやつる方法
CHAPTER 10 英語のカタチで格段にアップ! リスニングの鍛え方
付録 リスニング演習&英語のカタチ別!動詞の使い方と例文
エピローグ 10日間の魔法の英語トレーニングで、1年後にはここまで変わる -
「来春のサクラが咲くのを見ることはできないと思いますよ」View More
医師からそう告げられたのは、2023年11月8日のことだった。余命4カ月の通告だった。私はにわかには信じられなかった。何しろ、なんの自覚症状もない。朝から晩までフル稼働で仕事をして、食事もモリモリ食べていた。
突然の余命宣告から、治療法の選択、
がんとお金、死生観…
満身の闘病ドキュメント
私は「いつ死んでもいい」とは思っていないものの、延命にはこだわっていない。
それは、いつ死んでも悔いのないように生きてきたし、いまもそうして生きているからだ。それが具体的にどういうことなのか。それをお伝えしたいというのが、本書のメインテーマだ。
(「まえがき」より)
もくじ
まえがき
第1章 突然のがん宣告
晴天の霹靂
抗がん剤で死にかける
初めての長期入院
精神的、肉体的限界
マスメディアへの公表
第2章 殺到する「がんの治し方」
精神論——「がんの治し方」アドバイス1
飲食物——「がんの治し方」アドバイス2
体を温める——「がんの治し方」アドバイス3
イベルメクチン——「がんの治し方」アドバイス4
名医がいるクリニック——「がんの治し方」アドバイス5
アドバイスしてくれる人の3タイプ
本当の効果はわからない
第3章 がん治療とお金
衝撃の血液パネル検査結果
がん細胞軍団vs免疫細胞軍団
標準治療と自由診療
預金を生前整理する
投資資産の有意義な使い方
がんと仕事と障害年金
詐欺広告に利用されて
第4章 私の選択
泣きっ面に尿管結石
お見舞いをお断りしたワケ
血液免疫療法の選択
第5章 いまやる、すぐやる、好きなようにやる
私の仕事のスタイル
格差と出合う
営業が一番楽しかった
運命の出会い
三井情報開発とバブルの恩恵
理想の会社を作る
大きな転機
「ニュースステーション」の約束
ラジオという自由の大地
モリタクゼミの改革
B級で、おバカだけれど、ビューティフル
第6章 素敵な仕事、自由な人生
歌人になりたい
歌手になりたい
童話作家になりたい
モリオ童話集withかのん
ヒツジ飼いの少年とオオカミ/お代官さまと農民/曜変天目茶碗
新版 アリとキリギリス/星の砂/イワシとシャチ
農業ほど知的な仕事はない
家族のこと
父の信条
あとがき
【発行】三五館シンンャ/【発売】フォレスト出版