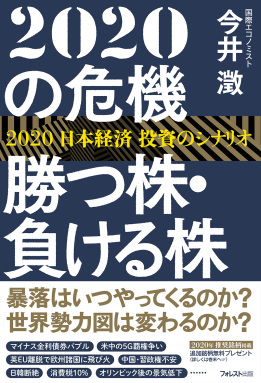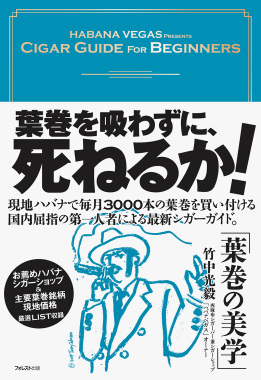著者の関連商品
著者の関連商品
-
毎年12月下旬に発売している「日本経済 投資のシナリオ」シリーズ。今年は10月下旬以降にかけて相場が暴落するかもしれないということで、読者にいち早くその内容をお伝えすべく早めに刊行しました。世界はすでに債券バブルで、いつこれが弾けてもおかしくない状況です。そして、2020年に迎える世界の危機的状況をどう乗り越えていくか、その道しるべとなる様々な世界情勢、日本経済、さらにブラックスワンのシナリオを開陳していきます。

POSTED BY稲川
View More暴落を示す「債券バブル」はいつ弾けるのか?
今、世界のマネーは債券市場に流れ続けています。
そのマネーの量は14兆ドルという途方もない数字です。
しかし、現在買われているのはマイナス債券です。
つまり、外国人投資家は行き先のないマネーを
マイナス債券でもいいと買い続けているのです。
当然、償還まで持っていれば赤字です。
ですから、償還前に売り抜けるのは必至で、
それがいつになるのかが、つまり暴落時期を意味します。
むろん、債券市場が引けばマネーの投資先は株式に戻りますので、
それが本格的になれば株式市場はにぎわいます。
つまり、債券の大量売りで市場はいったん混乱、暴落を迎え、
やがて株式市場に流れ込むという図式です。
では、そのサイクルはどうなのか?
本書は株式暴落から上昇へのシナリオを提示していきます。
こうした状況の中で、世界はどう動いていくのでしょうか?
新冷戦時代の突入で見えてきた勝ち組企業と負け組企業は?
トランプ大統領の再選はあるのか?
中国の習主席の一強体制はいつまでもつのか?
そして迎える、2020年の日本の行方は?……
著者の外国人ヘッジファンドからの情報や、
日本の要人や経済論客者からの話、
数字が示すさまざまなデータや図表から
これから勝つ株、負ける株が見えてきます。
予断を許さない世界のブラックスワンの可能性。そのとき日本株は……
これから迎える2020年は、日本にとって大きな節目となる年です。
2020年に先行して始まった消費税10%、オリンピック後の景気低下、
日韓断絶、拉致問題、そしてポスト安倍の存在……。
日本にとってはまさに危機が到来します。
しかし、債券バブル終焉から始まる株式市場の上昇で
ふたたび日本が復活する方策は、すでにいくつも存在しています。
本書ではそうした材料を提示し、日本株が上昇する構図を示していきます。
いっぽう、世界には日本市場を揺るがす
さまざまなブラックスワンも存在します。
そもそもブラックスワンは見えないところから突然やってくるものですが、
そうした火種は、世界中にあると言っていいいでしょう。
覇権争いで習一強体制が崩れた中国、
2020年も注視が必要なドイツ銀行、
EUが瓦解しかねないイタリアという新たな存在、
イランとサウジアラビアが繰り広げる中東不安、
経済が土砂降り状態の韓国など、
目に見えるだけでも、どこからでも不協和音が聞こえてきます。
こうした諸問題も押さえつつ、
自身の資産をどう守り、どう増やしていくのか。
まさに知っておくべき情報が満載です。
目次
はじめに
第1章「債券バブル」とその終焉を迎える世界
各国中央銀行が推進するバブル経済政策
2020年の危機の火種と「催促相場」の出現
1回目の日経平均下げは2万円前後か
2回目の危機はカネ余り債券バブルの崩壊
マイナス金利国債の保有残高は、いまや14兆ドル
なぜマイナス金利の債券でも買われるのか
2020年に起こる債券バブル崩壊
債券バブルを弾けにくくしている中国の為替操作
米国の大幅利下げが金融危機を封じ込める可能性
投資家が懸念する人為的な中国の米国債売却
600兆元、借金大国中国に米国債大量売りはできない
金利上昇に対する耐久力を示す「ゾンビ企業」の数
債券バブル崩壊で死刑宣告を受ける世界のゾンビ企業
債券バブル崩壊は日本の夜明けを告げる号砲となる
第2章 米中新冷戦の「勝ち組」と「負け組」
新冷戦の形はロシアのクリミア半島侵攻から変わった
戦争はもはや机の上で完結する時代となった
戦争は電磁波攻撃という恐ろしく「冷たい戦争」となった
経済で立ちゆかなくなった習近平の一強体制の陰り
習近平の権力低下で息を吹き返す人民解放軍と香港デモの行方
いまや主導権を掌握する人物「現代中国のラスプーチン」
5G覇権をめぐり静かに進行する米中経済断絶
30年のグローバル化はかつての冷戦時代へと逆回転する
グローバルIT企業にとって冬の時代が到来する
米中新冷戦時代の「勝ち組み・負け組」企業
第3章 2020の日本。拉致問題、北方領土、消費税、財政政策、そしてポスト安倍
W選挙が見送られた理由とポスト安倍の浮上
次期首相候補の存在感を国民に示した安倍首相
日朝首脳会談実現に向けて日本は食糧援助を申し出た
拉致問題のバトンは次期首相候補に手渡された
安倍首相が消費税10%強行した本当の狙い
日朝首脳会談に「無条件」を提示した日本に呼応した北朝鮮
衆院解散、自民快勝の伝家の宝刀は拉致問題
朝鮮半島、南北合邦に無視できない日本の存在
消費税増税で懸念される消費マインドの低下
「全世代型社会保障」という国民の負担増
増税による天下りポストを増やす財務省
2020年オリンピック後の2つの秘策
私が主張しつづける財源問題ウルトラC「超長期国債」
経済成長とともに借金が消える国債償還ルール
第4章 2020年の米国。トランプ大統領は再選されるか?
トランプは大衆操作に長けた興行師なのか?
白人貧困層をターゲットにしたSNSイメージ戦略
トランプの支持基盤、農業を攻撃する中国
牛肉を買わせるトランプに日本の畜産農家が打撃を受ける
好景気を演出するしかない工業都市での苦戦
経済と株価のテコ入れでニューヨーク市場はいつ天井を打つのか
米国の統一した政策「インフラ投資」
ドル、ユーロ、円。通貨量を増やしながらの均衡が暴落を抑える
5Gインフラ投資が世界のGDPを3兆ドルに押し上げる
5G覇権争いで一歩先を行くファーウェイとキャスティングボウトのEU
不透明資金や諜報機関がうごめく米国ITハイテク産業
新自由主義を後退させたトランプが世界に与えた影響
5G成功企業の投資はマイクロソフト株を連想させる
第5章 2020年の日本株。描かれる再挑戦へのシナリオ
エリオット波動が示すニューヨークダウの天井
底値からスタート。2020年に日経平均は3万円に再チャレンジする
日経平均は上昇トレンド過程の「サード・オブ・サード」
いまの相場では「個別銘柄偏重」と「信用取引」は避ける
2020年の危機、債券バブル崩壊後からの本格投資へ
「10月末買い、4月末売り」で値幅を取る
債券バブルをきっかけにアメリカ株は調整される
バブル崩壊後は債券の莫大なマネーが株バブルを生み出す
債券から株式マネーはどの市場に流れ込むのか
米中新冷戦の長期化によるグローバル企業の撤退で恩恵を受ける国
周囲に弱気が出回ったときこそ投資のチャンス
群集心理で動いていては大きな成功は得られない
第6章 世界経済を襲うブラックスワンの可能性
世界中にあった不良債権はどこへ行ったのか?
中国の不動産バブルはいつまで政治力で押さえ込めるのか
対米柔軟派と強硬派が主導権争いをくり広げる中国
隠されたマイナス成長と中国経済の崩壊
歴史の清算にこだわりつづける文政権と韓国
日米の影響力を排除したい「北の核」の存在
国際勢力図を揺るがしかねない韓国の南北統一
企業の信用度が著しく低下し、もはや土砂降りの中の韓国経済
サウジアラビア対イランの争いで風雲急を告げる中東世界
サウジアラビア攻撃でアメリカを翻弄するイランの目的
もはや自力で更生できないドイツ銀行は2020年も注視が必要
欧州の新たなる震源、反EUを掲げたイタリア
新たに発行する必要性が問われる暗号通貨「リブラ」
暗号通貨が世界の主流なるには乗り越えなければならない問題が山積み
おわりに「今井澂の心配(失敗)3原則」と「注目5銘柄&必勝テクニック」
-
全国の喫煙者諸君!オールドファッションを愛するが故に蔑まれる喫煙者たるもの(私も喫煙者です)、断固として禁煙ファシズムには立ち向かおうではないか!・・・というワケではないのですが、タバコがダメなら葉巻はどうでしょ。なんせ、カッコいいじゃないですか。でも、敷居が高いですよね。本書はそんなビギナーの思い込みをガツンと砕くインパクトがあります。ぜひ、お気に入りの葉巻とラム酒を片手にご一読を。

POSTED BY寺崎
View More葉巻界のレジェンドの生きざまを通して
いま、全国のバーで
葉巻の奥深い愉しみ方を伝える
葉巻ガイド決定版が誕生!
ひそかな葉巻ブームが起きているのをご存じだろうか。
2020年4月から東京都受動喫煙防止条例が施行され、
禁煙の流れが強まっているが、
シガーバーは規制の対象外となった。
近年の禁煙ブームの中、
新宿のとあるショップでは、
ここ10年ほど葉巻の売上げが伸び続けているという。
葉巻の吸い方にルールなどない
かつて、葉巻を愛した男たち。
ウィンストン・チャーチル、アーネスト・ヘミングウェイ、アル・カポネ、アラン・ドロン、チェ・ゲバラ、フィデル・カストロ、ジョン・F・ケネディ、吉田茂、マイケル・ジョーダン……。
綺羅星のごとく歴史上に名を遺した男たちだ。
少しでも彼らの存在に近づきたいのであれば……
葉巻を吸えばいい。
葉巻の吸い方にルールなどない。
葉巻の愉しみに正解などない。
葉巻は一般的にいえば、敷居の高い、
手の届かないものだという印象を持つ人は多い。
多くの初心者は、とかく身構えてしまい、
葉巻を崇高な嗜好品だと思い込んでいる。
みんなネットやマニュアルを見て、知識で理論武装。
頭をいっぱいにして葉巻の世界に入ってくる。
しかし、それは根本的に間違いだ。
繰り返し言うが、葉巻の吸い方に正解はないのだ。
それを教えてくれるのが
本書『葉巻の美学』である。
ようこそ。
かくも奥深き葉巻(シガー)の世界へ。
==========
本書は、国際的なシガーコンテストで優勝を果たし
現地ハバナで毎月3000本の葉巻を買い付ける
国内屈指の第一人者による最新シガー入門書です。
【こちらの目玉コンテンツも収録】
◎ハバナの極上シガーショップガイド(MAP付き)
◎初公開!主要葉巻銘柄の現地価格一覧
◎ハバナ・トラベルガイド
本書の目次
第1章 人生を識る。――私の銀座修行時代
第2章 いまを愉しむ。――「ハバナベガス」とハバナ
第3章 人生を学ぶ。――一流の男たちとの交遊
第4章 葉巻と生きる。――わが人生と葉巻
第5章 葉巻と興じる。――極私的葉巻ガイド20本
第6章 葉巻と出会う。――はじめての葉巻の嗜み方
第7章 聖地に集う。――ハバナの極上シガーショップ一覧
第8章 知恵を分け合う。――ハバナの葉巻と旅と酒と
- View More
-
View More
あなたは今、毎日を楽しく生きることができていますか?
誰だって
●将来に不安を感じてしまう
●自分らしい生き方が見つからない
●自分の感情を上手くコントロールできない など、
少なからず悩みを持っています。
あなたはどうですか?ほんの些細な悩みが原因で、 夜も眠れなかったり、仕事もぜんぜん手につかなかったり。
そんな経験、少なからずありますよね。あなただけではありません。みんな同じです。
不安を感じない人はいませんし、悩みがない人もいません。
どんな偉い人だって、あなたの憧れの人だって同じです。
ちょっと考え方を変えると毎日はもっと楽しくなる!
では、どうすれば、不安や悩みに負けず、
楽しくワクワクする毎日を送ることができるのでしょうか?
実は、"自分の悩みや不安にどう向き合うか?"
その方法を知っているだけで、まったく違う毎日が見えてきます。
あなたも「悩みや不安との向き合い方」を知ることさえできれば、
心がラクになって、毎日が今よりずーっと楽しくなります。
もしかしたら、
「そんな簡単にできるのかな…」と思うかもしれませんね。
でも安心してください。きっと、あなた思っているよりずっと簡単です。
"お金と幸せの専門家"であり、 ベストセラー作家・本田健さんが、
あなたの心がホッとさせて、毎日がワクワクする人生を送る方法を教えてくれます。
本田健さんが今まで学んできた 心理学のテクニック、メンターからの学びを凝縮して、分かりやすく伝えるCDを作りました。
CDを聞くだけで、心の不安が消え、感情がコントロールできるようになり、自分らしい生き方が見つかります。
あなたもぜひ、このCDを聞いてみてください。 - View More