 著者の関連商品
著者の関連商品
-
View More
"お金に縁がない人の設計図"を
突然ですが質問です。
"お金持ちの設計図"に書き換える方法とは?
あなたは次の項目に、
該当する内容がありますか?
□ なぜか、お金が貯まらない
□ お金のことを専門的に勉強したことがない
□「金持ちになれたらいいなぁ」と思っている
□ 何となくお金の不安がある
□ お金持ちになるには、何か秘訣があるのでは?と思っている
・・・いかがでしょう?
もし、1つでもチェックがついたとしたら、
知っておいて欲しいことが1つだけあります。
それは、残念ながらあなたがまだ
人生を豊かにする「お金の設計図」に
気付いていない――ということです。
「お金の設計図」とは、
「お金」に関して、あなたがどのような
運命を辿るのか、
そして、将来豊かになるのか、
それとも貧しいまま終わるのかをすべて解き明かした、
【財政状況を決める青写真】のようなものです。
これを知らない限り、あなたは
「なぜ今回は儲かったのか」
「なぜ今回は損をしたのか」という理由が
一切わからないまま、生きていくことになるのです。
そんな人生は、【ギャンブルと同じ】です。
「お金持ちがとるべき選択肢」と
「お金に縁がない人がとる選択肢」を
50:50の状態で選び続ける――
そんなギャンブラーのような毎日を
送っていくことになってしまうのです。
あなたはこのような人生を送りたいですか?
もし、あなたが、
この質問に「No!」と答え、
「"お金の運命"を自由自在にコントロールし、
常にお金持ちがとるべき選択肢だけを選びたい!」
このように思うとしたら
あなたが取るべき方法はたった1つ。
【お金持ちの設計図】を手に入れて、
もっと具体的にいえば、
それをあなたの今の設計図にインストールするのです。
【お金持ちの思考回路】【お金持ちの判断基準】を
あなたの潜在意識下に完全に刷り込ませるということ。
これさえ出来れば、
あなたの選択するあらゆる行動は、
【お金持ちの設計図】に則った行動となります。
そして、たとえどんな場面、状況でも、
【一切の迷いなく、常にお金に繋がる行動】
を選択することが出来るようになるのです。
そして今回、なんとあのT.ハーブ・エッカーが、
【お金持ちの思考回路】に共通するすべての点と、
【お金の設計図】の描き方を、日本で初公開します! -
あなたの中から、無限の富を引き出す方法を直伝します!
『Golden Life Program 2014』【ダウンロード版】通常価格
ジャネット アットウッド 講師/本田 健(Ken Honda) 講師/マーシー・ シャイモフ 講師/リン・ トゥイスト 講師/フィル・ タウン 講師

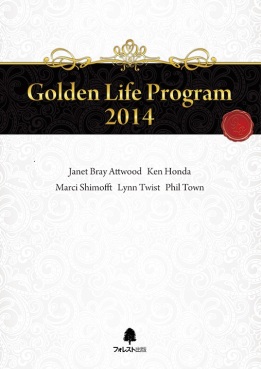 2014年5月、東京ビッグサイト―View More
2014年5月、東京ビッグサイト―View More
それぞれの分野でトップクラスの活躍をする
名スピーカーたちによって開催された
【伝説のプログラム】を映像化!
■情熱的な人生を送りたい
■運命を切り開きたい
■自分の才能を発掘したい
■幸福感に満ちた生活をしたい
■お金の不安を無くし、経済的自由を手にしたい。
これら全ての願いを叶える方法を、
この1本で手にすることができます! -
誰でも、「気が乗らないとき」「難局が立ちはだかるとき」というものはあるものです。でも、やらなければいけない、乗り越えなければいけない……。そんな状況のとき、何としても自分を動かす必要があります。自分で自分を奮い立たせる必要があります。本書では、NLP・行動分析学から導き出した科学的根拠に基づいた、自分のハートに火をつけ、圧倒的な結果を出す方法を解説しています。仕事にもプライベートにも使える1冊です。

POSTED BY森上
View More難局を乗り切るとき、
◎めんどくさいけれど、何としてもやらなければいけないとき。
自分を鼓舞するスイッチのつくり方
◎難局が立ちはだかったとき、自分を鼓舞する必要があるとき。
◎昔は熱い人間だったのに最近はなかなか熱くなれていない人。
◎なんとなくくすぶっている自分に納得できない人。
◎潜在能力は高いのに、本気になれないために結果がついてこない人。
◎昔から冷静だが、熱くならないといけない場面が増えている人。
◎モチベーション難民になって最初の一歩が踏み出せない人。
プライベートにせよ、仕事にせよ、
人生において
「自分で自分を鼓舞しなければならない」ときが、
誰にでもあるものです。
そんなとき、
自分を奮い立たせ、
圧倒的な結果を出す方法を
完全公開した書籍が登場です。
本書でお伝えするものは、
いわゆる「精神論」ではありません。
キーワードは、
「クールヘッド&ウォームハート」。
超人気の「絶対達成」コンサルタントが、
NLP・行動分析学から導き出した
くすぶっている自分のハートに火をつける方法を
徹底伝授します。
「気が向かないが、やらなければならないとき」
「目標達成まであともうひと踏ん張り必要なとき」
「突然のピンチ(難局)を乗り越えたいとき」
「大事なプレゼンなどの大一番の勝負のとき」
といったときに、
思いどおりに、
自分を熱くし、クールダウンさせる技術
をわかりやすく解説します。
気になる本書の内容
本書の内容は以下のとおりです。
第1章 「熱い人」を分類する
◎あなたの「火付け役」は誰?
◎自分で自分のハートに火をつけるメソッドとの出会い
◎少しの空気で火がつく炭になれ!
◎日本に少なくなった「熱い人」
◎「熱い人」の分類
◎重要なのは、「感情コントロール」
◎理想を語るだけで終わる「熱い系」の人々
◎あなたの身近にもいる「熱い系」
◎「熱い人」と「熱い系の人」の特徴と大きな違い
◎情熱の火が宝の持ち腐れに終わる人に足りないもの
◎「熱い人」なのか、「熱く話す人」なのか
◎「あり方」は1つ、「やり方」は無数
◎情熱の有無を測る1つのバロメーターとは?
◎「熱に浮かされた人」になっていないか?
◎本当に「熱い人」にあって、「熱い系の人」にないもの
◎「熱い系の人」は、各論に入るほど答えられない
◎「熱い人」のスケジュールの中身
◎「熱い系の人」が使う口グセ
◎熱い思いが空回りする根本原因
◎「脳のマイニングスキル」を鍛えよう
◎有名コラムニストに学ぶ、情報の収集&加工技術の磨き方
◎情熱は「視座の高さ」でわかる
第2章 「熱意」「情熱」「熱量」の正体
◎自分を熱くする「背景知識」
◎「1分」ではなく、「1時間」話せるか?
◎気勢を上げても、何も伝わらない
◎「非言語的コミュニケーション」の重要エッセンス
◎「話力」以上に熱意を伝えるもの
◎熱意は「点」、情熱は「線」
◎情熱とモチベーションの関係
◎モチベージョンが情熱に変わった人
◎モチベーションの高め方を知る前に、見極めるべきこと
◎偶然にどこまで期待するか
◎モチベーションを高めやすい体質になる、基本的な流れ
◎自分の〝体質〟を見る方法
◎自分の〝体質〟は、炭なのか、それとも、普通の木なのか
◎情熱がない人が情熱を持てるようになる方法
◎「気合い」を入れる有効性──精神論ではない「気合い」
◎「気合い」という便利道具を活用する
◎自分を熱くする最小単位「気合い」──小さな「きっかけ」づくり
◎「気合い」を入れるビフォーアフターを感じてみる
◎「感覚レベル」を設定し、数値化する
◎「感覚レベル」の手順
◎自分も他人も気づいていない自己を開く──「ジョハリの窓」
◎未知の自己を開くうえでの最大の敵
◎「未知の窓」を開くために必要なこと
◎なぜベテランほど、「気合い」が大事なのか?
◎AI時代、「熱量」はブランドになる
◎「熱量」とは、何か?
◎人(の心)を動かすのに、「熱量」は不可欠
◎恥ずかしがる人は、「熱量」が足りない
◎駆け出しのコンサルタントが熱量の価値を気づいた瞬間
◎くすぶっていた新人コンサルタント、「熱量」を取り戻す
◎自分の思考プログラムを変える
◎「伝える内容」は変わらないのに、「伝わり方」が大きく変わる
◎「恥じらい」が邪魔をする年齢層
◎熱量を浪費してはならない
◎誰をバスに乗せるか
第3章 人を動かす「情熱資産」
◎「情熱資産」とは、何か?
◎リーダーが持つべき、情熱資産の理想的な自己資本率
◎その情熱は、自己資本? 他人資本?
◎リーダーに求められる「熱量マネジメント」
◎いかに大きな「流れ」をつくれるか
◎個人レベルで「流れ」をつくる方法
◎組織を熱くする
◎そもそも組織とは何か?
◎熱気あふれる組織にするためのメンバー選び
◎組織の空気を良くする「メルコサイクル」の使い方
◎「ルール」を徹底させる取り組み
◎コミュニケーションを潤滑油にする3つのポイント
◎「メルコサイクル」を回す
◎人は物語で熱くなる
◎商品開発にも「物語」がある
第4章 ハートに火をつける技術
◎自分の「火種」はどこにある?
◎火種は、過去の経験にしか存在しない
◎私を救った1冊のノート――「火種ノート」
◎「火種ノート」に書く中身
◎質の高い「火種ノート」を書くポイント
◎自分を熱くする技術を学ぶ前に知っておきたい重要概念──アソシエイトとディソシエイト
◎私はどうやって、あの難局を乗り越えたのか?
◎論理的思考力は、ディソシエイト状態で発揮される
◎「根拠のない自信」をなぜおすすめしないのか?
◎「頑張ればできる」という論拠を見つける
◎難局を乗り越えるために、自分を熱くする手順
◎自分を熱くする2大テクニック
◎自分を熱くするために、最もお手軽な技術「アンカリング」
◎アンカーが落ちるタイミング
◎アンカリング効果を意図的に活用する
◎五感とディテール
◎「自分を熱くするスイッチ」のつくり方
◎戦略的にアンカーを落とす
◎「火種ノート」におすすめのノート
◎アンカリングを使って、鼓舞する
◎正しくスイッチをつくるための注意点
◎自信がみなぎった状態にする技術「ニュー・ビヘイビア・ジェネレーター」
◎自分に合った「ロールモデル」の見つけ方
◎徹底的にロールモデルになりきって演じられるかどうか
◎目で観て耳で聴いて熱くなるだけでは意味なし
第5章 熱さをコントロールするコツ
◎場の力で、熱さを補充する
◎熱中しないときを、あえてつくる
◎燃え尽きてしまったら終わりだ
◎リーダーこそ、燃え尽きにご用心
◎自己犠牲はほどほどに
◎衝動的な感情とうまく付き合うコツ
◎衝動で熱くなっている自分を和らげる方法──グラウンディングとカウントバック
-
25年間の実績、有名企業への研修・講演などで大人気!現在最も企業・教育現場が注目する自己肯定感のスペシャリストが、職場の人間関係を良好にする方法を紹介。自己肯定感を高めるステップを踏めば、わかりあえない他者とのコミュニケーションがうまくいく。

POSTED BY編集者H
View Moreわかりあえない他者との上手なつき合い方
仕事で上司や先輩と意見が食い違う
地位がある人からの理不尽がつらい
世代間ギャップを感じる
陰口やグチを言う人にストレスを感じる
仕事の進行をストップさせる人がいる
同じ職場に心を許せる人がいない
「職場の人間関係についての悩み」の悩みの根底には、
その人の「自己肯定感」が影響しています。
攻撃してくる人、苦手と感じる人など、
わかりあえない人とも、職場では、
コミュニケーションは取らなくてはいけません。
本書では、企業・組織で働くあなたが、
職場での人間関係の悩みを減らしていくための
「自己肯定感を高め方」をお伝えしています。
なぜ、自己肯定感を高めると、職場の人間関係が良好になるのか?
自己肯定感とは、
「ありのままの自分を、かけがいのない存在として、
好意的・肯定的に受け止める感覚」のことです。
自己肯定感が低い人は、
他者への許容力が低く、ちょっとした攻撃や、
行き違いで、心が折れてしまいます。
自己肯定感は、2種類あります。
社会的自己肯定感とは、
他者からの評価や相対的評価から生まれます。
絶対的自己肯定感とは、
「自分で自分の存在価値を認めてあげること」で生まれます。
社会的自己肯定感は、自分ではなかなかコントロールできないので、
まずは絶対的自己肯定感を持ってください。
自己肯定感は、本書でご紹介する
ステップを踏めば必ず高めることができます。
25年間で、のべ2万への指導実績
著者は現在、企業や教育現場で、研修、講演、
個人向けの講座を通して、自己肯定感の重要性を
広める活動を行なっています。
最近では、中学生の道徳の教科書にも、
自己肯定感について執筆しています。
これまで、25年探求してきた自己肯定感の知見に基づき、
2万人を超える人々にそのノウハウを伝えてきました。
本書では、その経験の中から再現性のある
人間関係に有効なものを抜粋しています。
それでは、気を楽にして読み始めてください。
本書の内容
●なぜ、自己肯定感を高めると職場の人間関係が好転するのか?
●自己保身をやめれば、あなたは安心される存在になれる
●絶対的自己肯定感を高める5つのステップ
●タイプ別で見る自己肯定感を下げないための対処法
●場面別で使える自己肯定感を下げない対処法
●1枚の紙に書くだけで自己肯定感は高められる
-
曖昧模糊とした「正解のない時代」を生き抜くグローバル人材の育成を目的に立ち上がった国家プロジェクト「トビタテ!留学JPAN」。View More
「成績・英語力不問」「情熱・好奇心・独自性」重視で選考した1万人の高校生・大学生を海外に送り出すプロジェクトは、「自立心が身についた」「自分の使命がわかった」と学生の人間的成長をもたらし、教育関係者や企業関係者から高い評価を得ています。
本書では革新的な留学プロジェクトが生まれた軌跡と海外で活躍ができる人材を育てるノウハウについてお伝えします。
著者は、「トビタテ!留学JAPAN」を立ち上げたプロジェクトディレクター。
商社マンや起業家として活躍し、ダボス会議のヤング・グローバル・リーダーズとして世界のトップ人材らとも交流。その経験から、「留学=越境体験」が飛躍的に若者を成長させると確信し、本書では「『世界』と『日本』、そして『自分』を知る」をキーワードに留学の魅力や意義をつづっています。
「トビタテ!留学JAPAN」には有名企業240社が構想に共感し、約120億円を寄附。これらの企業が留学経験を採用で重視しているデータもあるなど留学は人生を成功させるための強力なツールになっています。
本書には海外留学の修羅場を乗り越えた高校生・大学生の体験談、ソフトバンクグループ孫正義氏の留学体験スピーチをはじめ、プロジェクトの立ち上げに関わった第一線で活躍する政治家や起業家らの逸話や彼らが海外へ旅立つ学生たちに語ったアドバイスも収録されています。
本書の一部をご紹介
・憧れの本田圭佑選手に事業計画をプレゼン、
出資を決めさせた大学生のパッション
・中国系留学生に圧倒されて実力不足を痛感、
100本以上の論文を読みあさったストイック留学
・発展途上国の現実を肌感覚で実感、高校生が身に付つけた「自分を信じる力」
・日本人の強みと傾聴力とチーム力
・留学先で「Who are you?」と問われたら……
・「タグ付け」で自分を印象づけよう
・日本を理解することが「自分軸」のベースになる
・なぜ「日本発信プロジェクトをミッションにしたのか」
・「大人を信用するな」
・心の中にある「違和感」を大切に
・Think Globally、Act Locally
目次
第1章 世界に飛び立ってトビタテ留学生たち
第2章 衝撃的だった世界のリーダーたちの実力
第3章 「トビタテ!留学」プロジェクトの始動
第4章 トビタテ流人材育成の仕組み
第5章 これから海外へ飛び立つ君たちへ
第6章 私の「越境体験」とトビタテに込めた思い
【発行】リテル/【発売】フォレスト出版




