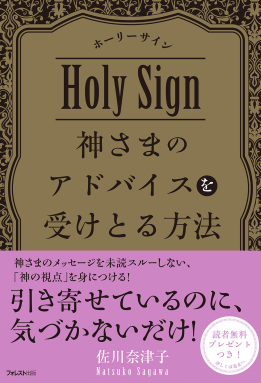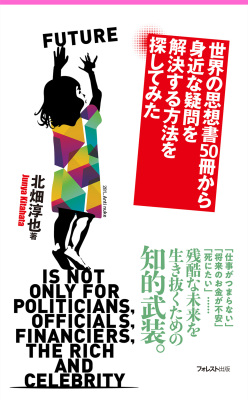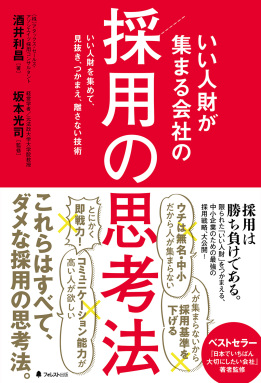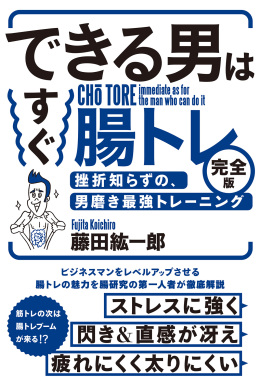著者の関連商品
著者の関連商品
-
読者のみなさまの厚い支持をいただくロングセラーの最新版です。長引くデフレ不況下の日本において、ニーズが高まりこそすれ衰えることは決してない「コスト管理」「原価管理」について、これほどまでに平易にわかりやすく解説した本は他にありません。

POSTED BY寺崎
View More15年間売れ続ける定番ロングセラーの最新改訂版!
本書は、読者のみなさまの厚い支持をいただき
ビジネスマンにとっての定番ロングセラーとなった
『これだけは知っておきたい「原価」のしくみと上手な下げ方』の最新版です。
日本では近年、物価上昇率が上がらない状況が続いています。
日銀が掲げた物価上昇率の目標も、
長い期間にわたって達成されませんでした。
その背景には、根強い消費者の節約志向があるといわれています。
このような状況で
商品やサービスの価格を上げることはむずかしいので、
企業にとってはより一層の原価管理が重要です。
逆にコストダウンができれば、価格は据置きのまま、
企業の利益を増やすことだってできます。
ましてやこの先、日本では増税の傾向が続くことでしょう。
増税分を価格に転嫁できれば簡単ですが、
消費者の節約志向を考えると簡単には踏み切れません。
そのとき力を発揮するのが、しっかりした原価管理と上手なコストダウンです。
原価を知らずにこれからのビジネスは考えられない!
こうしたことを考えても今の日本において、
原価のしくみを知るのはビジネスの常識といっていいでしょう。
「原価とは何なのか?」
「何が含まれているのか?」
「どのように計算して、そこからどうコストダウンするか?」
それらを知らずには、これからの時代のビジネスは考えられません。
この本を読むことで、原価のしくみをしっかり理解し、
原価計算……とまではいかなくても、
ビジネスマンとして日常のコストダウンに
生かせる知識が身につけられます。
この本は2004年に刊行され、
6刷を重ねた定番ベストセラーに
最新の情報を加えて加筆修正したものです。
全体の構成と表現を、わかりやすく整理してあります。
新しい原価計算については、新たなページを設けて説明を加えました。
目次
プロローグ 「原価」のしくみを知るのは仕事の常識です!
第1章 そもそも「原価」とは何だろう
第2章 「原価」はどうやって計算するの?
第3章 それでは「原価」の中身を見てみよう
第4章 正しい「原価」と利益の計算方法
第5章 「原価」のしくみを知るとコストダウンできる
エピローグ あなたの業界の「原価」を見てみよう
-
『神さまが味方する すごいお祈り』の佐川奈津子さんの最新刊です。人生に降りかかる課題を一瞬で鮮やかに反転させる「神の視点」が物語でわかります。

POSTED BY杉浦
View More引き寄せているのに、気づかないだけ!
仕事、昇進、お金、売上、
神さまのメッセージを未読スルーしない、
「神の視点」を身につける!
人間関係、恋愛、結婚、離婚、
家族、両親、兄弟姉妹、
病気、障害、死別……
人生に降りかかる課題を、
一瞬で鮮やかに反転させる
「神の視点」が物語でわかる!
********************
一番大事なことは、
「自分はこの中心軸で、調和の視点を
持ち続ける人間としていられるかどうか? 」
です。
豊かさを受けとる体験をされたいなら、
この中心軸に入った方だけが、
その調和の豊かさの結果を
受け取ることになるからです。―本文より
********************
神さまのメッセージを未読スルーしない!
本書をご購入くださった方全員に、 以下の無料プレゼントをご用意しています!
読者無料プレゼントつき!
『Holy Mirror 神の愛の鏡を思い出す物語』のスペシャル音声
聴くだけで、波動が変わる、空間が変わる、世界が変わる、
願いを夢で終わらせない、思い通りの世界を現実に描き、創造する─。
佐川奈津子氏の最新にして大ヒット音声教材『Holy Mirror』の
エッセンスを詰め込んだスペシャル音声をプレゼントいたします。
※無料プレゼントは、サイト上で公開するものであり、
CD・DVDなどをお送りするものではありません。
※無料プレゼントのご提供は予告なく終了となる場合がございます。
あらかじめご了承ください。
※無料プレゼントは、お客様ご自身で別途お申し込みが必要です。
本書の内容
プロローグ
第1章 仕事・「昇進」
第2章 仕事・「お金」
第3章 仕事・「売上」
第4章 仕事・「人間関係」
第5章 家族・「両親との関係」
第6章 家族・「兄弟姉妹との関係」
第7章 家族・「家族の病や障害」
第8章 健康・「看護、介護」
第9章 健康・「看取り、亡き命」
第10章 恋愛・「恋と同棲」
第11章 恋愛・「離婚」
第12章 恋愛・「結婚」
エピローグ
あとがきにかえて
-
哲学ブームが起こる一方、何かと敬遠されがちな「思想」。保守、リベラル、社会主義……といった言葉から政治性や党派性を感じてしまうからでしょうか。しかし、現代では、物事の根本原理を探る内向きの哲学よりも、「どう生きるべきか」を探求する外向きの「思想」のほうが、重みが増しているのではないかと感じています。そこで本書では、個人的、社会的な疑問の答えを思想書から探すことで、より「思想」を身近に感じてもらい、興味を持ってもらえるような構成にしました。ちなみに、カバーや章トビラのイラストは日本版バンクシーといわれて注目のグラフィティライター281_Anti nukeの作品。グラフィティ(壁や電車などへのラクガキ)とはラップなどとともにHIPHOPの4大要素の1つですが、このHIPHOPも立派な思想の1つなんですよ。

POSTED BYかばを
View More「仕事がつまらない」「将来のお金が不安」「死にたい」……
本書では、人が抱えるさまざまな疑問や悩みの答えを、古今東西の思想書から探ります。
残酷な未来を生きるための知的武装。
取り上げた名著は自分の人生に無関係に思えるものもあるかもしれません。
しかし、「思想」というものが、実は極めて身近であり、社会はもちろん、我々の思考や生き方を深いレベルで縛っていることを実感するはずです。
たとえば……、
Q.どうしてマスコミは偏った報道ばかりするのか?
→W.リップマン『世論』
Q.中国や韓国への差別意識はどこからきたのか?
→杉田聡編『福沢諭吉 朝鮮・中国・台湾論集:「国権拡張」「脱亜」の果て』
Q.金儲けは悪いことか?
→ジェイン・ジェイコブズ『市場の倫理 統治の倫理』
Q.仕事はなぜつらいのか?
→シモーヌ・ヴェイユ『自由と社会的抑圧』
Q.成功者になる条件とは何か?
→マックス・ヴェーバー『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』
Q.無能なリーダーが誕生するのはなぜか?
→カール・マルクス『ルイ・ボナパルトのブリュメール18日』
「哲学」から「思想」が求められる社会へ
「哲学」と「思想」の違いとは?
もちろん厳密な定義というのはありません。
そこで本書では、「哲学」が物事の根本原理を探求するものだとしたら、「思想」は「現実において具体的にどうなるか」を突き詰めて考えるものだと定義しています。
たとえば、「神はいるのか?」「善とは何か?」といったものを徹底的に探求する内向きの思考が哲学だとしたら、どのように考えて行動すれば理想の人生を歩めるか、理想の社会を築けるか、という外向きの思考が思想ということです。当然、「保守」や「リベラル」といった政治思想もそこに含まれます。
哲学は生き方の指針を教えるものもあり、人生や社会の価値判断を考える上で重要です。
しかし、複雑化した世界や生き方が問われることが顕著な現代にあっては、「思想」がより求められているのです。
目次
まえがき 社会からの逸脱を感じたときに
第1章 希望持てないわ、ほんま *社会について
第2章 ある意味、スゴ~イデスネ!!*日本人について
第3章 お前が生き方を決めるな *価値観について
第4章 ウソがホントになる世の中で *政治について
第5章 稼ぐ力も生産性もなかったら… *仕事について
第6章 簡単に啓発される我々の「自己」って… *自分磨きについて
第7章 いつも憂鬱の種は尽きまじ *悩みについて
あとがき 思考しない人生に意味はない
-
2019年現在、人財不足が深刻になっています。これは、一時的なものではなく、少子高齢化が進む日本において、今後も続くものだと思います。そんななか、中小企業で採用予定数が15人程度の中小企業に1万人近くの応募がある会社があるなど、いい人財が集まる会社は日本全国に多く存在します。その格差は広がっていく可能性があります。では、その違いは何なのか? それは思考法でした。つまり、採用に対する考え方が違うのです。その思考を基に、採用戦略、戦術が組まれているのです。「とりあえず採用してから育てる」は危ない――。御社の「採用の常識」を覆す、中小企業の採用担当者&経営者必読の採用バイブルが誕生しました。

POSTED BY森上
View More採用コンサルのスペシャリストが説く、
採用がうまくいっていない
いい人財が集まる会社の採用戦略、大公開!
中小企業の経営者、採用担当者に質問です。
「ウチは無名・中小だから人が集まらない」
「人が集まらないから採用基準を下げる」
「採用してみないとわからない」
「コミュニケーション能力が高い人が欲しい」
「とにかく即戦力!」
あなたは、
このようなことを考えていませんか?
もしそうだとしたら、
残念ながら、
今後も御社には「いい人財」は集まらないでしょう。
なぜなら、
これらはすべて、
採用がうまくいかない会社に共通する
ダメな思考法だからです。
それは、
御社が有名だろうと、無名だろうと、関係ありません。
御社が大手だろうと、中小零細だろうと、関係ありません。
「売り手市場」でも、採用がうまくいっている会社があります。
「同規模の中小企業」でも、採用がうまくいっている会社があります。
「同業界」でも、採用がうまくいっている会社があります。
「同条件の企業」でも、採用がうまくいっている会社があります。
では、
いい人財を「集める」ではなく、
いい人財が「集まる」会社は、
どういう考え方で採用活動をし、
採用戦略を練っているのか?
その思考法&実践法を公開したのが本書です。
著者は、
中小企業の採用コンサルのスペシャリスト。
加えて、
ベストセラー『日本でいちばん大切にしたい会社』
著者が完全監修。
この最強タッグが、
人財不足で悩む中小企業のために、
いい人財を集めて、
見抜き、つかまえ、離さない技術を徹底解説します。
【内容の項目】※一部抜粋
◎いい採用ができない会社の5つの理由
◎採用が下手な会社ほど、「即戦力」「コミュニケーション能力」を求める
◎「人財」ではなく、「人手」の採用になっていないか?
◎「誰を採用するか」以上に大切なのは、「誰が採用担当か」
◎「集める」ではなく、「集まる」
◎「採用してみないとわからない」のウソ
◎採用パイプライン
◎採用の4Pマーケティング戦略
◎いい人財が集まる採用基準の設定法、選定法
◎自社に合った採用方法の見つけ方
◎効果的なスカウトメールの書き方
◎求職者に興味を持たせる技術
◎見極め、惹きつける面接術
◎間違った採用をリカバリーする方法 and more!
気になる本書の内容
本書の内容は以下のとおりです。
はじめに――あの会社はどうして優秀な人財を採用できるのか?
第1章 採用をなめてはいけない──なぜ採用がとても大事なのか?
いい採用ができない会社に共通する「最悪の勘違い」
「人さえいれば……」という時代!?
採用がうまくいかない、根本的な原因
やっぱり、採用も「始めが大事」──A good beginning makes a good ending.
「始め」を疎かにするデメリット
「採用を真剣に考える」とは、実際どういうことか?
焦って人を採用すると、ロクなことがない
イメージしていた人物像に近い人が応募してきた!
採用後に発覚した期待外れの「即戦力」
「採用の失敗」だけは、絶対に避けるべき失敗
採用は「点」でなく、「線」と「面」で考える
確かに「人手不足にあえいでいる」けれど……
採用失敗のダメージは、思う以上に大きい
組織力も売上アップも、まずは素材から
成果が上がる組織の公式
一流のリーダーでも、限界はある
人を見抜く力こそ経営力
採用は「競争」とわかっているか?
採用の市場原理
「採用してみないとわからない」のウソ
選考で特にどこを重視したかで、その会社の経営力がわかる
採用は、勝つか負けるか
求職者の心理プロセスの中身
なぜ営業活動より採用活動のほうが厳しいのか?――限られたパイを奪い合う戦い
採用活動は、種まき·水まき活動である
学生が成長する機会
「企業の社会的責任」を果たすのが採用活動――選考する企業側の社会的責任(CSR)
本気で向き合う選考プロセスが生み出す大きなメリット
だから、採用をなめてはいけない――第1章のまとめとして
第2章 いい採用ができない会社の5つの理由
ダメ採用は、ダメ営業?
ダメ営業マンは何が間違っていたのか?
ダメ営業マンも採用に苦戦している人も、変われる
「片手間でやっている」から、うまくいかない──いい採用ができない理由①
片手間でやっているかどうかの基準
大企業のいい採用ができる理由は、知名度があるからだけではない
いい採用ができる中小企業にあって、いい採用ができない中小企業にないもの
「他責にする」から、うまくいかない──いい採用ができない理由②
同じ商品でも売れる営業、売れない営業の違い
トップセールスマンの「商品への自信」に学ぶ「自社への自信」のつけ方
他責にした瞬間に起こること
「相手を知らない」から、うまくいかない──いい採用ができない理由③
知らなければ、戦略も立てられない
求職者について知っておくべきこと
情報は、待っていても入ってこない
「マーケットを知らない」から、うまくいかない──いい採用ができない理由④
「マーケットを知っている」とは、どういうことか?
採用のマーケティング
「行き当たりばったり」だから、うまくいかない──いい採用ができない理由⑤
「あたりまえ」になっているか?
採用のPDCA
自社の採用活動を再チェック――第2章のまとめとして
第3章 いい採用を実現させるために案外やっていないこと
経営の問題の根源は、「採用基準」にあり──誰を採用するか①
問題解決の手順の第1ステップ
安易に採用基準を下げると、組織は疲弊する──誰を採用するか②
「採用基準」を下げていいのは、この2パターン
採用基準を下げるかどうかは、入社後の教育をセットで考える
3つの覚悟があれば、採用基準を下げてもいい
採用の質を下げても、お客様への提供の質は下げられない──誰を採用するか③
質の優先度を下げる会社、増加中
採用するうえで、一番やってはいけないこと
誰をバスに乗せるか──誰を採用するか④
行き先を決める前にやるべきこと
VUCA時代に求められる経営戦略とは?
「バスに誰を乗せて行きたいか?」を言語化する
採用を妥協したらどうなるか?──誰を採用するか⑤
世界的名著の教え
採用後の教育でなんとかなる!?――私の失敗談を交えて
デメリットは、売上減だけにとどまらない
「人財」ではなく、「人手」の採用になっていないか?
常に探し続ける
いい人財を見抜く基準──採用基準を設定する正しい方法①
採用基準を下げず、採用要件を盛り込みすぎない
人財の素質を見抜く2つのポイント
「先天的·後天的能力」を見抜く──採用基準を設定する正しい方法②
人間の意識レベルには5つの階層がある――ニューロロジカルレベル
人の意識を変える手順――正しい「場」を設計する
コミュニケーション能力は、入社時には必要のない能力
「後天的に」伸ばせる能力は、採用基準から外す
「価値観」のマッチングを重視する──採用基準を設定する正しい方法③
教育しても変えられないもの
絶対に外せない採用基準
いい人財を「集める」ではなく、いい人財が「集まる」会社の採用基準
面接官の主観に左右されない採用基準を設定するコツ
「誰が採用するか」で採用の質は変わる
人生を変えた1冊の本と1本の電話
「何をするか」より「誰とするか」
採用とは、人財を供給する活動
採用担当にふさわしい人、ふさわしくない人
採用する「人数」と「期限」を定める──どう採用するか①
なぜ「期限」設定が必要なのか?
理想的な期限設定
中途採用で「期限なし」は危ない
採用戦略·シナリオをつくる──どう採用するか②
戦略がなければ、どんな戦術も効果なし
数値化して、全体を俯瞰して管理する――採用パイプライン
採用パイプラインを使ったシナリオ作成例
第4章 いい採用を実現させる具体的なステップ
採用がうまくいっている会社の戦術とは?
作成した戦略をどう実現するか?
御社を「知らない」から応募がない──いい人財を集める①
人は未知のものを怖がり、不安だから近寄らない
知らない=怖い
「知らない」を「知っている」に変える努力をしているか?
自社を「知ってもらう」方法──いい人財を集める②
採用の4Pマーケティング戦略
自社を知ってもらう方法
「リアル」「早期化」重視の時代
強くて愛される会社がやっていること
自社に合った採用方法の見つけ方
エントリーは、「量」より「質」──いい人財を集める③
量に比例してかかる3つのコスト
「はじめまして」で伝えるべき情報──いい人財を集める④
人が動かない4つの理由
目には入っても、脳には入っていない
「知らない」を「知ってもらう」に変える秘策――「インパクト」×「コンパクト」
「はじめまして」の後につなげるべきこと
効果的なスカウトメールの書き方
求職者に興味を持たせる技術──いい人財を惹きつける
会社説明会では、説明はいらない
求職者が求める知りたい情報とは?
知名度が低い会社がマッチングの精度を上げた方法
見極め、惹きつける技術──いい人財をつかむ面接術
採用面接を行なう2つの目的
面接官は誰がやるのか?――いい人財をつかむ2つの役割分担
相手のホンネを引き出し、こちらに惹きつける面接のスタンス術
見極めるポイントは、結果主義でなく、プロセス主義――できる面接官が持っている「掘り下げ力」
掘り下げることで、惹きつけられる
適性検査と人間の役割
志望動機は聞かない
志望動機とは、自分と会社とをつなぐもの
自社が応募者にどういうポイントで選ばれたいか?
いい人財を逃さず「動機づけ」する技術──内定後フォローの方法
内定辞退者続出の時代
内定者フォローが必要な場合のやり方――2つのステップ
間違った採用をリカバリーする方法
人間が幸せを実感するとき
「日本でいちばん大切にしたい会社」に学ぶ人財採用の目的
「間違った採用」の定義
ミスマッチを防ぐ施策
間違った採用をしてしまったら
おわりに -
View More
筋トレから腸トレの時代へ
免疫細胞の60~70%が存在する人体最強の免疫器官であるばかりか、
脳に匹敵する1兆以上もの神経細胞ニューロンが存在する
考える臓器でもある「腸」。
腸をトレーニングすれば、
ストレスに負けない免疫の基礎が固められ、
生命力あふれる生き方が可能になります。
ビジネスマンをレベルアップさせる
「腸トレ」の魅力を腸研究の第一人者が徹底解説。
本書で紹介する「腸トレ」は、
ただ腸のことを考えた健康法の実践だけが目的ではありません。
腸内細菌が体に与える影響を踏まえ、
自分が求めているものをはっきりさせ、
各々に合った「腸トレ」を組み立てることで、
あなたが求めていたものを手に入れるのです。
それは前向きな思考だったり、よい目覚めだったり、
スリムで健康な体だったり、充実した長寿だったりするでしょう。
【今すぐ腸トレを取り入れるべき人】
□うつうつとしてやる気が出ない、幸せを感じられない
□疲れやすく、風邪をひきやすい
□生活リズムが狂っている
□頭脳明晰になりたい
□だんだん太り始めた
□老けたくない
□将来の健康や生活が心配
□今までの自分を変えたい
――腸を変えれば、人生が変わります
はじめにより
「脳トレ」も「筋トレ」もテレビ番組や書籍、雑誌など、
ありとあらゆるところで目にしますし、
もはや一般名詞といってもいい状態です。
ところが、「腸トレ」というのはほとんど目にすることがありません。
腸の研究者としてはたいへん遺憾ながら、
どうやら腸は軽んじられているようです。
しかし、
長年の研究で腸のスゴさ、奥深さを実感してきた私にいわせれば、
腸トレほど、さまざまな効能をもたらしてくれるものはありません。
腸をトレーニングして整えることは、
さまざまな効能をあなたにもたらしてくれるのです。
特に筋トレは見た目にも効果がわかりやすく、
精神面でも自信が持てるようになるため、
意欲的に活躍しているビジネスマンのあいだでここ数年、
一大ブームになっているようです。
それならば、ぜひそこに「腸トレ」を加えてみてください。
ぜひ気楽に、楽しみながら「腸トレ」にチャレンジしてみてください。
きっと人生がポジティブなものに変化していくはずです。
気になる本書の内容
本書の目次は以下のとおりです。
はじめに
Chapter1 男性に“腸トレ”をオススメする8つの理由
その①:腸トレでストレスに強くなれる
その②:腸トレで「折れない心」を養う
その③:腸トレは「直感力」を鍛える
その④:腸トレで「頭脳明晰」になろう
その⑤:腸トレが質のよい眠りに導く
その⑥:老けづらく、太りにくくなる
その⑦:ビジネスマンの多くが悩む過敏性腸症候群も解決
その⑧:私が特に男性に腸トレをおすすめしたい理由
Chapter2 厳禁!腸トレを邪魔する6つのNG
NG①:可愛がりすぎは逆効果。気難しい腸
NG②:清潔すぎる環境は、常在菌が家出する
NG③:早食いはすべてにおいてよいことなし
NG④:「押し付けごはん」を食べてませんか?
NG⑤:「菜食主義や粗食は健康によい」を疑おう
NG⑥:50歳を過ぎたら、炭水化物に気をつけよう
Chapter3 藤田式「最強の腸トレ」メソッド10
腸トレ①:発酵食品には、賢いとり方がある
腸トレ②:活性酸素を避け、抗酸化習慣を身につけよう
腸トレ③:万能薬「短鎖脂肪酸」をどんどん作りましょう
腸トレ④:必要な油と、不要な油を理解しよう
腸トレ⑤:水の飲み方にも健康になるコツがある
腸トレ⑥:腸を生まれ変わらせる「ボーンブロス」
腸トレ⑦:糖質依存を断ち切ろう
腸トレ⑧:週末プチ断食でライフスタイルを変える
腸トレ⑨:平均体温を1℃あげてみよう
腸トレ⑩:体からの“お便り“をじっくり読もう
Chapter4 「腸トレ」習慣化のための3つのステップ
ステップ①:正しい理由と目標を掲げる
ステップ②:TODOリストはこうして作ろう
ステップ③:記録をつけてフィードバックする
【発行】三五館シンシャ/【発売】フォレスト出版